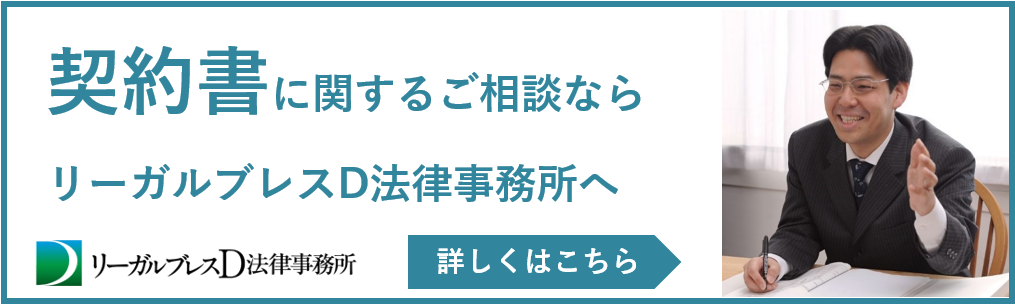契約書を作成するに際して押さえておきたいポイントとチェック事項を解説
【ご相談内容】
取引先と契約をする場合、当社は法務担当者がいないため、営業担当者が契約書を作成する必要があります。もっとも、営業担当者は法務知識に明るいとはいえず、自ら契約書を作成する能力を持ち合わせていないことから、インターネットで検索した契約書をコピペして用いているのが実情です。
先日、見様見真似で作成した契約書に不備があり、当社は甚大な被害を受けたことから、時間をかけてでも適切な契約書を作成しようという機運が社内で高まっています。
どのような点に注意して契約書の作成を行えばよいのか、教えてください。
【回答】
契約書を作成するに際しての注意事項は、細かいことを挙げればきりがないくらい無数に存在します。これらの事項をすべて理解した上で、契約書の作成を実施するというのは実際のところ不可能と言わざるを得ません。
そこで、本記事では枝葉末節の箇所は触れず、幹(骨格)となる部分に絞って解説を行います。
その内容ですが、まずは契約書の大まかな構成を示したうえで、形式面での注意事項、内容面での注意事項、いわゆる一般条項と呼ばれるたいていの契約書に用いられる条項を利用する上でのポイントに触れていきます。そして、最後に雛形を用いることの効用と注意点についても触れておきます。
なお、他人が作成した契約書をチェック・審査する場合のポイントについては、次の記事をご参照ください。
【解説】
1.契約書を作成する目的
契約書を作成する目的には様々なものがありますが、代表的なものとして次の3つがあげられます。
(1)合意成立の事実を確認すること
契約は口頭でも成立するという話をどこかで聞いたことがあるかもしれません。たしかに、一部の契約を除いて、法律上は契約の締結方法について特に規制を設けていません。ただ、口頭で合意した事項は、時の経過とともに記憶が曖昧となったり、(悪意なく)記憶が書換えられたりすることは十分あり得る話です。このため、双方当事者の記憶が異なる場合、合意内容を巡る紛争が生じることになります。
そこで、契約当事者の記憶の曖昧性・書換えを排除することを目的として、契約書という媒体物に残すことが重要となります。
以上の通り、契約書を作成する目的として、合意成立の事実を確認できるようにすることがあげられます。
(2)紛争解決基準となること
一方当事者において契約違反が発生した場合、たちまち緊張関係となり、紛争の火種がくすぶることになります。
もっとも、契約書に当該紛争が生じた場合は××と処理する旨ルールが定められていた場合、両当事者はそのルールに従って対応すれば、大きな混乱を招くことなく処理することが可能となります。
以上の通り、契約書を作成する目的として、当事者間での紛争解決基準を設定できることがあげられます。
(3)証拠を確保すること
上記(1)でも触れた通り、口頭での契約を行った場合、どうしても契約当事者の記憶の曖昧性・書換え可能性等により、契約内容を巡っての紛争が起こりがちです。
しかし、契約内容を書面等の媒体物に残している場合、その媒体物を確認さえすれば、どちらの言い分が正しいか一目瞭然となります。
以上の通り、契約書を作成する目的として、自らの主張を裏付けるための最良の証拠になるということがあげられます。
2.契約書の基本的な構成
一般的な契約書であれば、おおむね次のような構成で作成されています。
・表題(タイトル)
・前文
・本文
・後文
・作成日付
・署名押印
それぞれについて、ポイントを解説します。
(1)表題
表題(タイトル)については、特別決まり事はありません。
したがって、単に「契約書」と書くだけでも問題ありませんし、表題(タイトル)を書かなくても、契約書の有効性に影響を与えることはありません。
なお、極端な話ですが、契約書で定められている内容が売買取引に関するものであるにもかかわらず、表題(タイトル)が「賃貸借契約書」であったとしても、やはり契約書の有効性に影響を与えることはありません。なぜなら、契約書に定めている取引が何に該当するのか、法的に問題がないか等を決める判断基準は、表題(タイトル)ではなく、本文で定められている内容となるからです。
とはいえ、一般的には、契約書に記載されている内容が一目で分かるように表題(タイトル)が付されるのが通常です。内容と表題(タイトル)が異なるというミスはできれば避けるべきですし、あまり奇をてらった表題(タイトル)を付すのは考え物です。
ところで、契約書を作成した場合、印紙の貼付が必要となる場合が多いのですが、印紙税の対象となる取引の判断基準は、表題(タイトル)ではなく、本文で定められている内容から導き出される(解釈される)取引類型となります。
ときどき、印紙税の負担を避けるべく、定められている内容からして請負契約であると解釈されるにもかかわらず、業務委託契約(準委任)と表題(タイトル)を付すということが行われているようですが、全く意味はありません。この点はご注意ください。
(2)前文
前文についても、必ず記載しなければならないとされているわけではなく、記載するにしても特段の決まり事はありません。
もっとも、一般的には、契約当事者と契約内容の特定(表題・タイトルよりはやや詳し目に記載する)を行うことを目的として記載されています。例えば、次のような一文です。
(例)
×株式会社(以下「甲」という)と△(以下「乙」という)とは、□マシン(以下「本商品」という)の売買につき、以下の通り動産売買契約を締結する。
(3)本文
当事者が合意した内容を記載する、まさしく契約書の最重要項目となります。
一般的には、「第×条」と大分類し、その第×条を再分類する場合は「第×項」とし、さらに第×項を細かく分ける場合は「第×号」と記載します。
(例)
第×条(契約の解除)
1 乙において次の各号のいずれかに該当した場合、甲は本契約を解除することができる。
(1)納期までに本商品を引き渡さなかったとき
(2)(以下省略)
2 前項による解除を行った場合、甲は乙に対して、損害賠償を請求することができる。
上記例でいえば「第×条」は文字通りです。算用数字の「1」と「2」の部分が第1項、第2項に該当し、( )数字の部分が第1号、第2号となります。
ところで、上記では第×条の横に「契約の解除」という表題(タイトル)を付していますが、この表題(タイトル)を付すかは任意です。別に付けなくても構いませんし、上記(1)の表題で解説した通り、内容と表題(タイトル)にズレがあっても契約書の有効性に影響を与えません。とはいえ、内容と表題にズレがあった場合、見栄えの良い物ではありませんし、読みにくい契約書であることは間違いありませんので、このようなズレはできる限り回避したいところです。
(4)後文
後文についても、絶対に記載しなければならない事項という訳ではなく、無くても契約書の有効性に影響を与えません。
ただ、一般的には、当事者間で合意が成立した事実と契約書の作成通数が記載されています。例えば次のような一文です。
(例)
本合意成立の証として契約書を1通作成し、甲乙相互に署名押印の上、原本を甲、副本を乙が保有する。
(5)作成日付
契約書がいつ作成されたのかを裏付けるものとして重要な意義を有するはずなのですが、空欄になっていたり、実際に作成した日付と異なる日が記入されたりして、現場実務ではしばしば混乱が生じる項目といえます。
特に契約書の本文中に、「本契約の有効期間は、本契約締結の日から1年間とする」と定められていた場合、作成日付は契約開始時期と契約有効期間の判断基準となることから、正確な日付を記入したいところです。
なお、契約書のバックデートに問題が生じることについては、次の記事をご参照ください。
契約書のバックデートは可能? 契約書作成日の意義について弁護士が解説
(6)署名押印
細かな話ですが、「署名押印」の場合は自署して押印となり、「記名押印」の場合は押印のみとなります(自署するべき事項が予め印刷されている、ゴム判を押すことで代用する等の理由で、本人自らがサインしないため)。
なお、法人取引の契約交渉が終了し、いざ契約書を締結するという段階でよく問題となるのが、契約書の署名押印欄に記載されているのが、代表取締役ではなく、××部長といった代表者ではない肩書となっている場合です。上場企業や日本有数の大企業と契約書を取り交わす場合に見かけることが多いのですが、たしかに、理論的に考えた場合、××部長と称する人物が代表取締役より契約締結権限を授与されているのであれば法的に問題がなく、契約も有効に成立します。しかし、××部長に契約締結権限があるのかについて、一方当事者からすれば客観的に判断が付きませんし、万一社内処理に誤りがあり、後で契約は無効であると主張された場合は泣くに泣けない状態となります。
一方当事者としては、委任状を徴収するのが一番確実なのですが、難しい場合、メール等で契約締結権限があるのかを問合せ、先方より契約締結権限ありという回答をもらうなどして証拠を残すといった対策が必要となります。
3.契約書を検討する際の形式的留意事項
契約書を作成する場合、一般的な構成は上記1.で解説した通りです。
ここでは、構成以外で契約書を作成するに当たり、具体的な合意内容(=本文に定める内容)以外で注意しておきたい形式的事項につき記述します。
(1)要式契約の確認
契約に関する解説書を読むと、必ず契約は口頭でも成立し、契約書の作成は原則不要であると書かれています。
この指摘は間違いではありません。
ただ、法律の世界では原則があるのであれば、その例外は何かを探る必要があります。なぜなら、その例外が現場実務では極めて重要となることが多いからです。
この点、必ず契約書を作成しなければならない「例外」ですが、代表的なものとして、保証契約(民法第446条第2項)、定期借地契約(借地借家法第22条第1項)、事業用定期借地契約(借地借家法第23条第3項)、定期借家契約(借地借家法第38条第1項)、任意後見契約(任意後見契約法第3条)などが該当します。
特に債権回収の場面などにおいて、「取引先が支払ってくれないので、取引先社長に掛け合ったところ、取引先社長が肩代わりして支払うと口頭で約束してくれた。録音も残っている。」といったご相談を受けることがあるのですが、残念ながら口頭での保証契約は認められない以上、法的には意味のない録音となります。
上記は一例ですが、無駄足を踏まないためにも、契約書の作成が義務付けられている契約とは何か(なお、作成が義務付けられている契約は「要式契約」と呼ばれます)を、しっかり押さえておく必要があります。分からない場合は、必ず弁護士に確認するべきです。
(2)用語例に注意
契約書作成に際し、どこかの書式をコピペした場合によく生じるのですが、用語例に乱れが生じたりします(例えば、「書面」と「文書」の混在、「承諾する」と「同意する」と「了承する」の混在など)。
さて、上記の例程度であれば致命傷にならないのではと思われる方もいるかもしれません。しかし例えば、書面での通知には電子メールの送信を含むと定められていた場合、あえて文書と定めたのであれば電子メールを含まないと解釈されることになります。そして、契約書上、文書での通知と定めているにもかかわらず、電子メールだけで連絡していたとなると、連絡方法に不備があったという認定になってしまいます。
細かいと思われるかもしれませんが、日常用語では同義語であっても、法解釈上では異なるものとして取り扱われる可能性があることを認識する必要があります。
また、日常用語と法令用語とで意味が異なるにもかかわらず、これを意識せずに用いている場合があります。例えば、「社員」という用語は、日常用語では従業員のことを指しますが、法律上「社員」は株主等の出資者のことを指し、従業員のことは指しません。契約内容如何によっては、当事者間で社員の範囲につき異なる認識であったという事態にもなりかねませんので、注意が必要です。
さらに、自社内だけで意味が通じるオリジナル用語、業界特有の用語、カタカナ言葉、略語(特に3文字のアルファベットで示す省略用語)などは、第三者、特に裁判官が理解できず、複数の解釈論が成立してしまうリスクがあります。このような事態となった場合、契約書が物事の判断基準とならず、かえって争いの種を生み出すだけのお荷物扱いとなりかねません。略語は用いないという意識を徹底したいところです。
(3)契約書の体裁
契約書を作成した場合、よほどのことがない限り、A4用紙1枚に収まることなく、たいていは4枚前後の分量になることが多いかと思います。
この場合、A3用紙の両面に印刷して1枚の契約書として編成するという方法も考えられますが、A4用紙を4枚編綴するという方法が一般的かと思います。
この4枚編綴という方法を採用する場合の注意点ですが、ホチキス止めして契印を押す、又は製本テープを用いてテープと紙の境目に契印を押す、といった方法を取るべきです。なぜなら、製本化しないまま最後のページだけに署名押印し、その最後のページだけ相手当事者に提出した場合、残りのページに定められている契約内容をすり替えられてしまうリスクが生じるからです。
時々、署名押印欄だけで独立の1ページになっている契約書式を見かけますが、そのページだけを相手に提出した場合、例えるなら捨印を押した空白の紙を提出したのと同じ状態となります。後で契約書に記載されているような合意を行っていないと主張しても、ひっくり返すことはかなり難しいことを肝に銘じるべきです。
4.契約書の内容面で一般的に検討するべき事項
契約書を作成する場合、取引類型及び当事者間の合意内容等に応じて、様々な考慮事項が出てきます。したがって、××取引であれば××とするべき…といった一義的な結論にはならないのですが、ある程度の共通項を抽出することは可能です。
ここでは、契約書を作成する上で、共通する考慮事項につき解説します。
(1)法的有効性・法的拘束力の具備
契約書を作成する目的の1つとして、相手当事者が契約違反した場合、国家権力(裁判手続き)を用いて強制的に契約内容を実現できるようにする、というものがあります。
ただ、国家権力を用いる以上、法的に有効な契約内容であり、かつ法的に実現可能な契約内容であることが前提となります。そこで、契約書を作成するに際しては、次に記載する3点を意識する必要があります。
・契約の当事者が適切か
例えば、個人(自然人)と取引を行っていると認識していたが、実は契約書には見たこともない法人の署名押印があったという場合(逆も然りです)や、個人事業主であるにもかかわらず、当事者欄には屋号しか書いていなかったという場合(個人事業主である以上、その代表者個人の署名押印が正式な署名押印方法です)が典型的な失敗例です。
相手当事者が不正確な場合、契約違反を誰に問えばよいのか分からなくなるという問題が生じますので、注意が必要です。
・強行法規違反はないか
例えば、消費者と取引する場合、消費者契約法や特定商取引法において、契約に違反した消費者に対し、事業者が損害賠償責任を追及する場合は一定の制限が課されています。そうであるにもかかわらず、この制限を超えた損害賠償責任を消費者が負担する旨契約書に定めたとしても、その契約は無効とされます。
一方当事者にとって都合の良い契約書を作成したとしても、強行法規違反があれば契約内容通りの履行を求めることができなくなることに注意が必要です。
なお、強行法規違反以外にも、民法に定める公序良俗違反、各種業法違反、裁判例等を通じて違法と解釈されている条項などにも気を配る必要があります。
・実現可能性はあるか
例えば、契約に違反した場合、違反当事者は相手に対し土下座して公開謝罪するという内容を定めたとしても、法的に強制することは困難です。なぜなら、他人(国家権力を行使する者)が違反当事者を縛り上げ、違反当事者の手足を逐一動かして、土下座という行為に至らしめること自体が人道に反する行為といえるからです(根本的に、謝罪意思がないのに見せかけの土下座をさせること自体がナンセンスともいえますが)。
契約に違反した場合の原則的措置は損害賠償である、というのが法律の基本発想です。この基本発想を超えた制裁措置を定めても、法的に実行することが不可能であるという点を意識する必要があります。
(2)救済手段の確保
上記(1)において、契約違反した場合の原則的措置は損害賠償であると記述しましたが、この損害賠償責任の追及が制限されていないかを検討することがポイントとなります。例えば…
・損害賠償責任を追及する期間が短くなっていないか
・損害賠償責任を追及するための条件が厳しくなっていないか
・損害賠償責任を追及した場合の損害内容及び金額について制限が課せられていないか
といった事項を意識する必要があります。
なお、具体的な検討事項については、次の記事をご参照ください。
契約書に定める「損害賠償条項」の考え方・チェックポイントを解説
5.合意事項を条項化(本文へ記載)するに際して押さえておきたい事項
ここでは、多くの契約書で定められることが多い内容(いわゆる一般条項と呼ばれるもの)を取り上げ、簡単にポイントを解説します。
(1)目的条項
取引を開始するに至った経緯、どのような取引を行うのか、取引を行うことによって当事者は何を実現しようとしているのか等を本来記載するべきなのですが、この目的条項は非常に簡易に定められることが多いようです。
ただ、2020年4月1日より施行された改正民法で新たに設けられた契約不適合責任に対応させる場合、この目的条項の充実化が1つのポイントになると考えられます(契約不適合=契約目的を達成しえなかった場合と解釈されるため)。
したがって、できる限り具体的に記載することをお勧めします。
(2)権利義務に関する条項
「権利義務に関する」と書くと、難しく考える方がいるかもしれません。
ここでは端的に、この契約によって、一方当事者は何を要求できるのか、その要求に対して相手当事者は何をしなければならないのか、といった通常取引を行う中で発生するやり取りを抜き出し、その内容を条項化するとイメージすれば十分です。
意外とこれができていないため、一方当事者は××までしてくれるものだと思い込んでいたのに対し、相手当事者は××まではしなくてもよいと認識していたといった形でトラブルが生じます。取引の流れ・一連の経過を考慮して、できるだけ具体的に定めるのが重要となります。
(3)条件、期限に関する条項
上記の権利義務に関する条項と一部重複する内容となるのですが、例えば、某作業を開始するよう要求する場合、前提として着手金を支払わなければならないといったことが条件に関する条項となります。
また、某作業は×月×日までに完了させなければならないといったことが期限に関する条項となります。
おそらくは取引を開始する上で、事前に詰めた交渉を行い、合意に達している事項のはずですので、その合意事項を契約書に反映させることがポイントとなります。
(4)契約期間、契約終了事由、契約終了方法に関する条項
いつからいつまで取引を行うのかを定めるのが契約期間に関する条項となります。なお、これに関連して契約期間を更新する場合の条項も一緒に定めることもあります。
次に、契約終了事由に関する条項ですが、このまま契約を継続することは支障があると考える事由を定めることがポイントです。多くの場合、相手当事者が契約に違反した場合はもちろんのこと、相手当事者の信用状態に不安が生じた場合(破産申立を行った等)、相手当事者との信頼関係構築が難しくなった場合(代表者や大株主が変更された、M&A・組織再編により他社の影響力が強くなった等)などを定めています。
さらに、契約終了方法に関する事項ですが、契約を終了させるためには何をすればよいのかを定めることになります。例えば、上記のような契約終了事由に該当した場合は当然に契約が終了となるといった規定を置く、あるいは終了事由に該当しなくても、一方当事者が一定の期間を置いて通知すれば中途解約可能とする規定を置く、というのが典型例です。
これらの条項は、相手に対していつまで契約の拘束力を維持させるのかという視点と、当方はどうすれば契約の拘束力から解放されるのかという真逆の視点を持ち合わせる必要があることに注意が必要です。
(5)契約の締結・履行に要する費用負担に関する条項
例えば、物の引渡しが必要となる取引であれば、運送費用はどちらが負担するのかを定めることになります。あるいは、不動産取引であれば、境界確定費用や固定資産税等の税金負担について、いつを基準としてどちらが負担するのかを定めることになります。
なお、契約書の作成自体に費用が発生する場合(公正証書を作成する場合など)や印紙代の負担についても、誰がどのように負担するのかを定めることになります。
(6)法令対応として必要な条項
例えば、個人情報を取扱うのであれば個人情報保護法に則った情報管理条項が、反社会的勢力が取引に介入しないようにするための暴力団排除条項などが該当します。
(7)紛争解決手段、準拠法、合意管轄に関する条項
紛争解決手段に関する条項について、日本国内に活動拠点を置く当事者であり、かつ日本国内での取引を想定している場合は、日本国の裁判手続きを利用する旨定めることが通常です。そして、これに関連し、どの地域の裁判所を利用するのか定めるのが合意管轄条項となります。一方、海外に活動拠点を置く当事者である場合、裁判手続きよりも仲裁手続きを用いて紛争解決を図るとする条項を定めることが多いようです。なお、仲裁手続きを利用する場合、どの国に置かれている仲裁手続きを利用するのかを明記する必要があります。
次に、準拠法に関する条項ですが、これはどの国の法律を適用するのかという問題です。日本国内に活動拠点を置く当事者であり、かつ日本国内での取引を想定している場合、当然に日本法を前提にしているためあえて定めないこともあります。しかし、海外に活動拠点を置く当事者である場合、どの国の法律を適用するのか明確にしておかないことには、例えば、日本法では認められていない権利が海外では認められているとして、予想外のリスクを負担することになりかねません。したがって、海外取引の場合は、準拠法に関する条項を定めることは必須となります。
6.当事務所でサポートできること
契約書を作成する上での注意点や、比較的用いる頻度の多い契約条項(本文)のポイントを解説しました。
ところで、契約書を作成する場合、“インターネット等で公開されている契約書の雛形を用いれば事足りるのではないか?”と思われる方がいるかもしれません
たしかに、どのような契約条項(本文)を定めるべきかが分かりますので、検討するべき項目漏れを防止できるという点で優れていると思います。
しかし、例えば、一口に業務委託といっても、準委任型の業務委託と請負型の業務委託とでは検討するべき事項が異なってきます。また、準委任型業務委託には業務遂行が主たる内容となる類型がある一方で、成果の完成が主たる内容となる類型も存在します。さらに、請負型の業務委託には、有体物の製造が目的となるものがある一方で、無体物の制作を目的とするものがあります。
つまり、取引内容に応じて検討するべき事項が異なる以上、必要となる契約条項(内容)も異なってくるのであって、業務委託契約書とタイトルが付された雛形を用いれば、必要十分な契約書が作成できるわけではありません。言い方は悪いですが、思考停止で雛形をそのまま用いてしまった場合、合意内容の記載漏れはもちろん、希望する法的効果が得られない、想定外のリスクを負担する等のトラブルを抱えることに繋がります。
トラブル回避のためには、雛形を用いて作成した契約書について、当事者間で合意した取引実情と合致するものなのか、義務・負担が偏っていないかという視点で専門家に検証してもらうことが重要です。
契約書チェックについては是非当事務所をご利用ください。
<2023年2月執筆、2023年9月更新>
※上記記載事項は弁護士湯原伸一の個人的見解をまとめたものです。今後の社会事情の変動や裁判所の判断などにより適宜見解を変更する場合がありますのでご注意下さい。