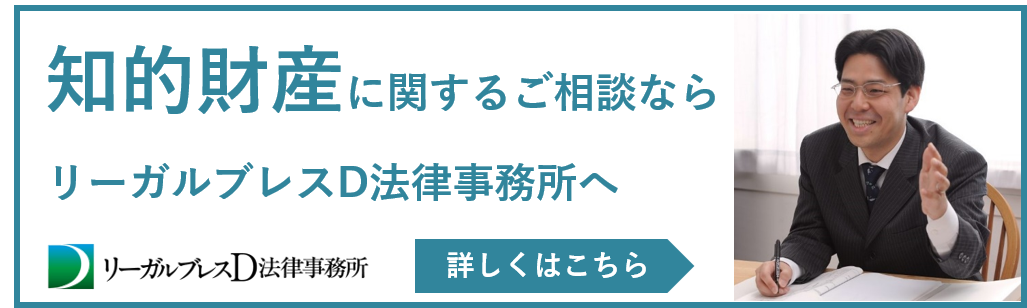著作権に関する契約(利用許諾・ライセンス、譲渡、制作)のポイントについて解説
【ご相談内容】
当社は映像コンテンツ等の制作及び販売を行っている会社です。
これまでは特定の事業者との取引しかなかったのですが、新たな取引先を開拓しようと考えています。
そこで、取引先と締結することになる、コンテンツ(著作物)に関する契約書の整備を図ろうと考えているのですが、どのような点に注意して契約書を作成していけばよいのか教えてください。
【回答】
著作権に関する契約について、譲渡する場合は売買契約を、利用許諾(ライセンス)する場合は賃貸借契約を、制作する場合は請負契約をそれぞれ参照すればよいと考える方もいるようです。
たしかに、基本的な考え方として強ち間違っているとはいえません。
しかし、民法とは別に著作権法が制定されている以上、民法の考え方のみで対応するのは間違いと言わざるを得ません。著作権法独特の考え方を考慮しながら、契約書の作成を図る必要があります。
そこで、本記事では、著作権法に関する概要を簡単に確認した上で、著作物利用(ライセンス)契約、著作権譲渡契約、著作物制作契約の3つについて、ポイントを解説します。
【解説】
1.著作権法の概要
(1)著作物とは
著作物とは、「思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの」をいいます(著作権法第2条第1項第1号)。
著作物に関するポイントは次の3点です。
・創作的なものであること
他人の作品を模倣しただけでは、作者独自の思想感情を表したとはいえません。逆に偶々他人の作品と類似した場合であれば、著作権侵害は成立しないことになります。
・外部に表現したものであること
他人に話す、紙に描くなどの外部への表現行為が必要となります。頭の中で考えただけのアイデアが著作権法上の保護対象とならないのは、この要件を充足しないからです。
・文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの
芸術性が求められるわけではありませんが、機械的・実用的な製品などは著作物に該当しないことになります。もっとも、プログラムは実用的なものですが著作物に該当します。
(2)著作者とは
著作者とは、「著作物を創作する者」をいいます(著作権法第2条第1項第2号)。
著作者について留意しておきたいポイントは次の3点です。
・法人著作、職務著作(著作権法第15条第1項)
一昔前に「職務発明」に該当するとして、一従業員が会社を訴え、会社が200億を支払うよう命じる判決が出たことを覚えていないでしょうか。これは特許法においては、従業員が職務遂行過程で発明を行った場合、その発明に係る権利は従業員個人に帰属すること、会社が譲り受けるためには相当の対価を支払う必要があること、が定められていたために発生した紛争となります。
もっとも、著作権法の場合、一従業員が著作物を創作した場合であっても、一従業員が著作者になるとは定めておらず、逆に原則会社が著作者になるとされています。この点、著作権法第15条第1項では、「法人その他使用者(以下この条において「法人等」という。)の発意に基づきその法人等の業務に従事する者が職務上作成する著作物(プログラムの著作物を除く。)で、その法人等が自己の著作の名義の下に公表するものの著作者は、その作成の時における契約、勤務規則その他に別段の定めがない限り、その法人等とする。」と定めています。
・プログラムの著作物(著作権法第15条第2項)
上記の法人著作と基本的な考え方は同じ、すなわち一従業員が創作したプログラムに係る著作者は原則会社となるのですが、「公表」が不要とされています。
・委託者と受託者がいる場合
委託者は単なるアイデアやコンセプト等を提示しただけに過ぎず、当該提示を受けて受託者が創作を行った場合、受託者が著作者となります。
なお、業務委託契約や請負契約等に基づき、受託者及び請負人等が創作行為を行った場合、法人著作(職務著作)が適用されません。
(3)著作権者とは
著作者は、著作権と著作者人格権を享有することになります(著作権法第17条第1項)。したがって、創作段階では著作者=著作権者となります。
もっとも、著作権は譲渡が可能であり、また相続の対象となるため、著作者と著作権者が異なる場合が生じ得ます。
一方、著作者人格権は譲渡不可であり、相続の対象とならないため、著作者と著作者人格権保有者とが別々になることはありません(著作権法第59条)。
(4)著作権及び著作者人格権の内容
一口に著作権といっても、様々な権利が含まれており、代表的な物として複製権(著作権法第21条)、上演権及び演奏権(同22条)、上映権(同22条の2)、公衆送信権等(同23条)、口述権(同24条)、展示権(同25条)、頒布権(同26条)、譲渡権(同26条の2)、貸与権(同26条の3)、翻訳・翻案権(同27条)などがあります。
現場実務としては、上記の権利の中からライセンスや譲渡の対象となる権利を選択し、適宜契約書に明記するという作業が求められることになります。なお、展示権は美術や写真の著作物に関して適用される権利、上映権及び頒布権は映画の著作物に関して適用される権利です。美術・写真・映画を対象とするライセンスや譲渡契約を締結する場合、見落とさないよう注意を払う必要があります。
これに対し、著作者人格権は、公表権(著作権法第18条)、氏名表示権(同第19条)、同一性保持権(同第20条)の3種類となります。
ときどき、著作者人格権まで譲渡対象とする旨の契約書を現場実務で見かけたりしますが、著作権法第59条により譲渡することは不可能です。ライセンスや譲渡契約を締結する場合、著作者人格権は著作者に帰属することを前提に必要な手当てを行うことになります。
(5)マルCマークの意義
いわゆる「マルCマーク」を付けないと、著作権法上の保護が受けられないのではないかという問い合わせを受けます。
しかし、少なくとも日本国内では、「マルCマーク」が無くても著作権の保護対象となります。なお、著作権法第17条第2項では、「著作者人格権及び著作権の享有には、いかなる方式の履行をも要しない。」と定められています。
2.著作物利用(ライセンス)契約
(1)事前に検討するべき事項
著作物の利用(ライセンス)契約については、著作権法第63条で次のように定められています。
|
1 著作権者は、他人に対し、その著作物の利用を許諾することができる。 |
この条項を踏まえ、利用(ライセンス)契約を締結するに際しては、次の点を意識する必要があります。
・対象となるものが「著作物」といえるのか(著作物ではない場合、ライセンス自体不要な場面が想定されるため)
・著作権者は誰なのか(著作者と著作権者が異なる場合があるため)
・保護期間はいつまでか(著作権の保護期間が終了している場合、ライセンス自体が不要であると考えられるため)
また、上記以外に著作権法が認める、権利制限規定(著作権者が著作権侵害を主張できない場面を定めたもの)に該当しないかについても確認する必要があります。代表的なものは次の3つです。
・引用(著作権法第32条)
現場実務で度々問題となるのが「引用」該当性です。
著作権法第32条第1項では、「公表された著作物は、引用して利用することができる。この場合において、その引用は、公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行なわれるものでなければならない。」と定められているところ、これまでの裁判例等を踏まえ
①他人の著作物を引用する必然性があること
②自己の著作物と引用部分とが区別されていること
③主従関係が明確であること
④出所の明示が行われていること
の4要件を充足する必要があると考えられます。
・プログラム複製物の所有者による複製等(著作権法第47条の3)
一昔前であれば、プログラム制作を委託した場合、媒体物にプログラムのコピーを記録して納品することが行われていたことから、この条項を用いることができたのですが、近時は媒体物を納品するということ自体が行われなくなっています。このため、著作権法第49条を意識して、ユーザ自らが使用する限りにおいて複製等ができる旨契約書に明記することで対処することが多いようです。
なお、著作権法第47条の3条第1項では、「プログラムの著作物の複製物の所有者は、自ら当該著作物を電子計算機において実行するために必要と認められる限度において、当該著作物を複製することができる。ただし、当該実行に係る複製物の使用につき、第113条第5項の規定が適用される場合は、この限りでない。」と規定されています。
・著作物に表現された思想又は感情の享受を目的としない利用(著作権法第30条の4)
いわいるAIによる学習を可能にするための規定であり、「情報解析」(著作権法第30条の4第2号)の場面であれば著作権侵害にならないとされています。
十分に認知されているとは言えない状況のようですが、今後は積極的に活用されるものと思われます。
なお、あえて明記していませんが、私的使用のための複製(著作権法第30条)は、事業者には適用が無いと考えられていることに注意が必要です。
(2) 著作物利用(ライセンス)契約書を作成する上でのポイント
・当事者
|
第×条 |
上記1.で簡単に触れましたが、著作者と著作権者は異なる場合があります。このため、正当な著作権者を「甲」として表示する必要があります。
何らかの事情で著作権者を「甲」として記載することができない場合、甲に記載されている者が著作権者より正当な権利を保持しているのか(乙に対する利用許諾権を有するのか)調査することはもちろん、甲に表明保証させる別条項を設けることも検討するべきです(なお、著作権が共有状態の場合、共有者全員の同意を得る必要があることにも注意。著作権法第61条第2項)。
一方、利用者ですが、例えば、親子会社やグループ会社での著作物の利用を予定している場合、乙として全当事者を記載するのが原則です。何らかの事情で全当事者を記載することができない場合、別条項で「乙は特定の第三者に対して、再利用許諾することができる。」ことを定めておく必要があります。
・対象の特定
|
第×条 |
利用許諾の対象物が不明確な場合、一方は許諾対象である、他方は許諾対象ではないといったトラブルの原因となりますので、「□□」の部分は具体的に明記し、対象物の特定を行う必要があります。
一般的には、著作物の名称、種類、内容、著作者名等で特定を図ることになりますが、複数の著作物が予定されている場合は別紙で特定する、媒体物内に保存した著作物をもって特定するといった創意工夫が行われています。
なお、媒体物をもって許諾対象となる著作物を引き渡す場合、データの形式や加工作業の有無、加工作業が必要な場合はどちらの負担で行うのか等についても取り決める必要があります。
・ライセンスの種類、範囲
|
第×条 |
利用(ライセンス)契約を締結するに際して、一番のポイントとなる条項です。
「いつ」「どこで」「誰が」「誰に対し」「何を」「どうやって」といった5W1H等を意識しつつ、著作物の利用方法を想定しながら、具体的に明記するのが重要となります。
「期間」は字義どおりですが、例えば、著作物を用いた制作物(パンフレットなど)が第三者に提供される場合、既に流通してしまい回収不能な制作物については、期間経過後であっても著作権侵害を問わないといった取り決めを行う必要があります。
「地域」も字義どおりですが、例えば、インターネット上で公開する場合、全世界に著作物が公開されることになりますので、地域の限定ができるのかという観点からの検討が必要となります。
「態様」とは、著作物を紙に印刷し販売する(複製権や譲渡権の許諾)、WEBページに掲載し公開する(複製権や公衆送信権等の許諾)、プログラムを組み込んでシステム運用を行う(複製権や翻案権の許諾)といった取り決めのことをいいます。なお、著作物を利用するに当たり、サイズや色調の変更、一部分の切り抜きといった改変が想定される場合、改変の可否や程度についても定めておく必要があります(読みづらくなる場合、別条項で定めることも問題ありません)。
「媒体等」は、上記例の場合、出版社・出版日・題号等で特定された書籍、URLで特定されたWEBページ、使用目的や使用場所等で特定されたシステムといったものを指します。
「独占の有無」は、独占的な利用許諾権を付与するのか(利用者にとっては有利だが、利用料が高額になる可能性有)、非独占的な利用許諾に留めるのかを明記します。
なお、再利用許諾(サブライセンス)を一定の条件で認める場合、ここで明記しておいた方が分かりやすいと思われます(もちろん、別条項として定めておくことでも問題ありません)。
・対価
|
第×条 |
いわゆるライセンス料については、一時金として支払う方式、分割方式、月の使用量等に応じて支払う方式、月額定額料金を支払う方式(サブスクリプション)など様々なものが考えられるところです。
なお、使用量等に応じて支払う方式の場合、基本的には乙からの報告内容をもって甲は使用量等を把握することになります。もっとも、乙からの報告内容が適切なのか疑義が生じる場面も想定されることから、甲による監査権を定めておき、甲自らが使用量等をチェックできる体制を構築することも検討する必要があります。
・権利侵害時の責任
|
第×条 |
著作権は甲に帰属する以上、紛争処理は甲が対応するという規定にしましたが、決まり事はありません。上記の条項例とは逆に、乙に対応させることでも問題ありませんが、この場合、乙の不十分な対応によって甲の著作権にキズが付く可能性があることから、甲への報告と甲の指示に従うといった甲の関与条項を設けることが通常です。
なお、上記の条項例をベースとしつつ、「但し、乙の責めに帰す事由による場合はこの限りではない」と定めて、双方のリスク分担を行うということも検討に値します。
・契約終了後の措置
|
第×条 |
措置内容として「消去又は廃棄」と記述しましたが、状況によっては「返還」させるといったことを定める場合もあります。
なお、上記の「ライセンスの種類、範囲」の「期間」の箇所で触れましたが、契約終了後も一定の条件にて著作物の利用が可能である場合、必ずその点を定めておく必要があることに注意を要します。
3.著作権譲渡契約
(1)事前に検討するべき事項
著作権の譲渡契約については、著作権法第61条で次のように定められています。
|
第×条 |
注意を要するのは著作権法第61条第2項の存在です。著作権法第27条では翻訳権・翻案権等が、著作権法第28条では二次的著作物の利用に関する原著作者の権利が定められていますが、譲渡されることが明記(特掲)されていない限り、原則として譲渡したことにはならないと定められています。
なお、著作権には様々な権利があること上記1.(4)で記述した通りですが、色々と書くのが面倒なので「全ての著作権を譲渡する」と書きたくなるかもしれません。しかし、このような書き方の場合、特掲されたとは言い難いので、翻訳権・翻案権及び二次的著作物の利用に関する原著作者の権利が譲渡対象外となるリスクが生じることに注意を要します。
なお、著作物を出版する場合、著作物の譲渡を受ける方法と出版権の設定を受ける方法があります(もちろん、著作物の利用許諾を受ける方法もあります)。
著作物の譲渡と出版権の設定は似て非なるものですので、この点は勘違いしないようにしたいところです。
(2)著作権譲渡契約書を作成する上でのポイント
・当事者
|
第×条 |
上記(1)で解説した通り、譲渡対象となる著作権の範囲につき、全ての著作権を対象とするのであれば、著作権法第27条及び同第28条を特に明記しておく必要があります。上記条項例はその点を意識したものとなります。
他に注意するべき事項は、上記2.(2)「当事者」で解説した事項と同様となります(著作者と著作権者が異なる場合があること、著作権が共有状態である場合は全共有者の同意が必要となること等)。
・対象の特定
|
第×条 |
利用許諾の対象物が不明確な場合はトラブルの原因となること、トラブル回避のためには「□□」の部分を具体的に明記し、対象物の特定を行う必要があること、上記2.(2)「対象の特定」で解説した事項と同様となります。
ところで、著作物がプログラムの場合、著作権の譲渡が行われるのであればソースコードも譲渡されることになるのではないか、という疑問が生じます。
この点、譲渡対象物としてソースコードを明記しているのであれば、譲受人はソースコードを取得することになりますので、譲受人は譲渡人に対してソースコードの開示を請求することが可能です。
もっとも、明記されていない場合、オブジェクトコードが譲渡対象となることは明白なのですが、ソースコードが含まれるのかは不明確です(理論的にはソースコードは譲渡対象物に含まれないという解釈も十分成立し得ます)。譲受人としては、プログラムの機能追加や保守等を自ら行いたいと考える場合、ソースコードが譲渡対象物となるよう明確にすることが重要となります。
・著作者人格権の不行使
|
第×条 |
前述1.(3)で解説した通り、著作者人格権は譲渡の対象となりません(著作権法第59条)。そして、この著作者人格権の不行使特約を定めておかない場合、乙が譲り受けた著作物を改変しようとしても、著作者より著作者人格権の侵害を主張されることで、結果的に改変不可という事態に陥ることがあり得ます。
譲受人の立場からは、このような事態を回避するためには、必ず定めておかなければならない条項となります。
・対価
|
第×条 |
これについては、単なる支払方法の問題にすぎず、著作権譲渡契約として特有の問題はありません。
・権利侵害時の責任
|
第×条 |
上記条項と次に記載する条項との相違ですが、上記条項は第三者が著作権を侵害してきた場面、すなわち乙が著作権侵害であるとして第三者を攻撃する場面であるのに対し、次に記載する条項は第三者が著作権侵害であると主張してきた場合、すなわち乙が非侵害であるとして防戦する場面という違いがあります。
さて、ここでは、著作権は乙に帰属する以上、紛争処理は乙が対応するという規定にしましたが、決まり事はありません。上記の条項例とは逆にすることも可能ですが、その場合、乙への報告と乙の指示に従うといった乙の関与条項を設けておいたほうが良いこと、上記2.(2)「権利侵害時の責任」で解説した通りです。
・表明保証等
|
第×条 |
第三者より権利侵害の指摘を受けた場合の対応について、甲・乙のどちらが対応するかについて決まり事はありません。したがって、どちらでもよいのですが、上記条項例では甲に対応させるという内容にしています。
仮に乙が第三者との紛争対応を行う場合、当該対応に要した費用負担について甲が負担するといった第3項の内容を充実化させることがポイントになると考えられます。例えば、第三者に対して支払った金額のみならず、紛争解決のために必要となった弁護士費用等の実費分についても甲が負担する旨定めるといったことが考えられるところです。
4.著作物制作契約
(1)事前に検討するべき事項
一般的には「著作物制作契約」というタイトルは付けず、例えば、WEB制作契約、コンテンツ作成契約、システム開発契約といった、制作等する著作物の具体的内容を用いてタイトルを付することが多いと思われます。
さて、著作物の制作契約を締結する場合、著作物は誰に権利帰属するのかという点を意識して定めることが最重要となります。
もっとも最近では、何が何でも権利を取得したいというスタンスではなく、権利帰属自体は相手方で構わないが、実質的には自由に利用可能なライセンスを獲得するという契約交渉が多くなってきているようです。この場合、上記2.で解説した著作物利用(ライセンス)契約の内容も加味して検討を進める必要があります。
(2) 著作物制作契約書を作成する上でのポイント
・委託業務の内容
|
第×条 |
当たり前のことですが、どのような著作物を制作してもらうのか具体的かつ明確に定める必要があります。時々「××一式」といった記載を見かけますが、この一式には何が含まれるのか当事者双方で認識が異なることが度々起こり得ますので、「××一式」という記載は避けるべきです。
なお、上記のような映像コンテンツ制作の場合、動画の再生時間、使用可能な媒体、映像内に用いられる音楽や画像等の権利処理などについても定めておく必要があります。
・権利の帰属
|
第×条 |
著作権法上の原則からすれば、映像コンテンツに関する著作権は受託者である乙に帰属することになります。したがって、委託者である甲に著作権を帰属させたいのであれば、乙から甲に譲渡される旨定めておく必要があります。なお、正確には著作権が譲渡されることで甲に権利帰属するというのが正しい考え方とはなりますが、この点を省略して単純に「…著作権は、甲に帰属する。」と定めても意味は通じるかと思います。
ところで、本件とは異なり、システム開発等を含むプログラム制作の場合、著作権の帰属については厄介な交渉となりがちです。
どちらか一方の単独帰属とならない場合、
①共有とする
②汎用的に利用可能なプログラムについては乙に帰属し、それ以外は甲に帰属する
といった解決法が模索されることが現場実務では多いかと思います。
ただ、執筆者個人としては、①共有による解決はお勧めしません。なぜなら、著作物を利用する場合、相手当事者にいちいちお伺いを立てる必要が出てくるからです(著作権法第65条第2項)。あえて指摘するとすれば、共有で対処することは紛争の火種を残したままであることに留意するべきです。
そうすると、②の方法を採用することになるのですが、問題は「汎用的に利用可能なプログラム」とは何を指すのかという点です。現場実務において、これを具体的に特定して契約書に定めることは難しい場合も多いと思いますが、機能名等で特定しながら一例をあげるといった対処が考えられるところです。
なお、委託者より、お金を支払っている以上はプログラム著作物の著作権は当然に委託者に帰属して然るべきという主張を見かけることがありますが、お金の支払いと著作権の帰属は連動しません。この点は勘違いしないようにしたいところです(下請法の適用がある場合、下請法違反のリスクさえ生じ得ます)。
・納品、検収方法
|
第×条 |
納品、検収方法の問題は、著作物制作契約に限らず、何らかの物(有体物・無体物を問わない)を製造・作成する場合に必ず意識しなければならない条項となります。
上記条項例は非常に簡略化してありますが、委託者である甲の立場であれば、不合格となった場合は無償で修正することを乙に義務付ける条項を、受託者である乙の立場であれば、一定の検査期間内に合否通知がない場合は合格とみなす条項を、追加するといったことが考えられます。
5.ひな形・参考書式を使用する場合の注意点
おそらく契約書作成業務は非日常業務であり、一から調べて作成することが面倒であること等を理由として、本記事を含め、インターネット検索で表示されるひな形・参考書式をそのまま使用するということが行われていると予想されます。
しかし、特に著作権に関する契約書については、ひな形・参考書式をそのまま用いることは危険です。
①最適な契約書であることが保証されないこと
ライセンス、譲渡、制作など様々な著作権に関する契約書がありますが、その対象となる著作物も色々なものがあります。例えば、記事、音楽、美術、画像・映像、プログラムなどがあげられますが、実は著作権法は、著作物の種類に応じて、著作権者が保有する具体的な権利内容や権利制限内容を区別しています。
つまり、ひな形・参考書式が記事等の言語の著作物を念頭に置いて作成されている場合、そのひな形・参考書式をプログラムの著作物用としてそのまま用いた場合、明らかな誤りや矛盾のある契約書、最悪の場合法律上無効な契約書にもなりかねないのです。
ひな形・参考書式を用いる場合、著作物に応じた修正が必要となることを意識するべきです。
②正確性、妥当性、有用性、適法性が保証されないこと
著作権法は頻繁に法改正が行われる法律です。また、著作権法に対する裁判所の法解釈がある日を境に変更されることも珍しくありません。さらに、時代の進展に伴う社会的要請に応じた運用が行われるのも著作権法の特徴です。
このため、公開されているひな形・参考書式は、法改正や最新の法解釈が反映されていない、社会的要請に応じた内容になっていない等の問題がどうしても発生します。
ひな形・参考書式を用いる場合、旧来のままになっている事項を見つけ出し、現代版に置き換える作業が必要となることを意識するべきです。
③取引実情に合致する保証が無いこと
例えば、プログラム開発業務を受託し、一部業務を再委託する場合において、注文者とは注文者指定の契約書にて締結し、再委託先とはインターネット上で公開されていたひな形・参考書式を用いたとします。この点、注文者との契約書ではプログラムの著作物について注文者に譲渡する旨定められているのに対し、再委託先とのひな形・参考書式では再委託先に著作権が帰属し、受託者はライセンスを受けると定めていた場合、受託者は注文者との間で契約違反を犯してしまうことになります。
上記例のように、ひな形・参考書式自体に間違ったことは書いていなかったとしても、実際の取引実情を考慮した場合、ひな形・参考書式を用いること自体が誤りであったことが実際にあり得ます。
ひな形・参考書式を用いる場合、書いてある内容のチェックだけではなく、取引全体の流れから考えて、そもそもこのひな形・参考書式を用いても大丈夫なのかという点を意識するべきです。
6.当事務所でサポートできること
著作物に関係する契約として、著作物の利用(ライセンス)契約、著作権譲渡契約、著作物制作契約の3つを解説しました。
上記では、特に注意を要する事項のみ取り上げて解説を行いましたが、例えば…
・著作物の種類・性質によって検討するべき事項と契約書に定めておくべき事項が異なってくること
・頻繁な法改正、裁判所の判断動向に細心の注意を払いながら、契約書の内容を都度調整する必要があること
・契約書の内容自体は間違っていない場合であっても、取引全体における位置づけを踏まえ、相手当事者と交渉して修正するべき事項が生じること
など考慮するべき事項が多数あり、なかなか一筋縄ではいかないのが実情です。
また、上記5.でも記載した通り、安易にひな形・参考書式に頼ってしまうと、実情に合致しないどころか、かえって自分の首を絞めることにもなりかねません。
著作権に関する契約書作成・リーガルチェックは、独特の法解釈の理解、社会情勢の動向など専門的知見を必要とし、弁護士の関与が必須といっても過言ではありません。
この点、当事務所は、日常的に著作権に関する契約書の作成・リーガルチェックはもちろん、締結済みの著作権に関する契約書の合理的解釈論を踏まえた対処法、著作権に絡む紛争対応などを取扱い、これらを通じて取得したノウハウ等を日々集積しています。
当事務所へご依頼いただいた場合、当事務所が保有するノウハウ等を駆使し、最善の結果が得られるよう尽力しますので、是非ご利用ください。
<2023年2月執筆、2023年9月更新>
※上記記載事項は弁護士湯原伸一の個人的見解をまとめたものです。今後の社会事情の変動や裁判所の判断などにより適宜見解を変更する場合がありますのでご注意下さい。