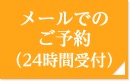普通解雇の手続き・要件とは?その他の解雇との違い
【ご相談内容】
当社従業員の中に、全くやる気がなく、どの部署に配属してもお荷物扱いとなってしまう者がいます。
当社としても色々と手を尽くしているのですが、従業員本人が非常に反抗的であり、他人のアドバイス等を受入れようとせず、対処に困っています。
いっそのこと解雇処分にしようと考えているのですが、問題はあるでしょうか。
【回答】
従業員が会社の期待通りに働いてくれないことを理由として普通解雇すること、これ自体は理屈の上では考えられるところです。
しかし、解雇手続きは厳格であり、また解雇の有効性についても、会社が想定している以上に認められにくいというのが実際の裁判実務となります。
なお、会社によっては、普通解雇と懲戒解雇を意識せずに解雇手続きを進めてしまったため、かえって自分の首を絞めるといったミスを犯すこともあるようです。
そこで、本記事では、普通解雇と他の解雇との相違点を簡単に触れつつ、普通解雇を行う場合の手続き上の注意点、及び普通解雇の有効性を検討する上での視点について解説を行います。
【解説】
1.普通解雇と他の解雇との相違
(1)普通解雇とは
普通解雇とは、労働・雇用契約が不履行であることを理由として、使用者(雇い主)が労働・雇用契約を解除することをいいます。俗にいう、会社が労働者を一方的にクビにすることです。
労働・雇用契約の不履行とは、心身の傷病や能力不足・成績不良による労務の提供が不能又は不十分である場合のほか、労働者の勤怠不良、業務命令(配転・出向等を含む)違反、職場での非違行為といった契約上の義務違反が典型例となります。
なお、職場外での非違行為といった労務提供の不十分さ及び契約上の義務違反と直ちに結びつくわけではないものの、結果的に使用者(雇い主)の信用を傷つける、あるいは職場内の人間関係を損なうといった場合も、労働・雇用契約の不履行として取り扱われることがあります。
(2)懲戒解雇との相違
懲戒解雇とは、職場の秩序違反に対する制裁処分の1つであり、社内秩序を回復するために労働・雇用契約を解除すること(会社が労働者を一方的にクビにすること)をいいます。例えば、職場内でハラスメントを行った場合、会社所有物の窃取や金員の横領など犯罪に該当する行為を行った場合、経歴詐称などが、懲戒解雇事由の典型例となります。
さて、使用者(雇い主)が労働・雇用契約を解除するという点では、普通解雇と懲戒解雇とに相違はありません。
しかし、普通解雇は、労働者による労務の提供が不能若しくは不十分、又は契約上の義務違反であることを根拠にした労働・雇用契約の解除であるのに対し、懲戒解雇は、労働者による労務の提供の有無・程度を問わず、このまま在籍させることは組織規律を維持する上で問題が大きいことを根拠に労働・雇用契約の解除を行うという、目的の違いがあります。その他にも、普通解雇と懲戒解雇とでは、次のような相違点があります。
【解雇事由】
普通解雇の場合、就業規則に定められていない事由であっても解雇することが可能な場合があります。
一方、懲戒解雇の場合、就業規則に定められた事由以外で解雇することはできません(この意味で、就業規則を制定していない使用者(雇い主)は懲戒解雇を実行することができないことになります)。
【弁明機会の付与】
普通解雇の場合、就業規則に労働者からの弁明の機会を付与する旨定めていないのであれば、弁明の機会を設けなくても解雇を実施することが可能です。
一方、懲戒解雇の場合、たとえ就業規則に労働者からの弁明の機会を付与する旨定めていなかったとしても、当該付与を行わないことには、手続き違反として解雇が無効となる場合があります。
【解雇予告手当の支払い】
普通解雇の場合、即時解雇を行うのであれば30日分以上の解雇予告手当の支払いが必要となります(解雇予告手当の支払いを免れたいのであれば、30日以上前の解雇予告を行う必要があります)。
一方、懲戒解雇の場合も普通解雇と同様なのですが、例外的に労働基準監督署より除外認定を受けた場合、解雇予告手当の支払いが不要となります(なお、執筆者個人の見解となりますが、除外認定を受けることは相当ハードルが高いと考えます)。
【退職金】
普通解雇の場合、退職金は満額支給されることが通常です。
一方、懲戒解雇の場合、退職金が減額又はゼロになる場合もあります(なお、退職金の減免については、就業規則の定め方によるため、懲戒解雇であっても退職金の減免が定められていない場合は、満額支給されることになります)。
【失業手当】
普通解雇の場合、いわゆる会社都合退職扱いとして処理することになります。
一方、懲戒解雇の場合、通常は重責解雇(雇用保険法上の概念です)に該当し自己都合扱いとして処理することになります(あくまでも労働者視点ですが、自己都合扱いと比較して、会社都合扱いであれば失業手当の支給開始が早く・長期間になります)。
(3)諭旨解雇との相違
諭旨解雇は懲戒処分の1つであるという点で普通解雇とは異なります。
ただ、一般的には懲戒解雇より軽めの懲戒処分として定められており、実のところ懲戒解雇との相違は明確ではない場合があります。
例えば、「労働者の不祥事・非行があった場合は、その行為を諭した上で、従業員の意思により辞表を提出させる」とあたかも退職勧奨を行うことのみ就業規則に定めている場合もあれば、「労働者による不祥事・非行に対し、当該労働者が深く反省している場合、辞表の提出を勧告する。×日以内に提出しない場合は懲戒解雇とする」と辞表を提出しなかった場合は懲戒解雇に処することまで就業規則に定めている場合もあったりします。
諭旨解雇を定める1つの目的として、懲戒処分を行う必要性はあるが、懲戒解雇による不利益(例えば、退職金の減額など)までは心苦しいといった場合への対処と思われますが、就業規則の定め方如何によっては何らの制裁にならない場合もあります。
労働・雇用契約の解除に重点を置くのであれば、諭旨解雇ではなく普通解雇を選択する場面も想定されるところです。
(4)整理解雇との相違
普通解雇は、一般的には労働者による労働・雇用契約の不履行を想定しています。
しかし、整理解雇は、使用者(雇い主)が労働・雇用契約に基づき将来的に賃金を支払うことができないことを理由としたものとなります。すなわち、労働者による労働・雇用契約の不履行を問題視するのではなく、使用者(雇い主)の経営上の都合による労働・雇用契約の解除となることから、懲戒解雇ではないという点では普通解雇に分類されるものの、一般的な普通解雇とは大きく異なるものとなります。
特に整理解雇の場合、(1)人員整理の必要性、(2)解雇回避努力、(3)人選の合理性、(4)手続きの妥当性という4要素を考慮して、その有効性を判断するという方法が裁判例として確立しています。
就業規則上は、普通解雇事由の1つとして整理解雇に関する規定が置かれていることが通常ですが、現場実務では、普通解雇と整理解雇は全く異質のものとして検討したほうが良いと考えられます。
2.普通解雇を実施するための手続き
普通解雇を実施する場合、内容面として、
・労働者のどの行為が労務提供の不当又は不十分と認識しているのか(問題行動の把握)
・問題行動について客観的な裏付けは取れているのか(証拠の確保)
・就業規則上どの条項に違反するのか(就業規則上の根拠。なお、就業規則が制定されていない場合は労働・雇用契約から導かれる労働者の義務違反の検討)
をまずは確認する必要があります(なお、詳細は後述3.参照)。
この内容面の検証が非常に難しく、使用者(雇い主)の常識と裁判所の考え方が大きくズレてしまうため、使用者(雇い主)がなかなか解雇の裁判で勝訴することができないという実情があります。使用者(雇い主)が問題視している労働者の行為は、裁判で耐えうる解雇事由と言えるのかについては、是非弁護士と相談してほしいところです。
さて、ここでは内容面以外に、普通解雇を実施するにあたって手続き面で確認しておきたい事項を解説します。
(1)解雇予告と解雇予告手当
上記1.(2)でも少し触れましたが、普通解雇を実施する場合、
・30日以上の予告期間を設けて解雇する(要は30日以上の経過を待って労働・雇用契約の解除を行う)
・予告期間を設けない場合は、30日分以上の解雇予告手当を支払う
のいずれかを選択する必要があります。
一般的には、普通解雇を実施せざるを得ない従業員を引き続き在籍させ、業務従事させるわけにはいきませんので、解雇予告手当を支払うことを選択します。
この“解雇予告手当”の計算方法ですが、「平均賃金」の「30日分以上」と労働基準法第20条では定められています。この平均賃金ですが、
・解雇通告の直前の賃金締切日から起算して3ヶ月分の実際の支給総額を算出する(通勤手当や残業代等が含まれることに注意。なお、賞与など3カ月を超える期間ごとで支払うものは含まれない)
・3ヶ月分の総歴日数を算出する(28日、29日、30日、31日の実際の月の日数で算出する)
・上記支払総額に対して上記総歴日数を除する(銭位未満の端数は切捨て)
にて算出することになります。
ところで、現場実務で勘違いしやすいものとして、解雇予告手当の支払いタイミングがあげられます。
すなわち、通常の賃金と同じく、次の賃金支払い日に支払えばよいと考えている会社も多いのですが、行政通達では解雇の効力発生日に支払うことが求められています。即時解雇を行うにあたり、解雇予告手当を銀行振り込みにて支払う場合、銀行の送金業務対応時間を考慮する必要があります。
(2)通知方法
解雇通知は労働者の面前で行うことが通常なのですが、労働者が出勤しない又は会社担当者との面談を回避するなどして、面前通知ができない場合があります。
この場合、使用者(雇い主)は何らかの方法を用いて、労働者に対し解雇通知を行う必要があります。
この点、最も確実な方法は配達証明付き内容証明郵便となります(一般的に内容証明と呼んでいるものは、配達証明を付けた内容証明郵便のことを指します)。ただ、配達証明を付しているため、労働者が受領しない場合、一定期間経過後に郵便物が使用者(雇い主)の元に返却されるため通知を行うことができません。
この場合、労働者が確実にその場所(自宅など)にいることが判明しているのであれば、特定記録郵便又はレターパックライトを用いて通知することが考えられます。あくまでも特定記録郵便等はポストに投函されたことまでしか裏付けることができませんが、労働者本人において了知可能な状態になったといえますので、解雇通知の効力を認めてよいと考えられます。
他にも電子メールやLINE等の電子媒体を用いた通知方法が考えられます。
ただ、電子メールについては捨てアド等に代表される、実際には用いていない電子メールが存在しますので、上記郵便と比較して、果たして労働者において了知可能だったと言い切れるのかは微妙なところがあり、通知済みとは言いにくいところがあります(なお、開封確認機能を付した電子メールを送信し、開封確認が取れた場合は了知可能だったと考えることができるかもしれません)。
また、LINEについては、既読処理が行われた場合はともかく、未読の場合、労働者にとって了知可能とはやはり言い難いところがあり、通知済とすることは難しいと考えられます。
ちなみに、実例は少ないのですが、執筆者が取扱ったものとして電報を用いて通知したこともあります(配達証明付き内容証明郵便の場合、労働者が何かを察知して受領しない可能性があること、特定記録郵便では通知到達にやや不安がある場合に、物は試し…という程度で用いたにすぎません。通知完了自体には争いが生じなかったため、一応の目的は達することができました)。
なお、遺留分に関する通知の裁判例となりますが、配達証明付き内容証明郵便で送付し、受取人不在で郵便局保管となったところ、保管期間満了をもって通知済みの効力が生じると判断したものがあります(最高裁判所平成10年6月11日判決)。あくまでも事例判決ですが、事案によってはこの最高裁判決を根拠に、保管期間満了をもって解雇通知は行われたと解釈し対処することも検討に値します。
(3)解雇理由証明書、退職時証明書
解雇理由証明書は、解雇予告の日から退職日までの間において、労働者が解雇の理由を記載した書類発行を要求した場合、使用者(雇い主)が労働者に交付すべき書類となります(労働基準法第22条第2項)。なお、この制度は予告解雇手続きを実施した場合を前提にしていますので、即時解雇の場合は事実上適用の余地がないことになります。
一方、退職時証明書は、退職した労働者が、「使用期間、業務の種類、その事業における地位、賃金又は退職の事由(退職の事由が解雇の場合にあっては、その理由を含む。)」を記載した書類を要求した場合、使用者(雇い主)が労働者に交付すべき書類となります(労働基準法第22条第1項)。
離職票とは別に、これらの書類まで発行要求される場面は非常に少なく、使用者(雇い主)としては困惑するかもしれませんが、発行は法的義務である以上、従わざるを得ません。
なお、このような書類発行を要求された時点で、既に紛争の火種ありと言わざるを得ませんので、可能な限り、書類作成前に弁護士に相談し、今後のシミュレーションと対応方針を確認したほうが無難です。
3.普通解雇が有効となるための要件
使用者(雇い主)が解雇やむなしと考えている事案であっても、弁護士は不当解雇と判断されるリスクが高いとアドバイスし、実際の裁判でも解雇無効と判断され使用者(雇い主)が敗訴してしまう…というパターンが後を絶ちません。
これは解雇の有効性を判断する上で、どのような事項を考慮する必要があるのかにつき、使用者(雇い主)と裁判官の視点が異なっているためと考えられます。
そこで、裁判官作成の論文を参照しつつ、検討するべきポイントを以下解説します。
(1)客観的に合理的な理由
労働契約法第16条では、「解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする。」と定めています。
したがって、まずは「客観的に合理的な理由」とは何かを検討する必要があるところ、次の3点が検討要素になると指摘されています。
①解雇事由を特定すること
②契約不履行が将来的に継続されると予測されること
③解雇が最終手段となっていること
まず、1つ目の「解雇事由の特定」ですが、心身の傷病や能力不足・成績不良による労務の提供が不能又は不十分であるとった事実、あるいは労働者の勤怠不良、業務命令(配転・出向等を含む)違反、職場での非違行為といった契約上の義務違反に該当する事実のことをいいます。
この事実を指摘できなければ、そもそも解雇のしようがありません。
ただ、現場実務で悩ましいのは、この事実を裏付ける証拠を見つけ出すことです。残念ながら一義的かつ確実な物証は存在せず、関係者(同僚・上司等)の証言等を集めることになりがちですが、裁判官はどうしても関係者の証言に重きを置かない傾向があるため、裏付け証拠の確保に一苦労することになります。
なお、就業規則が存在する場合、該当事実が就業規則に定める普通解雇事由のどこに当てはまるのかについても検討する必要があります。
次に、2つ目の「契約不履行が将来的に継続されると予測されること」ですが、使用者(雇い主)において十分に検討できていない事項となります。
現場実務を見ていると、使用者(雇い主)は、ある特定の時点をもって「この労働者は不適格である」と判断し、それで足りると考えていることが多いのですが、裁判官は、その特定の時点のみならず、今後も不適格状態が継続するのかという視点を持ちながら、解雇の有効性を判断します。例えば、心身の傷病であれば将来回復する見込みは無いと専門家は言っているのか、能力不足・成績不良であれば今後の指導による改善の見込みは全くないのか、といった点を重視して判断しています。
よく巷では、「改善指導を一切行うことなく解雇しても無効である」と言われたりしますが、これは、①過去において使用者(雇い主)ができる限りのことをしたという意味に留まらず、②これ以上改善指導を尽くしても無駄である…といった労働契約の不履行状態が将来も継続することを裁判官に予測させるという意味もあることを押さえておく必要があります。
裁判官等の第三者の目から見て、引き続き労務提供の不能若しくは不十分、又は契約上の義務違反が今後も継続するであろうと予測できるようにすること、使用者(雇い主)が普通解雇を実施する場合、是非この視点を取り入れてほしいところです。
最後に、3つ目の「解雇が最終手段となっていること」ですが、使用者(雇い主)として解雇回避措置を尽くしたといえるかを意味します。
ただ、これは評価を伴うものであり、やや裁判官の考え方(人生観)に左右されがちなところがあって、非常に判断しづらい事項となります。
一般論としては、例えば、職務・職種限定契約で採用した労働者が、その職務・職種に必要な能力水準を保持していない場合、一応の改善指導さえ行っておけば、配置転換等まで検討することなく普通解雇は可能と考えられます。一方、総合職で採用した労働者の場合、必要十分な改善指導を行ったことはもちろん、配置転換などの人事裁量権を行使し尽くさないことには普通解雇は難しいと考えられます。
なお、中小企業の場合、配置転換を行う余裕はなく解雇回避措置を講じたくても講じようがないという場合があります。この場合、使用者(雇い主)の実情を裁判官に指摘しつつ、例外的に緩やかな解雇回避措置で足りることを理解してもらう訴訟活動が必要となります。
(2)社会通念上の相当性
上記(1)で引用した労働契約法第16条の定めから、次に(解雇を行うことが)「社会通念上の相当性」があるかを検討する必要があります。
要は解雇以外の他の処分に留めるべきではないかという観点で判断することになるのですが、これには、労働者の情状(反省の有無、過去の勤務態度、処分歴、年齢、家族構成など)のみならず、労働者において不法な動機・目的がないか、他の労働者と処分の均衡はとれているか、使用者(雇用主)の対応に落ち度はなかったか、使用者において解雇目的を偽装していないか等々のあらゆる事情を考慮することになります。
結局のところは評価判断になるため、やはり裁判官の考え方(人生観)に左右されがちなところがありますが、使用者(雇い主)としては、自らに非が無いことを指摘しつつ、類似事案の裁判例を弁護士と相談しながら見つけ出し、裁判官が社会的相当性ありと自信をもって判断できるよう後押しするような訴訟活動が必要と考えたほうが良いかもしれません。
4.その他
普通解雇を実行するために注意するべき事項は、上記1.から3.記載の通りですが、ここでは少し細かい普通解雇に関するお役立ち知識について触れておきます。
(1)懲戒解雇事由による普通解雇の可否
タイトルだけを見ているとよく分からないかもしれません。
例えば、現場実務でよく起こり得ることとして、問題となっている労働者については辞めてもらうほかない、しかし、これまでの功労を考えると退職金を減額するのは忍びない、また懲戒解雇とすることで失業手当の支給開始が先延ばしになる、当該労働者の転職活動に支障を来す等の悪影響は避けたい等の理由で、懲戒解雇ではなくあえて普通解雇に留めたいと使用者(雇い主)が考える場面で、検討することになります。
結論から言うと、懲戒解雇事由があるから必ず懲戒解雇を実施しなければならないという訳ではなく、普通解雇にて処理することも問題ありません。
ただ、就業規則を定めている場合、どの普通解雇事由に当てはめるのか検討が必要になるかもしれません。なぜなら、普通解雇事由として「懲戒解雇に相当する事由がある場合」といった定めがあればともかく、ピッタリ当てはまる事由がない場合、いわゆるバスケット条項で処理するのか、バスケット条項がない場合は、労働・雇用契約に基づく労務提供不能(不十分)又は契約上の義務違反があったと理論づけて考える必要があるからです。
(2)懲戒解雇から普通解雇への転換の可否
使用者(雇い主)が労働契約を解除するという点では同様であることから、使用者(雇い主)によっては懲戒解雇と普通解雇を意識せずに解雇手続きを進めることもあるようです。
しかし、上記1.(2)で解説した通り、法的には懲戒解雇と普通解雇とでは色々と相違点があります。また、実際の裁判例などを見てみると、懲戒解雇は厳しすぎるので無効、しかし普通解雇であれば有効といった事例も存在します。
このような事情があることから、何らかの手違いで懲戒解雇を言い渡したものの、普通解雇として処理したいと使用者(雇い主)が考えた場合に、普通解雇に転換して処理ができるのかという問題が起こります。
これについては、原則として普通解雇への転換はできないと考えたほうが無難です(転換を認めた裁判例もありますが、特殊な事情があり、一般化することはできないと思われます)。
普通解雇にて処理したいのであれば、懲戒解雇を撤回し、改めて普通解雇を言い渡すことが必要となります(なお、懲戒解雇の言い渡しから普通解雇の言い渡しまでの賃金支払い義務が生じることに注意)。
ところで、上記例とは異なり、解雇言い渡しの時点で、懲戒解雇を言い渡しつつ、念のため(予備的に)普通解雇も同時に言い渡すという方法も行われたりします。懲戒解雇と普通解雇を同時に言い渡すこと自体は法的に認められていますが、懲戒解雇が無効となった場合、退職金を減免した場合の差額分につき支払義務が生じるといったことが後で発生することになりますので、その点は注意が必要です。
(3)解雇事由の追加
例えば、解雇を言い渡した時点では使用者(雇い主)は認識してなかったものの、その後何らかの事情で解雇に相当する事由が発覚した場合、解雇の有効性を担保するために事後的に発覚した事由を用いてよいのかという問題となります。
このような問題が生じるのは、たいていの場合、労働者が不当解雇を主張し紛争状態となった場面において、使用者(雇い主)が当該労働者のことをよくよく調査してみると、色々と問題行為が浮き彫りになってきたというパターンが多いように思います。
さて、解雇事由の追加ですが、結論から指摘すると、普通解雇の場合は可能、懲戒解雇の場合は不可となります。
理屈は色々あるのですが、現場実務においてはまずは結論を押さえておくことが重要です。
そして、どうしても労働者を辞めさせたいという場合、普通解雇を言い渡したほうが、後日紛争になっても追加で問題行為を指摘できるという点で有利に作用するということを理解する必要があります。もちろん、普通解雇に留まりますので、退職金の減免等ができないといった使用者(雇い主)の不利益が考えられますが、最終的には何を重視するのかにより選択することになります。
なお、懲戒解雇を主張しつつ、同時に普通解雇も主張することは可能であること、前述(2)で解説した通りです。
<2022年9月執筆>
※上記記載事項は弁護士湯原伸一の個人的見解をまとめたものです。今後の社会事情の変動や裁判所の判断などにより適宜見解を変更する場合がありますのでご注意下さい。