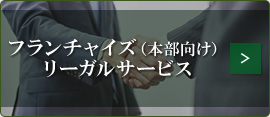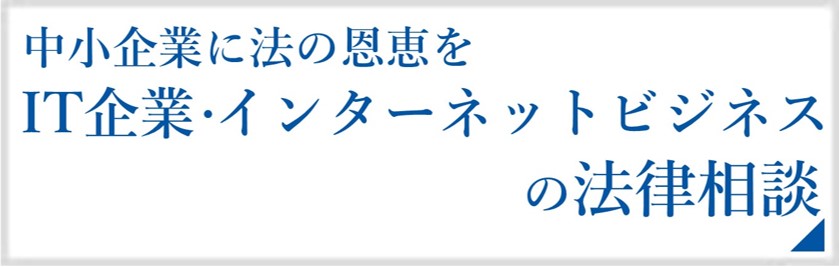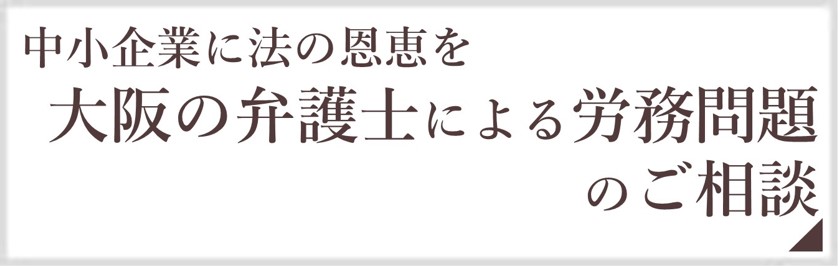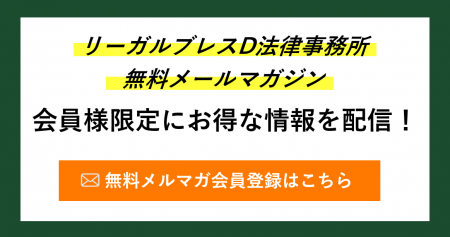【間違えやすい賃金実務②】 退職金支給の必要性
質問
元従業員より退職金の支払い要求を受けているのですが、次のような場合、支払義務はあるのでしょうか。
① 退職金制度が存在しないが、過去に退職金を支給した実績がある場合
② 会社からの貸付金や損害賠償金があるので、退職金との相殺を主張した場合
③ 元従業員を懲戒解雇した場合
④ 元従業員が同業他社へ転職した場合
回答
解説
1.① 退職金制度が存在しないが、過去に退職金を支給した実績がある場合
退職金制度は任意の制度である以上、退職金制度がないことそれ自体は法的には何ら問題がありません。
したがって、退職金制度が存在しないのであれば、退職金支給義務は発生しません。
なお、時々勘違いする人がいるのですが、就業規則の記載事項として、「退職手当」に関する事項があることを根拠に(労働基準法89条3号の2)、就業規則が存在するのに退職金に関する事項を定めていないことは違法だと主張する人がいますが、完全に誤りです。条文をよく読んで頂ければ分かるのですが、「退職手当の定めをする場合においては…」という表現になっています。つまり、退職金制度を設ける場合には就業規則に定める必要があるという構造になっていますので、退職金制度を設けないのであれば就業規則に定める必要が無いということになります。
さて、原則としては上記の通りなのですが、過去に退職金名目で何らかの支給を行っていた場合、「あの人には支給したのに、何故私には支給してくれないのか?」という不平不満が生じます。この不平不満は理解はできますが、単純に過去の支払い実績があったから、私も支給されて然るべきという結論には至りません。
ただし、この支給実績が「労使慣行」になっていること、すなわち、①長時間にわたって反復継続していること、②この状態について労使双方が異議を出していないこと、③使用者側において当該状態に従うという規範意識が存在すること、の要件を充足している場合には、たとえ退職金制度が就業規則その他明文化されていなくても、退職金支給義務が発生することとなります。
もっとも、退職金支給が労使慣行になったか否かについては、各社の状況によってまちまちの判断にならざるを得ず、裁判例も肯定例があったり否定例があったする状況です。
いずれにせよ、過去に支払い実績があった事実が直ちに他の方への退職金支給義務が肯定されるわけではありませんが、特にこの人には何らかの功労に報いたいという場合、名目を含めて支給方法を検討する必要があるかと思われます。
2.② 会社からの貸付金や損害賠償金があるので、退職金との相殺を主張した場合
退職金の法的性質については色々と見解があるようですが、最高裁判例(最判昭和48年1月19日)によれば、就業規則においてその支給条件が予め明確に規定されて使用者が支払義務を負うものである以上、労働基準法11条でいう「賃金」に該当すると判断しています。
したがって、労働基準法24条1項が適用される結果、使用者からの一方的な相殺は不可という結論となってしまいます(いわゆる賃金全額払いの原則)。
もっとも、使用者からの一方的な相殺が禁止されるだけですので、元従業員が任意で相殺を認めるのであれば、それは禁止されることはありません。
この結果、元従業員の自由意思で合意相殺したというのであれば、会社からの貸付金や損害賠償金と退職金とを相殺することは可能です。
3.③ 元従業員を懲戒解雇していた場合
上記「1」でも記載した通り、退職金制度を設けるか否かは会社の裁量とされています。したがって、退職金制度を設けるにしても、どの様な退職金制度とするのか、つまり要件・条件をどの様にするのかについても原則会社の裁量に委ねられています。
したがって、「懲戒解雇となった者に対して退職金を支給しない」という条件設定を行えば、この条件設定自体は有効となります。
もっとも、労働者保護の観点から、多くの裁判例では、上記のような条件設定に該当する場面を「限定解釈」という手法を用いて、その該当性を狭くしているのが実情です。つまり、懲戒解雇が相当であったとしても、当該解雇事由について、これまでの勤務期間における功労を抹消・減殺するほど信義に反するものといえない場合には、上記条件に該当しないとして、退職金の全部又は一部を支給するよう命じています。
この結果、懲戒解雇であり、就業規則(退職金規程)に退職金不支給という条項があったとしても、全部不支給に値するか、再度立ち止まって検討する必要があります。
4.④ 元従業員が同業他社へ転職した場合
この場合も基本的な考え方は、上記「3」と同じです。
すなわち、同業他社へ転職することがこれまでの勤務期間における功労を抹消・減殺するほど信義に反するか否かによって、退職金不支給の有効性が判断されています。
これは、職業選択の自由という憲法上の要請から、転職の事由は最大限尊重されなければならないという考え方によるものと思われます。
※上記記載事項は当職の個人的見解をまとめたものです。解釈の変更や裁判所の判断などにより適宜見解を変更する場合がありますのでご注意下さい。