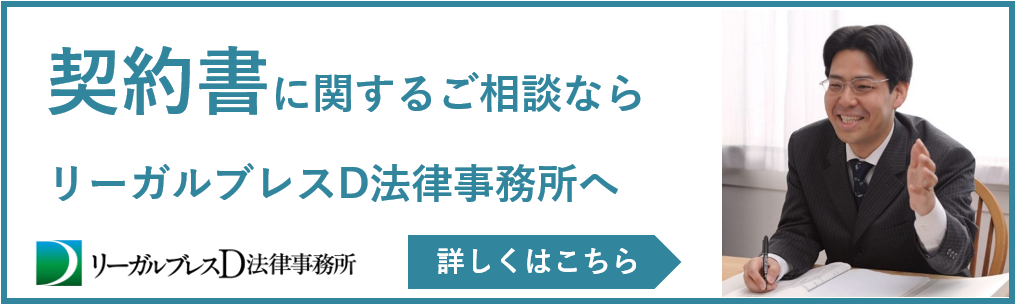IT業界で業務委託契約書を作成する場合の注意点とは?
Contents
【ご相談内容】
新規で取引を開始するに当たり、先方より業務委託契約書の作成依頼を受けました。
当社でも一応雛形はあるのですが、雛形が想定している取引内容と今回の取引内容とでは相違があり、そのまま用いるわけにはいかないと考えています。
業務委託契約書を作成するに際して、どのような点に注意を払えばよいのでしょうか。
【回答】
現場実務で用いられる契約書の中でも、業務委託契約書は頻度の高い契約書の1つと言えます。
しかし、使用頻度が高いにもかかわらず、実は民法や商法には業務委託契約という用語例は出てきません。つまり、法律では定義づけられていない契約となります。このため、一口に業務委託契約といっても、IT業界で用いられる業務委託契約には様々なものが含まれ、特に業界の特性上、無形資産を対象としたものが多くなるという特徴を有します。
本記事では、様々なタイプが存在する中で共通して問題となり得る条項を中心に、委託者・受託者双方の視点に立って解説を行います。
【解説】
1.業務委託契約とは
業務委託契約とは、ある者(委託者)が第三者(受託者)に対し、一定の業務を委ねて託する契約のことをいいます。
アウトソーシングといった言葉が用いられることもありますが、要は、事業者が第三者に外注する取引とイメージしておけば十分です。
2.業務委託契約のメリット・デメリット
業務委託契約のメリット、デメリットは次のように整理することができます。
【メリット】
|
・自らが保有しない技術・ノウハウ等を利用することが可能となり、高品質化を実現することが可能 ・委託対象となる業務について、内製化するよりも変動費化を図ることが可能 ・事業の選択と集中が可能
|
【デメリット】
|
・自社内で技術・ノウハウ等を蓄積できず、受託者への依存度が高まるリスク ・受託者の経営状態などの外部環境の変化により、かえってコストアップに繋がるリスク ・責任の所在が曖昧になるリスク
|
なお、デメリットについては、業務委託契約書の定め方によってある程度回避することが可能です。
例えば、受託者に対して技術・ノウハウ等の開示を義務付けることでリスクヘッジを図る、委託費用の定額化を定めることでリスクヘッジを図る、責任の分配を明確化することリスクヘッジを図るといったことが考えられます。
業務委託契約書作成及びチェックに際しては、是非意識しておきたいところです。
3.業務委託契約書の種類
IT業界で用いられる代表的な業務委託契約としては、次のような種類があります。
・開発制作契約(システム、プログラム、アプリ、WEB等)
・運用保守契約(稼働監視、バグ補修等)
・コンサルティング契約(SEO対策、WEBメディアの改善提案等)
・広告運用代行契約(広告キーワードの選定・入札、アフィリエイトの利用等)
・仲介媒介契約(人材紹介、ユーザマッチング等)
・外部人材利用契約(労働者派遣、フリーランス等)
さまざまな種類の業務委託契約が存在しますが、法的に考えた場合、事務の処理を目的とする委任(準委任)型の業務委託契約と、仕事の完成を目的とする請負型の業務委託契約とに分類して検討することが通常です(なお、委任は法律事務を対象とする契約、準委任は法律事務以外の業務を対象とする契約です。IT業界の場合、法律事務を対象とすることはまずないので、準委任契約と考えて間違いないと考えられます)。
そして、準委任と請負の相違点は次のようになります。
| 準委任 | 請負 | |
| 契約の目的 | 受託者は、委託者より依頼を受けた事務を処理すること | 受託者は、委託者より依頼を受けた仕事を完成させること |
| 受託者の義務 | 善管注意義務 | 仕事を完成させる義務 |
| 報酬請求権 | 事務を履行した後でなければ報酬請求できない | 仕事を完成させた後でなければ報酬請求できない |
| 契約解除 | 委託者と受託者は、いつでも契約解除可能 | 委託者は、仕事完成前であれば契約解除可能(受託者からは不可) |
| 再委託 | 原則不可 | 可 |
| 報告義務 | あり | なし |
(1)報酬
報酬に関する条項とは、例えば次のようなものです。
| 委託者は受託者に対し、次の区分にて報酬を支払う。
(1)着手時…×円 (2)中間金…×円 (3)完了時…×円 |
上記条項は、成果物の引渡しを念頭に置いた請負又は成果完成型委任(準委任)に多いものとなります。他にも業務遂行時間に応じて報酬が発生するタイムチャージ形式や月額固定払い形式など様々なものが想定されるところです。
さて、報酬に関する条項を定める場合、対価内容、報酬の算出方法、支払い時期、支払方法、支払に要する費用負担等につき、具体的に定めておく必要があります。なぜなら金銭が絡むことであり双方当事者にとって重大な利害関係があるところ、一度でも食い違いが生じれば大きな紛争に発展しがちだからです。
このようなトラブルを回避するためには、各当事者において次のような視点で上記条項を検討する必要があります。
【委託者側視点】
上記のような条項であれば、基本的には報酬の算出方法について気にする必要はないと考えられます。一方で、報酬から除外される費目は無いか(後述(2)のような実費は除外されていないか)、いつまでに支払う必要があるのか、現金以外の支払方法が認められているのか、振込手数料はどちらが負担するのか等については明確に定めておくべき事項となります。
なお、いわゆるタイムチャージ方式で報酬を算出する場合、青天井で予想外の金額になることも想定されますので、例えば1ヶ月当たりの上限金額を設けておいた方が安心かもしれません。
【受託者側視点】
基本的には委託者側視点で記述した通りです。
なお、受託者としては、追加業務が発生した場合等の理由で当初定めていた報酬では不足すると考える場合、必ずその旨委託者に申入れを行い、別途追加報酬の合意を取り付ける等の対応を行うべきです。
また、報酬の未払いがある場合、成果物の引渡しを拒否することができる、今後発生する業務を一時停止することができる(契約違反責任を負わない)等の債権回収に資する条項を追加できないか検討することも必要です。
(2)費用負担
費用負担に関する条項とは、例えば次のようなものです。
| 受託者は、業務遂行に要する費用について事前に委託者に報告し、委託者が承認した費用に限り、請求することができる。 |
この費用負担についてはトラブルになりやすい条項となります。
例えば、業務遂行に際して現地訪問が必要となる場合、それに要する旅費交通費や宿泊費はどちらが負担するのかといった問題が生じます。これ以外にも、成果物を制作するに際して第三者が権利を有するものを利用する場合、ライセンス料・利用料をどちらが負担するのかといった問題もあります。さらには、委託者が指定する場所で業務を行う場合の賃料や光熱費、機器の貸与があった場合の賃料なども問題となり得ます。
このようなトラブルを回避するためには、各当事者において次のような視点で上記条項を検討する必要があります。
【委託者側視点】
委託者としては、報酬以外に負担しなければならない費用が存在するのか、契約書をよくよく確認する必要があります。例えば、契約書によっては「実費について別途負担する」といった一文があるにもかかわらず、読み飛ばしていた場合、後で何が実費に含まれるのかにつき当事者双方でズレが生じ、トラブルとなりかねません。
委託者有利で考えるのであれば、一切の経費・実費は請求不可と明文化したいところですが、例えば、第三者が権利を有するものを利用する場合のライセンス料については、受益者である委託者が負担して然るべきと考えられます。
結局のところ、委託者が負担する費用と受託者が負担する費用等について区分し、それを契約書に定めておくというのが対処法となります。
【受託者側視点】
受託者としても、委託者が負担する費用と受託者が負担する費等について区分し、それを契約書に定めておくことが重要となります。
なお、サンプルのような条項案の場合、いくら必要性・相当性を説明したとしても、委託者の承認が無い限り、受託者負担とせざるを得ません。したがって、なるべくならサンプルのような条項案は用いず、せめて「別途協議する」という表現で、委託者が不合理に費用負担しない場合は、委託者に責任が発生すると解釈できるよう仕掛けを作りたいところです。
(3)中途解約時の清算方法
まず中途解約に関する条項は、一般的には次のようなものが多いと思われます。
| 委託者及び受託者は、3ヶ月前の予告期間をおいて通知することにより、いつでも本契約を解約することができる。 |
何らかの理由で成果を得ることが不要となった委託者、諸般の事情により業務を継続することができなくなった受託者双方において、契約を途中で解消できるようにしておくことは意義があります。
ただ、問題は中途解約した後の清算処理です。2020年4月施行の改正民法により請負の場合であっても一定条件を満たせば出来高報酬を求めることができるようになったとはいえ、出来高の算定方法は当事者双方で意見の対立が深刻になると思われます。
このようなトラブルを回避するためには、各当事者において次のような視点で上記条項を検討する必要があります。
【委託者側視点】
委託者としては、完成していない以上、報酬は支払いたくないと考えがちです。しかし、委託者都合による場合や委託者に帰責事由がある場合は、やはり何らかの清算が必要と考えられます。
ところで、受託者に帰省事由がある場合であっても、民法は清算義務を課しているところ(民法第634条、民法第648条参照)、受託者に帰責事由があるにもかかわらず報酬を支払うことについて抵抗感を覚える委託者は多いようです。この点を考慮するのであれば、受託者に帰責事由がある場合は清算義務が無いこと(報酬支払いは不要であること)を契約書に明記することがポイントとなります。
【受託者側視点】
受託者としては、時間と労力をかけた以上、業務遂行相当分だけでも報酬を支払ってほしいと考えるのが通常です。ただ、請負の場合、民法第634条では「請負人が既にした仕事の結果のうち可分な部分の給付によって注文者が利益を受けるとき」という条件が付いているため、当然に出来高払いを請求できるわけではないことに注意が必要です(なお、成果完成型の委任(準委任)の場合も同様です)。
純粋な出来高払いを求めるのであれば、中途解約時の清算方法につき適切な基準を契約書に定めておくことが重要となります。
(4)契約不適合責任
契約不適合責任に関する条項とは、例えば次のようなものです。
| 委託者は、納品された成果物に不適合がある場合、受託者に対し、成果物の修補、代替物の引渡し又は報酬減額請求をすることができる。 |
契約不適合責任は委任(準委任)では適用されないため、請負の場合に問題となる条項となります。
契約不適合責任は、2020年3月31日以前は瑕疵担保責任と呼ばれていたものに相当するのですが、民法改正により色々と発想の転換が迫られる内容となっています。瑕疵担保責任の知識のままで対処すると、誤解・認識不足によるトラブルが生じることから、各当事者において次のような視点で上記条項を検討する必要があります。
【委託者側視点】
責任追及するためには「不適合」があること、要は契約の目的を達成できない不具合があることが条件となるのですが、何をもって不適合と考えるのかは、双方当事者の見解対立が生じやすいと予想されます。上記2.(1)の「業務の範囲」と重複するのですが、契約から導き出される成果物はどのような質・程度のものなのかを明確に定め、双方当事者の認識を共有できるようにすることがポイントとなります。
また、民法上の契約不適合責任は、履行の追完(修補、代替物の引渡し、不足分の引渡し)が原則であり、代金減額請求は履行の追完請求を行った後でしか行使できないと定められています(民法第563条)。上記条項例では権利行使の順番はつけられていませんが、一応注意が必要です。
なお、履行の追完ですが、民法上は必ずしも委託者の希望通りに追完する必要はないと定められています(民法第562条第1項但書)。追完方法につき受託者に選択権を持たせたくないのであれば、民法第562条第1項但書の適用を排除する旨契約書に明記する必要があることも押さえておく必要があります。
【受託者側視点】
契約不適合責任が定められている場合、受託者としては
①責任追及開始日はいつに設定されているのか
②責任追及が可能な期間はどのように設定されているのか
③責任追及を受ける具体的内容はいかなるものと設定されているのか
をよく確認する必要があります。
なぜなら、①については、民法上は不適合を知ったときから責任追及可能と定められているため、例えば納品後5年経過してから委託者が不適合に気付いたとしても責任追及可能となっているからです。受託者としては、忘れた頃に責任追及を受けないようにするべく、納品日や検収合格日といった開始日を固定化することがポイントとなります。また、②については、民法上は不適合を知ったときから1年間と定められていますが、成果物の性質如何によっては1年では長すぎるという場合も想定されます。受託者としては、事例に応じて短期間に修正する等の対応が必要となります。さらに、③については、例えば負担する責任内容は履行の追完のみであり、代金減額請求や契約解除を免れたいと考えるのであれば、代金減額請求及び契約解除は不可であることを契約書に明記する必要があります。なお、履行の追完をもって損害賠償請求不可ということも付加したいところです。
ちなみに、システム制作の場合、制作完了後は運用保守業務を受託するということもあり得るかと思います。この場合、運用保守業務の一環として不適合の補修を行うことが多く、契約不適合責任と運用保守業務が重複するという場面も考えられます。この場合、契約不適合責任については一切負担しないとする特約を定めることも有用と考えられます。
(5)損害賠償
損害賠償に関する条項とは、例えば次のようなものです。
| 本契約に違反した場合、受託者は委託者が被った損害を賠償する。但し、損害賠償額は報酬額を上限とする。 |
この条項は非常に利害が対立しやすい条項となりがちです。
委託者からすれば被った全損害を請求したいところですし、受託者からすれば、あれもこれも損害であるという際限のない請求を是が非でも回避したいところです。このような条件交渉の応酬により、いつまで経っても契約を締結できないという事態にもなりかねません。
このようなトラブルを回避するためには、各当事者において次のような視点で上記条項を検討する必要があります。
【委託者側視点】
損害賠償の上限を設けることは、IT業界の受託者サイドとしては常識になりつつありますので、上限条項を削除するということは難しいかもしれません。この場合、委託者としては、将来生じるかもしれない損害につき、報酬額を上限とすることで十分カバーできるのかを検証しつつ、もう少し上限額をアップすることができないかを中心に交渉することがポイントとなります。あるいは、原則として上限条項を受入れつつ、受託者に故意又は重過失がある場合は上限条項の適用が排除されるといった例外を定めることも一案です。
また一方で、上記のような条項の場合、公平の観点から、委託者が責任を負う場合も上限を設定してほしいと交渉すると打開策が出てくることが多いように思われます(単純に委託者も上限条項を適用するという形で終ることも多いですが)。
なお、委託者としては、損害賠償の問題とは別に定められていることが多い免責条項を見落とすことなく、受託者の免責範囲が不当に拡大されていないかチェックすることも忘れてはなりません。
【受託者側視点】
受託者としては
①損害賠償請求の発生要件を制限することはできないか(故意・重過失に限定する)
②損害項目を一定の範囲内に収めることができないか(逸失利益等の特別損害を除外する)
③損害額につき上限を設定することができないか(上記サンプル条項例を参照)
を検討することになります。
ただ、当然のことながら委託者からの抵抗も強いため、落し所として、①②は譲歩するが、③は死守するといった柔軟な対応も必要となります。
また、損害賠償の条項に拘らず、免責条項を具体化することでリスクコントロールすることも検討に値します。
4.業務委託契約の注意点
(1)準委任と請負の区分の曖昧性
上記3.で記述した通り、業務委託契約を法的に検証するに当たっては、準委任と請負のどちらに該当するのかを考えることが多いのですが、実際の現場実務では、仕事の完成と事務の処理の両方の目的が混在するパターンの業務委託契約が存在したり、逆に仕事の完成なのか事務の処理なのか目的が判別できないパターンの業務委託契約が存在したりします。
特に2020年4月1日に施行された改正民法では、成果完成型の委任(準委任)契約が認められたため、ますます請負と委任(準委任)の区別が難しい状況です。
したがって、業務委託契約を検討するにあたっては、請負か委任(準委任)かについて過度にこだわらず、また民法や商法に定める請負or委任の規定に頼ることなく、契約当事者自らの手で権利義務関係を契約書に落とし込んでいくという意識が必要となります。
ただ、自らの手で契約書に権利義務関係を落とし込む…と言われても、簡単にできることではありません。弁護士の支援を求めたほうが望ましいのですが、ここでは、現場実務の担当者がどのような視点で業務委託契約を検証すればよいのか解説します。
ポイントは「業務」に関する条項と、「お金」に関する条項となります。
(2) 外部人材を利用する場合
業務委託契約のうち外部人材の利用に関するもの、例えば、労働者派遣契約、出向契約、構内請負、個人事業主(フリーランス)との契約については、民法以外の法規制を意識する必要があります。
すなわち、労働者派遣契約であれは労働者派遣法に基づく規制、出向契約であれば労働契約法に基づく規制があります。また、構内請負であれば偽装請負該当性の問題を避けて通ることはできません。さらに、個人事業主(フリーランス)の場合、そもそも労働者に該当し労働契約と評価されないか、労働者ではないとしても独占禁止法が適用されるのではないか、2024年以降はフリーランス新法(特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律)に基づき規制対象とならないか等に注意を払う必要があります。
なお、外部人材が日本国籍以外の者である場合、国内にいるのであれば入管法の問題、国外にいるのであれば準拠法の問題なども意識しなければなりません。
外部人材の利用を目的とする業務委託契約書を作成する場合、様々な法律を意識する必要があることから、弁護士の支援がマストであると考えるべきです。
(3)下請法との関係
業務委託契約に基づく取引内容が下請法に該当する取引である場合、下請法を意識して条項作成する必要があることに注意が必要です。なお、下請法については、次の記事をご参照ください。
企業が下請法を意識しなければならない場面(取引類型、資本関係)を弁護士が解説!
下請事業者による下請法の上手な活用法について、弁護士が解説!
(4)印紙税との関係
業務委託契約書を締結する場合、印紙税の問題を別途検討する必要があります。この点については、次の記事をご参照ください。
業務委託(委任、請負)契約を締結する際の印紙税のポイントを弁護士が解説!
(5)個別具体的な条項内容に関する注意事項
業務委託契約書に定める個別具体的な条項内容を作成・チェックするにあたり、是非とも注意しておきたいと考えられる事項について、以下の5.から7.では「業務」、「お金」、「一般条項」という分類に従い、解説していきます。
5.「業務」に関し注意したい条項
(1)業務の範囲
業務の範囲に関する条項とは、例えば次のようなものです。
| 委託者は受託者に対し、次に定める事項を委託し、乙はこれを受託する。
(1)委託者が使用する××システムの開発 (2)その他前号に付随する事項 |
例えばシステム開発契約において、上記のような条項を定めることはかなり多いように思います。
しかし、上記条項は非常に漠然としており、結局のところ何をどこまで開発すればよいのか一義的に判断することはできません。このため、システム完成後に、委託者は××の機能が実装されていない、レスポンスタイムが遅い等の理由で未完成又は不具合があると主張して報酬の支払いを拒絶する、一方受託者は××機能は特殊なものであり予算外である、レスポンスタイムも常識の範囲内であり完成済み又は不具合なしとして報酬の支払いを求める、といった紛争が起こったりします。
このようなトラブルを回避するためには、各当事者において次のような視点で上記条項を検討する必要があります。
【委託者側視点】
何をどこまでやってもらうのか、完成品をイメージしながら具体的に業務内容を特定し、契約書に記載することが重要となります。
もっとも、例えばシステム開発の事例の場合、自らでは開発できない(全く知識がない)から他人の力を借りるのであって、具体的な業務内容をイメージすることさえ難しいということがあるかもしれません。
この場合、例えば、受託者が契約前に提出している提案書や見積書、議事録等を参照しながら業務の洗い出しを行い契約書に記載していく、あるいは提案書等を契約書の別紙として引用し、提案書等に記述されている内容を契約に定める業務とするといった対策を講じることが考えられます。
【受託者側視点】
委託者視点と同様に、何をどこまで行うのか具体的に業務内容を特定し、契約書に記載することが重要です。
ただ、契約締結段階では、当事者間で完成品のイメージ共有ができておらず、今後の協議によって整理を図るという場合もよくある話です。
この場合、逆転の発想となりますが、受託者において行わない業務は何かをピックアップし、契約締結時点ではっきりしている除外業務を個別具体的に明記することで、業務範囲の絞り込みをかけるということが有用と考えられます。
(2)履行方法
業務の履行方法に関する条項とは、例えば次のようなものです。
| 受託者は、×年×月×日までに委託者が指定する場所に××システムを納品する。 |
システム開発において、最終目標はシステムを完成させ、委託者が指定するサーバ等に格納することですので、上記条項は間違いではありません。
しかし、システム開発の場合、納品までに、企画・基本設計・プログラム制作・運用準備支援といった業務プロセスを踏み、委託者と受託者が協力しながら業務を進めていくことが通常です。このため、各プロセスにおいて、実施期間・役割分担・作業範囲等を明確にしておかないことには、後々混乱や支障を来し、最悪の場合システムが完成しないということさえあります。
このようなトラブルを回避するためには、各当事者において次のような視点で上記条項を検討する必要があります。
【委託者側視点】
委託者としては、必要な協力は惜しまないとはいえ、経験・スキル等が不足している以上、基本的には受託者主導で業務を進めてもらいたいと考えています。この点を考慮して、システム開発契約の場合、最近では受託者に対してプロジェクトマネジメント義務を明記することが多くなってきています。
しかし、抽象的にプロジェクトマネジメント義務を課し、全てを受託者に押し付けても物事は進みません。
とはいえ、委託者として何をどこまですればよいのか分からないのも事実ですので、委託者の負担するべき範囲として、例えば受託者より明示的な要請があった場合のみ協力する(いわゆる空気を読んで委託者が先行して対処しなければならない範囲を極力なくす)といった内容を契約書に記載し、各自の役割分担を明らかにするといった対策が検討に値します。
【受託者側視点】
上記ではシステム開発を取り上げましたが、システム開発以外の業務であっても、委託者に協力してもらわないことには業務を進めようがないという場面が多々生じます。この点を考慮し、システム開発契約の場合、最近では委託者が協力義務を負うことを明記することが多くなってきています。
ただ、一般論として協力義務を負担することを定めたところで、委託者としては、業務を任せた以上、受託者が主導的に対処してくれると期待しており、この期待は正しいと言わざるを得ません。
したがって、委託者に求める協力内容を契約書に具体的に明記すること(例:必要資料を提供する、定期的なミーティングを開催し意見交換と認識共有を図る、2つ以上の選択肢がある場合において期日までに決定してもらうなど)が重要となります。
(3)貸与物の取扱い
貸与物の取扱いに関する条項とは、例えば次のようなものです。
| 委託者は受託者に対し、業務遂行に当たり必要となる資料等を提供する。 |
業務を進めていくためには、委託者が保有する資料や情報を受託者に開示しなければならない場面が出てきます。したがって、上記条項自体は特に違和感なく受け入れることが多いかと思うのですが、提供された資料等の提供条件や取扱い方法等についても触れておかないことには、後で思わぬトラブルを招くことにもなりかねません。
このようなトラブルを回避するためには、各当事者において次のような視点で上記条項を検討する必要があります。
なお、貸与物の取扱いに準じるものとして、機器の貸与や作業場所を提供する場合、提供条件や取扱い方法等以外に金銭負担の問題を意識する必要があります。また、営業秘密や個人情報等の取扱いに細心の注意を払う情報が開示される場合、情報漏洩対策を含めた安全管理措置を定めておく必要があります。
【委託者側視点】
委託者が受託者に提供した資料等について、①受託者は善管注意義務を負うこと、②受託者に対し業務遂行目的以外での使用を禁止すること、③契約終了後その他委託者の指示があった場合、受託者は返還(又は破棄)義務を負うこと、少なくともこの3点については契約書に明記し、委託者のコントロールが及ぶ状態を作出したいところです。
【受託者側視点】
委託者より資料等の提供を受けるに際して、何らかの金銭負担が発生するのかを確認すると共に、無償提供であるのであればその旨契約書に明記することが望ましいと言えます。
また、資料等の提供を受けることでかえって重い義務負担を課せられることにならないか(重厚な安全管理措置を講じる義務を負担する等)を検討し、場合によっては提供を受けず、委託者の管理支配するスペース内で閲覧するのみに留め、その際のルールを契約書に明記するといった対応も検討する必要があります。
(4)再委託
再委託に関する条項とは、例えば次のようなものです。
| 受託者は、第三者に業務を再委託することができない。 |
業務委託契約が請負に該当する場合、受託者の自由裁量により再委託させることが法的に可能ですが(なお、委任・準委任の場合は当然に再委託させることはできません)、委託者としては責任の所在を明らかにする等の目的で、再委託不可という条項を盛り込みがちです。
しかし、システム開発等であれば、受託者が協力会社を用いて成果物を制作することは当たり前のように行われており、再委託を絶対に禁止するというのは現実的ではなく、かえって業務が遂行できないというトラブルを招きかねません。
このようなトラブルを回避するためには、各当事者において次のような視点で上記条項を検討する必要があります。
【委託者側視点】
再委託は原則不可としつつ、①委託者が承諾した場合のみ再委託可とする、②受託者が負担する契約上の義務を再委託先にも負担させ、遵守させる義務を課す、③再委託先による業務遂行は受託者による業務遂行とみなし、再委託先による不履行について全責任を負うことを約束させる、といった条項を明記することが得策と考えられます。
なお、再委託は受託者の自由裁量に任せるというパターンも十分想定されます。その場合、上記②及び③を契約書に定めることはもちろん、再委託先の会社情報等につき受託者は報告義務を負うという内容を契約書に定めておくことで、委託者による統制を図ることも検討に値します。
【受託者側視点】
再委託が当初より予定されているのであれば、契約書の文言を再委託可と修正するか、又は契約締結時に再委託に関する同意書を別途取得することが対処法となります。
なお、再委託先に受託者の名刺を持たせ、あたかも受託者の従業員であるかのような外観を呈して業務遂行させるという方法が、かなり横行しているようです。当然のことながら再委託禁止条項に違反しますし、何か事故等が生じた場合、受託者は契約違反であることを認識しながら業務遂行していたこと、すなわち悪質性を基礎づける事由となってしまい、委託者の怒りをかってしまうこともあります。また、故意の契約違反であるとして、いざというときに頼りにしていた損害保険が使えないという場面が生じ得ます。
したがって、上記のような方法は厳に慎むべきです。
(5)報告
業務遂行状況の報告に関する条項とは、例えば次のようなものです。
| 受託者は、委託者より請求を受けた場合、業務の進捗状況について速やかに報告する。 |
業務期間が短期で成果物が一義的に明確になっている場合であれば、わざわざ進捗状況について、委託者は報告を求めませんし、受託者も報告しないことが多いと思われます。
一方、数年単位のプロジェクト案件等であれば、むしろ適切な時期に報告会を開催するなどして、当事者双方の認識をその都度共有しないことには、最終成果物が委託者の意に沿わない等のトラブルが生じる恐れがあります。
このようなトラブルを回避するためには、各当事者において次のような視点で上記条項を検討する必要があります。
【委託者側視点】
委託者としては、順調に業務が進んでいるのか(納期に間に合うのか)、委託者の考え通りに成果物は仕上がっているのか等気になるところです。したがって、上記のような、委託者の任意のタイミングで受託者に報告義務を課す条項を設けることは非常に有益となります。
なお、そもそも上記のような条項が業務委託契約書に定められていないこともあります。理論的に考えた場合、業務委託契約の法的性質が委任(準委任)に該当するのであれば、民法第645条に基づき報告義務を課すことができますが、請負の場合、当然に報告義務を課すことはできません。この点については注意が必要です。
【受託者側視点】
現場実務でよく聞く話として、受託者が委託者に報告を行っても一切の返答がない、委託者が選択するべき事項を決定してくれない…という不満や困惑です。そのような現場実務の声を踏まえると、上記のような条項では物足りず、むしろ1ヶ月に1回の定例報告会を開催するといったことまで条項化することも一案です。
また、しばしばよく問題になる事項として、受託者は委託者の誰に報告を行えばよいのかという点です。受託者が報告義務を負担する場合、報告先となる委託者の責任者名や責任部署を明示することも検討するべきです。
(6)業務完了
業務の完了に関する条項とは、例えば次のようなものです。
| 受託者が委託者の指定する場所に成果物を納品することで、業務完了とする。 |
請負型の業務委託契約の場合、何をすれば業務完了となるのか定めることが多いところ、上記条項例は「成果物の納品」をもって業務完了と定めており、常識的な内容といえます。
ただ、よくよく考えると、不具合の有無を問わず納品したという事実のみをもって業務完了としてよいのか、不具合が一切ない状態で納品しない限り業務完了とはいえないのか、上記条項からは明らかではありません。
そして、業務完了時期が曖昧なことは、他の問題にも派生することになります。例えば、報酬の支払い義務は発生しているのか、所有権や知的財産権の移転はしているのか、危険負担への対応はどうするのか等です。
このように業務完了は様々な事項に影響を及ぼす事項であるところ、曖昧なままでは複数のトラブルが勃発することになりかねません。このようなトラブルを回避するためには、各当事者において次のような視点で上記条項を検討する必要があります。
【委託者側視点】
委託者としては、不具合が無い状態にて業務完了としたい(不具合があれば、受託者に無償補修対応をさせたい)と考えるのが通常です。
そうであれば、委託者による検収手続きと検収合格をもって業務完了とする旨定めることは必須の対応と言えます。
なお、業務完了に伴い派生する事項については、検収完了を基準にするのか(例:報酬の支払い時期など)、納品を基準とするのか(例:危険負担への対応など)を分けて検討する必要があります。
【受託者側視点】
委託者より検収手続きと検収合格をもって業務完了としたい旨の申入れがあった場合、ある程度は受け入れざるを得ません。受託者としては、検収手続きが行われることを前提に、①検収合格基準のすり合わせを行うこと、②一定期間内に連絡が無い場合はみなし合格とすること、③業務完了後に見つかった不具合への補修対応の範囲・条件等を明確化する、といった対案を出しながら交渉を進めていくのが現実的対応と考えられます。
(7)業務内容の変更
業務内容の変更に関する条項とは、例えば次のようなものです。
| 委託者及び受託者は、業務内容について変更の必要があると判断した場合、変更の可否につき協議を行う。 |
一見すると当たり前のことしか書いていないように思われるかもしれません。
しかし、例えば、協議が決裂した場合、受託者は今後どのように業務を遂行していけばよいのか、一方で協議が整った場合、何をもって協議が成立したとするのか判然としません。
結局のところ、協議を行った後のことを見据えて契約書に定めておくことが必要であるところ、その点を明記しなかったがために、極端な場合かもしれませんが、協議が成立しなかったことを理由に責任追及を受けるといったトラブルさえ想定されるところです。
このようなトラブルを回避するためには、各当事者において次のような視点で上記条項を検討する必要があります。
【委託者側視点】
委託者より変更要請を行うことも想定されますが、受託者より変更要請を受ける場合も当然あり得る話です。ただ、どちらが行うにせよ、変更合意が成立したと言える場面を明確にしておくことが有用です。その観点から、合意成立は口頭ではなく書面に限定することを契約書に明記することを検討してもよいかもしれません。
なお、委託者としては、受託者からの変更要請を拒絶したことをもって、契約違反とはならないこと(責任追及を受けないこと)も明記したいところです。
【受託者側視点】
受託者としても、合意成立の場面を限定したほうがトラブル防止に役立つという意味で、委託者側視点で解説した事項が当てはまります。
一方、受託者特有の視点から検討すると、協議中は業務を中断できること、中断に伴い納期が後ろ倒しとなることを明示することが有用です。また、万一協議が決裂した場合、当初の合意通りに業務を遂行すれば契約違反とはならないということを明記することもポイントとなります。
なお、協議の際に当然交渉することになるかと思いますが、業務変更により業務量が増大した場合は報酬が増額となること、納期が変更となること、当初の提案資料や契約締結時の仕様等の記載事項につき確約ができないこと等も明記したいところです。
6.「お金」に関し注意したい条項
(1)報酬
報酬に関する条項とは、例えば次のようなものです。
| 委託者は受託者に対し、次の区分にて報酬を支払う。
(1)着手時…×円 (2)中間金…×円 (3)完了時…×円 |
上記条項は、成果物の引渡しを念頭に置いた請負又は成果完成型委任(準委任)に多いものとなります。他にも業務遂行時間に応じて報酬が発生するタイムチャージ形式や月額固定払い形式など様々なものが想定されるところです。
さて、報酬に関する条項を定める場合、対価内容、報酬の算出方法、支払い時期、支払方法、支払に要する費用負担等につき、具体的に定めておく必要があります。なぜなら金銭が絡むことであり双方当事者にとって重大な利害関係があるところ、一度でも食い違いが生じれば大きな紛争に発展しがちだからです。
このようなトラブルを回避するためには、各当事者において次のような視点で上記条項を検討する必要があります。
【委託者側視点】
上記のような条項であれば、基本的には報酬の算出方法について気にする必要はないと考えられます。一方で、報酬から除外される費目は無いか(後述(2)のような実費は除外されていないか)、いつまでに支払う必要があるのか、現金以外の支払方法が認められているのか、振込手数料はどちらが負担するのか等については明確に定めておくべき事項となります。
なお、いわゆるタイムチャージ方式で報酬を算出する場合、青天井で予想外の金額になることも想定されますので、例えば1ヶ月当たりの上限金額を設けておいた方が安心かもしれません。
【受託者側視点】
基本的には委託者側視点で記述した通りです。
なお、受託者としては、追加業務が発生した場合等の理由で当初定めていた報酬では不足すると考える場合、必ずその旨委託者に申入れを行い、別途追加報酬の合意を取り付ける等の対応を行うべきです。
また、報酬の未払いがある場合、成果物の引渡しを拒否することができる、今後発生する業務を一時停止することができる(契約違反責任を負わない)等の債権回収に資する条項を追加できないか検討することも必要です。
(2)費用負担
費用負担に関する条項とは、例えば次のようなものです。
| 受託者は、業務遂行に要する費用について事前に委託者に報告し、委託者が承認した費用に限り、請求することができる。 |
この費用負担についてはトラブルになりやすい条項となります。
例えば、業務遂行に際して現地訪問が必要となる場合、それに要する旅費交通費や宿泊費はどちらが負担するのかといった問題が生じます。これ以外にも、成果物を制作するに際して第三者が権利を有するものを利用する場合、ライセンス料・利用料をどちらが負担するのかといった問題もあります。さらには、委託者が指定する場所で業務を行う場合の賃料や光熱費、機器の貸与があった場合の賃料なども問題となり得ます。
このようなトラブルを回避するためには、各当事者において次のような視点で上記条項を検討する必要があります。
【委託者側視点】
委託者としては、報酬以外に負担しなければならない費用が存在するのか、契約書をよくよく確認する必要があります。例えば、契約書によっては「実費について別途負担する」といった一文があるにもかかわらず、読み飛ばしていた場合、後で何が実費に含まれるのかにつき当事者双方でズレが生じ、トラブルとなりかねません。
委託者有利で考えるのであれば、一切の経費・実費は請求不可と明文化したいところですが、例えば、第三者が権利を有するものを利用する場合のライセンス料については、受益者である委託者が負担して然るべきと考えられます。
結局のところ、委託者が負担する費用と受託者が負担する費用等について区分し、それを契約書に定めておくというのが対処法となります。
【受託者側視点】
受託者としても、委託者が負担する費用と受託者が負担する費用等について区分し、それを契約書に定めておくことが重要となります。
なお、サンプルのような条項案の場合、いくら必要性・相当性を説明したとしても、委託者の承認が無い限り、受託者負担とせざるを得ません。したがって、なるべくならサンプルのような条項案は用いず、せめて「別途協議する」という表現で、委託者が不合理に費用負担しない場合は、委託者に責任が発生すると解釈できるよう仕掛けを作りたいところです。
(3)中途解約時の清算方法
まず中途解約に関する条項は、一般的には次のようなものが多いと思われます。
| 委託者及び受託者は、3ヶ月前の予告期間をおいて通知することにより、いつでも本契約を解約することができる。 |
何らかの理由で成果を得ることが不要となった委託者、諸般の事情により業務を継続することができなくなった受託者双方において、契約を途中で解消できるようにしておくことは意義があります。
ただ、問題は中途解約した後の清算処理です。2020年4月施行の改正民法により請負の場合であっても一定条件を満たせば出来高報酬を求めることができるようになったとはいえ、出来高の算定方法は当事者双方で意見の対立が深刻になると思われます。
このようなトラブルを回避するためには、各当事者において次のような視点で上記条項を検討する必要があります。
【委託者側視点】
委託者としては、完成していない以上、報酬は支払いたくないと考えがちです。しかし、委託者都合による場合や委託者に帰責事由がある場合は、やはり何らかの清算が必要と考えられます。
ところで、受託者に帰責事由がある場合であっても、民法は清算義務を課しているところ(民法第634条、民法第648条参照)、受託者に帰責事由があるにもかかわらず報酬を支払うことについて抵抗感を覚える委託者は多いようです。この点を考慮するのであれば、受託者に帰責事由がある場合は清算義務が無いこと(報酬支払いは不要であること)を契約書に明記することがポイントとなります。
【受託者側視点】
受託者としては、時間と労力をかけた以上、業務遂行相当分だけでも報酬を支払ってほしいと考えるのが通常です。ただ、請負の場合、民法第634条では「請負人が既にした仕事の結果のうち可分な部分の給付によって注文者が利益を受けるとき」という条件が付いているため、当然に出来高払いを請求できるわけではないことに注意が必要です(なお、成果完成型の委任(準委任)の場合も同様です)。
純粋な出来高払いを求めるのであれば、中途解約時の清算方法につき適切な基準を契約書に定めておくことが重要となります。
(4)契約不適合責任
契約不適合責任に関する条項とは、例えば次のようなものです。
| 委託者は、納品された成果物に不適合がある場合、受託者に対し、成果物の修補、代替物の引渡し又は報酬減額請求をすることができる。 |
契約不適合責任は委任(準委任)では適用されないと考えられるため、請負の場合に問題となる条項となります。
契約不適合責任は、2020年3月31日以前は瑕疵担保責任と呼ばれていたものに相当するのですが、民法改正により色々と発想の転換が迫られる内容となっています。瑕疵担保責任の知識のままで対処すると、誤解・認識不足によるトラブルが生じることから、各当事者において次のような視点で上記条項を検討する必要があります。
【委託者側視点】
責任追及するためには「不適合」があること、要は契約の目的を達成できない不具合があることが条件となるのですが、何をもって不適合と考えるのかは、双方当事者の見解対立が生じやすいと予想されます。上記5.(1)の「業務の範囲」と重複するのですが、契約から導き出される成果物はどのような質・程度のものなのかを明確に定め、双方当事者の認識を共有できるようにすることがポイントとなります。
また、民法上の契約不適合責任は、履行の追完(修補、代替物の引渡し、不足分の引渡し)が原則であり、代金減額請求は履行の追完請求を行った後でしか行使できないと定められています(民法第563条)。上記条項例では権利行使の順番はつけられていませんが、一応注意が必要です。
なお、履行の追完ですが、民法上は必ずしも委託者の希望通りに追完する必要はないと定められています(民法第562条第1項但書)。追完方法につき受託者に選択権を持たせたくないのであれば、民法第562条第1項但書の適用を排除する旨契約書に明記する必要があることも押さえておく必要があります。
【受託者側視点】
契約不適合責任が定められている場合、受託者としては、①責任追及開始日はいつに設定されているのか、②責任追及が可能な期間はどのように設定されているのか、③責任追及を受ける具体的内容はいかなるものと設定されているのか、をよく確認する必要があります。
なぜなら、①については、民法上は不適合を知ったときから責任追及可能と定められているため、例えば納品後5年経過してから委託者が不適合に気付いたとしても責任追及可能となっているからです。受託者としては、忘れた頃に責任追及を受けないようにするべく、納品日や検収合格日といった開始日を固定化することがポイントとなります。また、②については、民法上は不適合を知ったときから1年間と定められていますが、成果物の性質如何によっては1年では長すぎるという場合も想定されます。受託者としては、事例に応じて短期間に修正する等の対応が必要となります。さらに、③については、例えば負担する責任内容は履行の追完のみであり、代金減額請求や契約解除を免れたいと考えるのであれば、代金減額請求及び契約解除は不可であることを契約書に明記する必要があります。なお、履行の追完をもって損害賠償請求不可ということも付加したいところです。
ちなみに、システム制作の場合、制作完了後は運用保守業務を受託するということもあり得るかと思います。この場合、運用保守業務の一環として不適合の補修を行うことが多く、契約不適合責任と運用保守業務が重複するという場面も考えられます。この場合、契約不適合責任については一切負担しないとする特約を定めることも有用と考えられます。
(5)損害賠償
損害賠償に関する条項とは、例えば次のようなものです。
| 本契約に違反した場合、受託者は委託者が被った損害を賠償する。但し、損害賠償額は報酬額を上限とする。 |
この条項は非常に利害が対立しやすい条項となりがちです。
委託者からすれば被った全損害を請求したいところですし、受託者からすれば、あれもこれも損害であるという際限のない請求を是が非でも回避したいところです。このような条件交渉の応酬により、いつまで経っても契約を締結できないという事態にもなりかねません。
このようなトラブルを回避するためには、各当事者において次のような視点で上記条項を検討する必要があります。
【委託者側視点】
損害賠償の上限を設けることは、IT業界の受託者サイドとしては常識になりつつありますので、上限条項を削除するということは難しいかもしれません。この場合、委託者としては、将来生じるかもしれない損害につき、報酬額を上限とすることで十分カバーできるのかを検証しつつ、もう少し上限額をアップすることができないかを中心に交渉することがポイントとなります。あるいは、原則として上限条項を受入れつつ、受託者に故意又は重過失がある場合は上限条項の適用が排除されるといった例外を定めることも一案です。
また一方で、上記のような条項の場合、公平の観点から、委託者が責任を負う場合も上限を設定してほしいと交渉すると打開策が出てくることが多いように思われます(単純に委託者も上限条項を適用するという形で終ることも多いですが)。
なお、委託者としては、損害賠償の問題とは別に定められていることが多い免責条項を見落とすことなく、受託者の免責範囲が不当に拡大されていないかチェックすることも忘れてはなりません。
【受託者側視点】
受託者としては、①損害賠償請求の発生要件を制限することはできないか(故意・重過失に限定する)、②損害項目を一定の範囲内に収めることができないか(逸失利益等の特別損害を除外する)、③損害額につき上限を設定することができないか(上記サンプル条項例を参照)を検討することになります。
ただ、当然のことながら委託者からの抵抗も強いため、落し所として、①②は譲歩するが、③は死守するといった柔軟な対応も必要となります。
また、損害賠償の条項に拘らず、免責条項を具体化することでリスクコントロールすることも検討に値します。
7.一般条項のうち、特に注意しておきたい条項
IT業界特有の条項とは言い切れませんが、しかし定めるにあたって、IT業界特有の事情を考慮したほうが良い条項がいくつかあります。
ここでは代表的な5つの条項につき解説します。
(1)契約目的
契約目的に関する条項とは、例えば次のようなものです。
| 委託者は受託者に対し、××の業務を委託し、受託者はこれを受託する。 |
契約書の冒頭付近に定められていることが多い条項です。これまではあまり重要視されることがなかった条項ですが、2020年4月1日より施行された改正民法を念頭に置いた場合、今後スポットライトを浴びる可能性が出てきています。
したがって、各当事者において次のような視点で上記条項を検討する必要があります。
【委託者側視点】
改正民法では、履行不能(民法第412条の2第1項)、債務不履行に基づく損害賠償請求(民法第415条第1項但書)、契約不適合責任(民法第562条)などで、「契約の目的」が考慮要素になることを定めています。これにより、「契約の目的」を具体的かつ詳細に契約書に明記することで、例えば、従来の解釈論であれば特別損害として損害賠償対象となりえなかった損害が、通常損害として損害賠償対象になり得るということが起こりえます。
したがって、契約締結前の交渉内容、契約締結に至った背景事情、契約により実現しようとしている事項などを明記し、これらを「契約の目的」を構成する要素として取り込むことで、契約による保護範囲をコントロールすることがポイントとなります。
【受託者側視点】
基本的には委託者側視点で記載した内容と同様です。
なお、受託者としては、「契約の目的」が具体的かつ詳細に記載されることにより、責任範囲が拡大する恐れがあることを踏まえ、契約の目的条項の記載内容を精査することはもちろん、契約の目的条項により影響を及ぼし得る各条項を見直す必要がないかという視点も重要となります(例えば、損害賠償条項であれば、逸失利益は損害賠償の対象にならないことを明記するといった対応です。なお、上記6.(5)記載内容も参照してください)。
(2)契約期間
契約期間に関する条項とは、例えば、次のようなものです。
| 本契約の有効期間は、×年×月×日から1年間とする。 |
あまりにも当たり前すぎる条項のため、特に問題意識を持つことなく読み飛ばしがちです。しかし、契約期間は適切か、中途解約は禁止されるのか、契約期間満了後はどうなるのか…といった契約の拘束力という視点で検討を進めないことには、思わぬ落とし穴にはまってしまうこともあります。
したがって、各当事者において次のような視点で上記条項を検討する必要があります。
【委託者側視点】
委託者としては、契約期間が適切に設定されているか、継続的な取引を希望するのであれば自動更新条項を設ける必要がないかを考慮することがポイントとなります。
また、業務委託契約が基本契約と位置付けられる場合、基本契約が期間満了により終了した時点で未履行の個別契約につき、どのような処理を行うのかルールを定めておくことも重要な視点となります。
さらに、基本契約が終了した場合であっても、なお効力を維持したい条項がないか(例えば秘密保持義務を契約終了後の一定期間課しておく必要がないか等)を検討することも必要となります。
【受託者側視点】
基本的には委託者側視点で記載した内容と同様ですが、受託者特有の視点としては、中途解約の可否になります。
まず、受託者が中途解約権を保有したいのであれば、その点を明記することは必須と言えます(特に、業務委託契約の法的性質が請負の場合、法的に受託者は当然に中途解約権を有しないことに注意が必要です)。
一方、委託者による中途解約については、業務委託契約の法的性質が準委任の場合は民法第651条第1項により、請負の場合は民法第641条により、いつでも自由に中途解約可能であることを押さえておく必要があります。したがって、契約期間の拘束力を高めるのであれば、中途解約禁止条項を明記する必要があります。なお、委託者による中途解約を認めざるを得ない場合は、清算ルールを定めることが重要となりますので、上記6.(3)記載内容を参照してください。
(3)禁止事項
禁止事項に関する条項とは、例えば次のようなものです。
| 委託者及び受託者は、あらかじめ書面により相手方の承諾を得ない限り、次の行為をしてはならない。
①本契約及び個別契約上の権利義務ならびに本契約及び個別契約上の地位を、第三者に譲渡、移転その他の方法により処分すること ②×××(省略) |
上記サンプル条項では、とりあえず債権譲渡及び契約上の地位譲渡を禁止する条項をあげておきましたが、禁止事項は、業務委託契約に基づき、どのような取引を行うのかによって定める内容が異なってきます。
したがって、各当事者は、取引内容に応じて、次のような視点で上記条項を検討する必要があります。
【委託者側視点】
システム・プログラム・アプリ・WEB等の開発委託契約の場合、両当事者の役割分担(委託者であれば協力義務、受託者であればプロジェクトマネジメント義務)が重要となります。したがって、例えば、委託者に対する報告遅延の禁止、委託者の指示に誤りがあることを認識しながら直ちに指摘しないことの禁止等を定めておくことが考えられます。
稼働監視、バグ補修等の運用保守契約の場合、例えば、委託者からの問い合わせに対して一定時間内に応答しないことの禁止、合理的説明のない追加費用請求の禁止等を定めておくことが考えられます。
SEO対策、WEBメディアの改善提案等のコンサルティング契約の場合、例えば、委託者の指示に反する業務遂行の禁止(委託者の事前確認が行われていない、受託者による裁量遂行の禁止)、プラットフォーマーの方針変更があったにもかかわらず、修正せずに放置することの禁止等を定めておくことが考えられます。
広告キーワードの選定・入札、アフィリエイトの利用等の広告運用代行契約の場合、例えば、効果測定に必要な情報提供を行わないことの禁止、不適当なアフィリエイター選定の禁止等を定めておくことが考えられます。
人材紹介、ユーザマッチング等の仲介媒介契約の場合、例えば、受託者が認識した対象人材の問題点に関する情報提供を行わないことの禁止、マッチング不成立となった後、別の機会を通じてユーザとマッチングした場合の報告義務及びみなし報酬支払い義務の禁止等を定めておくことが考えられます。
労働者派遣、フリーランス等の外部人材利用契約の場合、例えば、派遣契約終了後の派遣従業員との直接契約を制限することの禁止、外部人材による無断再委託の禁止等を定めておくことが考えられます。
【受託者側視点】
システム・プログラム・アプリ・WEB等の開発委託契約の場合、両当事者の役割分担が重要であること前述の通りです。したがって、例えば、受託者が必要とする情報提供の拒否及び遅延を禁止する、一方的な仕様変更を禁止する等を定めておくことが考えられます。
稼働監視、バグ補修等の運用保守契約の場合、例えば、偽装請負防止の観点から委託者による受託者の作業者に対する直接指示を禁止する、受託者の人材確保の観点から委託者による作業者の引き抜きを禁止する等を定めておくことが考えられます。
SEO対策、WEBメディアの改善提案等のコンサルティング契約の場合、委託者に対し、例えば、成果物の第三者開示の禁止、無断転用・使用の禁止等を定めておくことが考えられます。
広告キーワードの選定・入札、アフィリエイトの利用等の広告運用代行契約の場合、委託者に対し、例えば、受託者からの提案に対する回答遅延の禁止、法令を無視した広告コンテンツの運用禁止等を定めておくことが考えられます。
人材紹介、ユーザマッチング等の仲介媒介契約の場合、例えば、受託者を介さない直接契約の禁止(受託者による成約報酬請求を妨害する行為の禁止)、委託者と対象人材等とのトラブルにつき受託者に責任追及することの禁止等を定めておくことが考えられます。
労働者派遣、フリーランス等の外部人材利用契約の場合、例えば、法令違反の禁止(派遣受入期間に関する虚偽報告の禁止など)、他の従事者と比較した場合の差別待遇の禁止等を定めておくことが考えられます。
(4)秘密保持
秘密保持に関する条項とは、例えば次のようなものです。
| 委託者及び受託者は、相手方当事者の承諾なくして、相手方当事者から開示された営業上又は技術上の秘密情報(以下「秘密情報」という)を、第三者に対して開示、漏洩してはならず、本契約の履行以外の目的で使用してはならない。ただし、以下のいずれかに該当する情報は秘密情報には含まれない。
(1)開示された時点において、既に公知であった情報 (2)開示された後に受託者の責任によらないで公知になった情報 (3)開示された時点において、受託者が既に了知していた情報 (4)正当な権限を有する第三者から、受託者が秘密保持義務を負うことなく適法に取得した情報 |
業務委託契約書の一条項として秘密保持義務を定める場合、上記サンプル条項のような簡単なものになることが多いようです。ただ、業務委託契約とは別に秘密保持契約も締結する場合、秘密保持義務が2種類定められることになりますので、どちらが優先して適用されるのか等を意識する必要があります。
その他にも各当事者は、次のような視点で上記条項を検討する必要があります。
【委託者側視点】
上記サンプル条項では問題となりませんが、場合によっては委託者のみ秘密保持義務を負担する内容となっている場合がありますので、果たしてこれでよいのか検討することがポイントとなります。
また、委託者が秘密情報を開示する側であれば、秘密情報に含まれる情報の範囲が適切か、形式的には秘密情報の例外に該当するが、更なる例外扱いにしなければならない情報が存在しないか(要は、原則に戻って秘密情報として取扱うということです)、行政機関等より開示要請があった場合は当然に秘密情報から除外されるという定め方になっていないか等を意識する必要があります。
逆に委託者が秘密情報の開示を受ける側であれば、秘密情報の範囲を限定する必要はないか、何らかのメルクマールを付す必要はないかといった視点をもって検討することになります。
【受託者側視点】
基本的には委託者側視点で記載した通りです。
なお、専ら受託者が開示を受ける側の場合、秘密情報の取扱いについて特殊な対応を義務付けられていないか精査する必要があります(例えば、インターネットに繋がっていないサーバ内に秘密情報を保管する義務が課されている、事業所内にアクセスが限定された隔離部屋を設け、当該隔離部屋内に秘密情報を保管することが義務付けられている等)。
(5)反社会的勢力の排除
反社会的勢力に関する条項とは、例えば次のようなものです。
| 1.委託者及び受託者は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動等標榜ゴロ、その他これに準ずる者(以下「反社会的勢力」という。)のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約する。
2.委託者及び受託者は、相手方が次の各号のいずれかに該当する場合、ただちに本契約を解除することができ、解除により相手方に損害が生じてもこれを賠償することを要しない。 (1)相手方または相手方の役員が反社会的勢力に該当すると認められるとき (2)相手方の経営に反社会的勢力が実質的に関与していると認められるとき (3)相手方が反社会的勢力を利用していると認められるとき (4)相手方が反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められるとき (5)相手方または相手方の役員もしくは相手方の経営に実質的に関与している者が反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有しているとき (6)自らまたは第三者を利用して、暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求行為、脅迫的な言動、暴力および風説の流布・偽計・威力を用いた信用毀損・業務妨害その他これらに準ずる行為に及んだとき 3.委託者及び受託者は、自己が前項各号に該当したため相手方が本契約を解除した場合、相手方に生じた損害を賠償しなければならない。 |
いわゆる反社条項は、ある程度画一化された内容が出回っているため、あまり細部にわたってチェックしない条項かもしれません。ただ、よくよく検討してみると不自然な内容であったり、現実に遵守できるのか疑問の残る内容であったりということがあります。
したがって、各当事者において次のような視点で上記条項を検討する必要があります。
【委託者側視点】
反社条項を定める場合、反社会的勢力の範囲(人的属性と行為態様の2つの考慮要素を用いることが通常)、反社会的勢力に該当した場合の処理(無条件に解除可能、解除された側は損害賠償請求不可)を明記することが重要となります。上記サンプル条項では明記されていますが、時々見かけるものとして、反社会的勢力の範囲のみ定めていて、該当した場合の処理に関する規定が抜けていることがありますので、この点は注意が必要です。
上記以外に、委託者側特有の視点として、受託者が第三者に再委託することが予定されている場合、再委託先についても反社会的勢力ではないことを受託者に表明保証させること、及び委託者による再委託先の調査が必要となった場合、受託者に協力義務を定めておくことも検討に値します。
【受託者側視点】
反社会的勢力の範囲、反社会的勢力に該当した場合の処理については、委託者側視点で記載した内容がそのまま当てはまります。
受託者特有の視点としては、委託者が再委託先を指定した場合は表明保証義務及び調査協力義務を負担しないといった限定を付することがポイントとなります。また、受託者が委託者に対して納めた成果物につき、反社会的勢力に転売・再利用させないことを明記することも検討に値します。
8.当事務所でご対応できること
前述した通り、業務委託契約書は様々な契約類型が想定され、安易に雛形等に頼ると、取引実態を反映できておらず、後で全く役に立たない(場合によっては自社にとって厳しい内容となる)ということが起こりがちです。
当事務所では、まずは取引内容と条件をお伺いした上で、オーダーメイドで業務委託契約書を作成させていただきますので、是非ご利用ください。
<2022年11月執筆、2023年9月及び2024年2月追記>
※上記記載事項は弁護士湯原伸一の個人的見解をまとめたものです。今後の社会事情の変動や裁判所の判断などにより適宜見解を変更する場合がありますのでご注意下さい。
- 「中途解約で泣き寝入りしない!」WEB制作の未払い報酬を回収する方法
- 利用規約とは?作成・リーガルチェックのポイントについて弁護士が解説
- なぜテンプレートの利用規約はダメなのか?弁護士が教えるテンプレートの落とし穴
- 契約書のAIレビュー・チェックだけで万全!? 弁護士のリーガルチェックとの異同を解説
- アプリ事業者必見!スマホソフトウェア競争促進法で変わるスマホ市場の競争環境
- 知らないと危険!SNS運用代行で法的トラブルを防ぐ契約書のポイント
- サイバー攻撃による情報流出が起こった場合の、企業の法的責任と対処法とは?
- システム開発取引に伴い発生する権利は誰に帰属するのか
- 押さえておきたいフリーランス法と下請法・労働法との違いを解説
- システム開発の遅延に伴う責任はどのように決まるのか?IT業界に精通した弁護士が解説