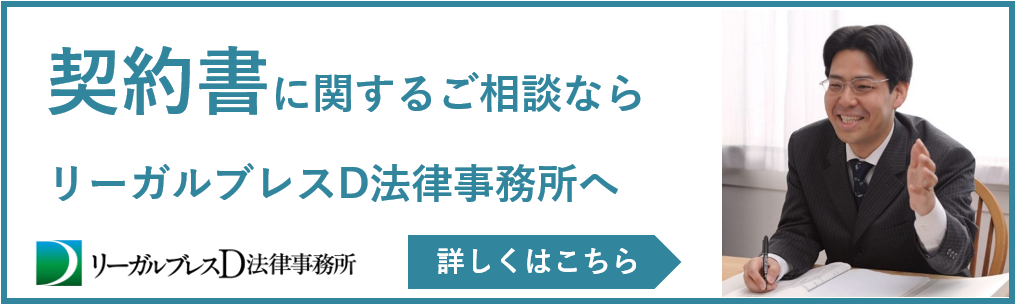契約書の「法的効力(法的拘束力)」とは何か?契約書の意義と機能につき解説
【ご相談内容】
大手企業と取引を開始するに当たり、かなり一方的な内容(当社にとって著しく不利な内容)の契約書の提示を受けました。
大手企業の営業担当者からは、「内容は厳しいことを書いてあるが、形式的に適用することはないので大丈夫」として、この内容のままサインするよう要請されています。
当該営業担当者の言葉を信じて契約書にサインしようと思うのですが、問題ないでしょうか。
【回答】
結論から申し上げると、大きな問題があると言わざるを得ません。
なぜなら、契約交渉時の説明内容と契約書に記載されている内容との矛盾・齟齬がある場合、よほどの特殊事情が無い限りは契約書に記載されている内容が優先され、その内容が法的に守らなければならない合意事項となるからです。すなわち、上記事例にある営業担当者の説明は、法的には何ら意味を有しないことになります。
現場実務では、取引先担当者から言質を取ったから大丈夫…と考える人が多いようですが、これは間違いと言わざるを得ませんので、十分注意してください。
【解説】
1.契約とは何か
(1)契約と法的拘束力
契約とは当事者間での合意・約束と定義づけられています。
これで一応意味は通じますが、より正確に定義するのであれば、一方当事者がその合意・約束を守らなかった場合、裁判所に対して救済を求めることができる合意・約束になります。具体的には、裁判を通じて、強制的に合意・約束を実行させる、又は合意・約束違反による損害賠償を支払わせることで契約違反に対する救済が実現されることになります。
要は、契約とは法律上の保護を受けることができる合意・約束であり、この法律上の保護が受けられることを「法的拘束力」があると言ったりします。
(2)法的拘束力の程度
この法的拘束力ですが、現場実務視点で検討する場合、“程度問題”があることを意識する必要があります。
すなわち、法的拘束力に差異が生じるものとして法律が明確に定めているものとして、書面によらない贈与は各当事者が解除できると定めている民法第550条があります。ちなみに、明文化されているのは贈与の場合だけですが、現場実務視点としては、対価性が無い契約あるいは実質的に無償に近い契約の場合、法的拘束力が弱まる可能性が高いことを押さえておく必要があります。
次に、事業者同士の契約であれば、契約内容に対する拘束力は強く、いくら不合理な契約内容であったとしても原則として契約内容を反故にすることはできません。一方、事業者と消費者間の契約の場合、消費者契約法等の法律による修正はもちろん、消費生活センター等の行政による指導を通じて契約内容の修正や不実行を余儀なくされることがあります。この意味で、契約当事者が事業者か消費者かによって法的拘束力の強弱が生じる場合があります。
さらに、契約当事者において情報・知識・経験・能力等の面で偏在や格差が生じている場合、要はプロフェッショナルとアマチュアとの契約の場合、契約を締結するに際しての説明義務及び情報提供義務を課すことで、契約の法的拘束力に差異を設けようとする裁判例が複数存在します(典型的には金融取引や投機的な保険、フランチャイズ契約など)。
2.契約書を作成する意義
契約は口頭でも成立する…という話はどこかで聞いたことがあるかと思います。たしかに、一定の例外(保証契約など)を除いて、口頭でも契約は成立します。しかし、契約書作成の重要性は強く指摘されています。
そこで、以下では契約書を作成する意義・目的について解説します。
(1)法律関係の明確化
契約を締結する場合、取引条件や支払い方法、万一の事態が発生した場合の対処法など様々な権利義務の発生・変更・消滅に関する取り決めが行われます。
これらの取り決めについて口頭でやり取りし、契約当事者双方の頭の中に記憶させておくという方法もできるのですが、時の経過とともに記憶が曖昧となったり、(悪意なく)記憶が書換えられたりすることは十分あり得る話です。このため、双方当事者の記憶が異なる場合、契約内容を巡る紛争が生じることになります。
そこで、権利義務の発生・変更・消滅に関する取り決めを契約書という書面(最近では電子上の記録媒体を用いることもありますが、本記事では媒体物に残すという意味でまとめて「書面」と呼びます)に明記することで、契約当事者の記憶の曖昧性・書換えを排除することが可能となります。
この意味で、契約書作成の意義は、法律関係の明確化を図ることがあげられます。
もっとも、この意義が達成されるのは、契約文言に不明確さが無く、疑義を挟む余地が無い場合です。
例えば、よくある例ですが、次のような秘密保持契約書を作成した場合、法律関係が明確化しないことになります。
| 秘密保持契約書
××(以下、甲という)と××(以下、乙という)とは、相互に開示される秘密情報の取り扱いについて覚書を取り交わすものとする。
第1条(定義) 本覚書において秘密保持の対象(以下「秘密情報」という)とは、甲又は乙が相手方に開示する次の各号に掲げる情報をいう。 (省略)
第2条(秘密の保持) 甲及び乙は、相手方から開示を受けた秘密情報を善良なる管理者の注意をもって管理するものとし、相手方の書面による事前の承諾を得ることなくその内容を第三者に開示又は漏洩してはならない。
第3条(目的外の使用禁止) 甲及び乙は、相手方の事前の書面による承諾を得ることなく、相手方から開示を受けた秘密情報を目的外で使用してはならない。 |
ここで注目して欲しいのは第3条です。一見すると当たり前のことを書いてあるように思われるかもしれませんが、「目的」とは何を指すのか契約書上に定義がありません。したがって、禁止される目的外使用が一義的ではなく、かえって様々な解釈が成立する点で法律関係の明確化を図ることができない状態となります。
このような“定義漏れ”以外にも、“用語の不統一”や“カタカナ(外来語)”は、しばしば複数の解釈論を生み出します。最終的には裁判所が、条項中の文言の文理、他の条項との整合性、契約締結に至る経緯等を双方的に考慮して判断することになりますが、裁判となると不確定要素が強くなり、契約書作成の意義が損なわれることにもなりかねません。
現場実務においては、契約書作成に際しては、その中身についても細心の注意を図りたいところです。
(2)最良の証拠確保
上記(1)でも触れた通り、口頭での契約を行った場合、どうしても契約当事者の記憶の曖昧性・書換え可能性等により、契約内容を巡っての紛争が起こりがちです。
しかし、契約内容を書面に残している場合、その契約書を確認さえすれば、どちらの言い分が正しいか一目瞭然となります。その意味で、契約書は自らの主張を裏付けるための最良の証拠になるという意義を有することになります。
そして、証拠として当事者双方の手元に残る以上、結果的に紛争の予防・抑止になると共に、万一紛争となった場合であっても紛争解決のための規範となることになります。
もっとも、最良の証拠として機能してしまうが故に、契約書に記載してある内容と現場実務の運用にズレが生じている場合、平常時においては見過ごされていても、何か事が生じた場合は直ちに契約違反の指摘を受けてしまうことになります。
例えば、委託者である甲と受託者である乙との間で制作物供給契約が締結されている場合において、甲が企画・デザイン・形状その他仕様等を細かく定め、その指示通りに乙は商品制作を行っているにもかかわらず、次のような条項が存在したとします。
| 乙は甲に対し、本件商品が知的財産権等の第三者の権利を侵害していないことを保証する。 |
第三者が本件商品外観に知的財産権侵害があると主張してきた場合、乙は甲の指示に基づいて商品制作を行っていたにすぎない以上、当該主張に対して責任を負うのは甲であるというのが一般的な感覚だと思います。
しかし、上記のような条項がある場合、形式論としては乙が全責任を負うと言わざるを得ません。また、上記のような一般的な感覚を主張したとしても、この条項を前提する限り、たしかに甲が指示している事情は認められるが、乙は当該指示内容につき知的財産権侵害の有無を調査する義務があったと解釈される可能性が高いと考えられます。
実情を踏まえて契約内容を見直さないことには、契約書の存在がかえって不利に作用することになることを押さえておく必要があります。
(3)合意内容の確定(固定)
契約締結に至るまで、当事者間では様々な条件交渉が行われることが多いと思いますが、その交渉時に提示されていた取引条件が契約書に反映されているのであれば、当然法的拘束力のある合意となります。
しかし、契約書に反映されていない場合、交渉時にいくら(仮)合意されていたとしても原則合意対象外と考えざるを得ません。
その意味で、契約書に反映されている内容が全てであり、反映されていない内容は契約内容ではないこと、すなわち、契約書は、当事者間で合意した内容を確定させると共に、流動的な合意内容を固定化させる意義を有することになります。
もっとも、一方では契約は口頭でも成立するというルールがある以上、実のところ、契約書に反映されていない内容は一切契約内容ではないと断定することが難しい場合があります。よくあるパターンとして、「担当者同士では、契約書にはこのように書いてあるけど、実際には適用しない」という約束があったという事例です。たしかに、本当に約束があったことを証明できるのであれば、契約書に反映されていない内容が、法的拘束力のある合意として取り込まれることになります。
ただ、このような契約書に反映されていない内容が法的拘束力を有するとなると、契約書に記載されていない背景事情や取引経過を探る必要があり、契約書だけから一義的に法律関係を判断することができず、何かと不都合です。
このような場合を考慮して、最近では完全合意条項と呼ばれる内容を契約書に盛り込むことが増加してきています。例えば、次のような条項です。
| 本契約は、本契約の対象事項に関する当事者間の完全な合意を示すものであり、本契約締結までに当事者間でなされたあらゆる合意(書面、口頭その他手段を問わない)はその効力を失う。 |
なお、完全合意条項を設ける場合、当然のことながら、自らにおいて合意したと認識している事項が全て契約書に反映されているのか確認する必要があります。
残念な事例として、完全合意条項を設けたがために、自らの首を絞めるという事態に陥ることを目にしますので、現場実務の担当者においては十分に注意をしたいところです。
3.契約による法的拘束力の限界
上記1.で記載した通り、契約が成立した場合、その合意内容は法的拘束力を有することになります。
しかし、合意があるとはいえ、法的拘束力を認めることが不適切な場合もあります。
ここでは、法的拘束力が認められない場合を解説します。
(1)当初より効力がないとされるもの
法律書を読むと「契約自由の原則」、「私的自治の原則」というキーワードが書いてあり、内容として、契約を締結するか否か、誰と契約するのか、契約内容をどのようにするのか等については、すべて当事者が自由に決めることができるとされています。
したがって、当事者間で合意がある以上、契約の法的拘束力は認めらえることが大原則なのですが、それでもなお法律により法的拘束力が否定されることあります。この点、民法第90条は次のように定めています。
| 公の秩序又は善良の風俗に反する法律行為は、無効とする。 |
いわゆる「公序良俗違反」と呼ばれるものです。
具体的にどういったものが公序良俗違反となるのか一義的に判断することは難しいのですが、裁判例を紐解くと、親子・夫婦間の同義など人倫に反する合意、犯罪等を勧誘するなど正義の観念に反する合意、暴利行為、個人の自由を極度に制限する合意、著しく射倖的な合意などが公序良俗違反により無効とされているようです。
何が公序良俗違反に該当するかは、現場実務担当者の判断だけでは難しいところがありますので、弁護士に相談したほうが良いと考えられます。
次に、公序良俗違反の一種にはなってしまうのですが、合意内容を全部無効とするのではなく、一定の場合につき無効と判断するという裁判例が数多く存在します。
例えば、事業者間での不動産賃貸借契約において、中途解約した場合の違約金につき契約残存期間分の賃料相当額と定めていた場合において、1年を超える部分は無効(=賃料12ヶ月相当分の違約金は有効)とした裁判例が存在します。また、不動産賃貸借契約において、1回でも賃料不払いがあった場合は契約解除可能という合意が行われていたとしても、1回程度の賃料不払いであれば信頼関係が破壊されたとは言えないとして、解除請求を認めないという裁判例が存在します。
要は裁判所が、合意内容を尊重しつつも、その適用場面を制限するという形で契約の法的拘束力を一部否定する、結果的に否定された部分については当初より法的効力を有していなかったと考えることになります。
現場実務において注意を要するのは、昨日までは有効と考えられていた契約内容が、ある日突然言い渡された裁判例により、その有効性に疑義が生じることがあるという点です。できる限り最新の裁判例まで把握し、その判断傾向を分析した上で契約内容を日々ブラッシュアップすることが望ましいのですが、一担当者では難しいと思われます。こういう時こそ、日々相談できる弁護士を準備したいところです。
(2)事後的に効力が失われるもの
一度契約をすれば、上記(1)のような例外が無い限り、契約の有効期間中その契約内容は当事者を拘束することになります。
しかし、契約締結後において生じた様々な変動により、当初の契約内容にて当事者を拘束することは不適切という場合もあり得る話です。
もちろん、契約締結当時において、ある程度の将来変動を予測した上で、適切なリスク判断を行い、契約内容に落とし込むことが理想です。また、法も基本的にはこの理想論に立っているため、契約締結後に生じた変動を根拠に契約の法的拘束力を失わせることを安易に認めていません。この問題は「契約を破る自由」はあるのかといった形で議論されることも多いのですが、理屈はともかく、現場実務において一応頭に入れておきたいポイントをあげておきます。
・事情変更の法理
これはどこかの法律に明文化されている概念でなく、法解釈論として考えられているものとなります。この事情変更の法理ですが、一般的には、契約締結後において、締結時に定めた契約内容通りの履行を当事者に強制することは著しく不公平であるという事由が生じた場合、契約の変更又は契約の解除が認められるとされる考え方です。
執筆者が知る限り、この事情変更の法理と呼ばれる考え方を真正面から取り上げて、契約内容の変更又は解除を認めた裁判例は存在しないようです。
したがって、今後裁判所で認められる可能性があるという点では、一応知っておいたほうが良いのですが、この事情変更の法理を唯一の拠り所として契約紛争に対処するというスタンスは取らない方がよいと考えられます。
・再交渉義務
上記のような事情変更の法理が一般的に認められにくいことを考慮して、将来的な事情変動があった場合は、当事者間で再度交渉を行うことを契約書上に定めるという対策が取られることがあります(念のための注意喚起ですが、契約書の最後の方に書いてある単なる「協議条項」とは異なります)。
ただ、あくまでも交渉のテーブルにつかせることに主眼がある条項であり、交渉したものの成果が上がらなかった場合にどのような効果が生じるのかについては、この再交渉義務を定めた条項から導かれるわけではありません。
せっかく再交渉義務を契約書に明記するのであれば、あわせて再交渉に応じなかった場合や再交渉により協議がまとまらなかった場合は契約を破棄できるといった効果論まで契約書に落とし込むことが、現場実務担当者の腕の見せ所と言えるかもしれません。
・不可抗力
これは多くの契約書で定められている条項であり、例えば次のようなものです。
| 天災、戦争、感染症の流行その他の不可抗力による本契約の不履行又は遅延について、当事者は責任を負わない。 |
当事者に責任が無い以上、当たり前のことと思われるかもしれません。
しかし、一度締結した契約内容の拘束力を喪失させるという意味では極めて特異な条項となります。このため、不可抗力に該当する事由について制限的に解釈する考え方が多いこと、したがって、現場実務担当者としては、何が不可抗力事由となるのか、できる限り具体的に明記するといった対応を行うことが望ましいと言えます(ちなみに、上記参考条項では「感染症の流行」と明記していますが、新型コロナ流行前まではこの文言が明記されていないことがむしろ一般的でした。このため、新型コロナの影響による様々な契約違反状態に対し、果たして不可抗力免責を主張できるのかという点は、現場実務では大論争となりました)。
・不安の抗弁
これも法律上の明文規定はなく、法解釈論として考えられているものとなります。不安の抗弁については、相手方の信用状態や契約履行能力に不安を抱いた当事者が、相手方に対し義務の履行を拒絶できるとする考え方と定義づけられることが多いようです。要は、契約締結後の相手方自身に関する事情変動によって、契約の拘束力に変更が生じると考えておけば十分かと思います。
ちなみに、事情変更の法理とは異なり、不安の抗弁を認めた裁判例はいくつか存在します。
したがって、契約問題へ対処する場合の1つの切り札として検討してよい考え方となります。しかし、
①相手方の財産状態が著しく悪化したことをどうやって裏付けるのか
②相手方が契約を履行しない恐れが高いことをどうやって裏付けるのか
という2点の適用が認められるためのハードルは決して低くはないことに注意が必要です。
4.専門家(弁護士)が契約書作成に関与する意義
契約を締結する場合、どのような取引条件にするのか、どのような懸念があるのか、どのような事項を要望したいのか等の実情を一番理解しているのは現場担当者です。したがって、現場担当者が契約書を作成することが望ましいといえます。
しかし、現場担当者が法的知識を十分に有しているとは限りません。法的知識に誤りや誤解があるまま契約書を作成してしまうと、気が付かない間にリスクを負担し、事が生じた場合に慌てふためくということもあり得る話です。
上記のような事態を回避することが、弁護士等の専門家に契約書作成に関与させる意義があると言えるのですが、それ以外にも次のようなことが考えられます。
(1)守られやすく、破られにくい契約条項を定めることができること
例えば、期限を表す契約上の言い回しとして、「直ちに」、「速やかに」、「遅滞なく」といった表現が契約書に用いられることが多いのですが、“いつまでのことを意味するのか”一義的に解釈することはできません。
このような場合に弁護士が契約書作成に関与することで、具体的な基準を明記する等の対処を行うことで、双方当事者にとって誤解を生まない“守られやすい”契約書の作成が可能となります。
また例えば、個人情報を取得し特定の目的に利用することへの同意を得る場合、様々な権利義務につき定められている契約書の一条項中にこっそり(?)定めているだけでは不十分とされることがあります。感覚的には契約書に署名押印をもらっている以上、契約内容につき了解を得ている、したがって、契約書のどこに書いていようと問題が無いのではと思われるかもしれません。しかし、個人情報の取得及び利用については個人情報保護委員会が定めるガイドラインが存在し、そのガイドラインを参照する限りは、上記のような取扱いは問題がある、すなわち個人情報の利用に関して無効と判断されるリスクが生じると考えられます。
弁護士が契約書作成に関与することで、上記のようなリスクを回避した、“破られにくい”契約書の作成が可能となります。
(2)現場担当者では気付かないリスクを想定し、紛争予防に資すること
弁護士は紛争案件を処理する専門家であるところ、どのような紛争が生じるのか、何故紛争が生じたのか、どのような解決処理の仕方があったのか等の経験と専門的知見を有しています。
弁護士が契約書作成に関与することで、その弁護士ならではの知見等により、現場担当者が気付かないリスクの発見とその予防を可能にする条項の作成や、リスクが顕在化した場合に最小限の被害で済むことを可能にする条項の作成などを提案し、契約書に落とし込むことができます。
(3)利益追求が可能となること
契約書を作成することで当事者間の権利義務が明確化することになりますが、この権利義務の中にはお金の動き(対価の支払い)が生じることが通常です。
財貨の移転が生じる以上、必ず税務問題が発生するのですが、例えば契約内容によっては課税を回避することができたりします。
税理士との共同作業となる場合が多くなりますが、弁護士が契約書作成に関与することで節税効果を得られる場合があり、経費削減=利益の増大を図ることができる場合があります。
なお、税務上の問題に限らず、例えば、対価を回収しやすい条項の作成などを提案するといったことも、弁護士なら可能です。
<2022年11月執筆>
※上記記載事項は弁護士湯原伸一の個人的見解をまとめたものです。今後の社会事情の変動や裁判所の判断などにより適宜見解を変更する場合がありますのでご注意下さい。
- その「免責条項」は本当に意味があるのか?契約リスクを左右する責任条項の考え方
- そのSLA、本当に機能していますか? 弁護士が教えるSLAの法的リスクと設計の勘所
- 契約書は誰が作成すべきか? 作成側・受領側が押さえたいポイントを弁護士が徹底解説!
- 偽装請負に該当するとどうなる? 契約形態・運用・制裁・是正策を弁護士が徹底解説
- IT取引の契約解消トラブル-無効・取消し・解除の実務対応
- 「中途解約で泣き寝入りしない!」WEB制作の未払い報酬を回収する方法
- 利用規約とは?作成・リーガルチェックのポイントについて弁護士が解説
- なぜテンプレートの利用規約はダメなのか?弁護士が教えるテンプレートの落とし穴
- 契約書のAIレビュー・チェックだけで万全!? 弁護士のリーガルチェックとの異同を解説
- アプリ事業者必見!スマホソフトウェア競争促進法で変わるスマホ市場の競争環境