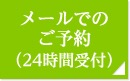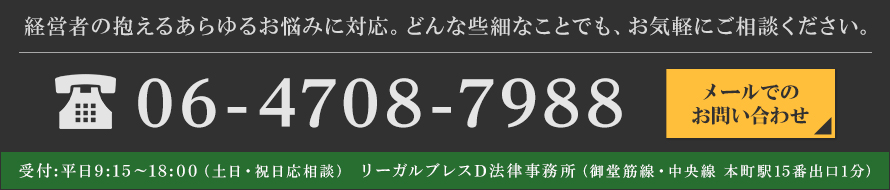景品表示法と表示・広告の関係について弁護士が解説!
景品表示法とは
一般的には景品表示法又は景表法と呼ばれることが多いのですが、正式名称は「不当景品及び不当表示防止法」です。
この正式名称からも分かる通り、景品表示法は「不当な景品」と「不当な表示」の制限・禁止という2つの類型を定めた法律となります。
2つの類型のうち広告表示に関するものは「不当な表示」となりますが、ここでは「不当な景品」について軽く触れておきます。
(1)不当な景品が制限・禁止される理由
事業者が過大な“おまけ”を謳い文句に宣伝広告した場合、消費者が商品やサービスを購入する際の判断を誤ってしまう恐れがあります。これを防止するために、景品表示法は、景品(おまけ)の上限額を設定し、その範囲内で宣伝広告するよう定めています。例えば、IT業界での景品規制であれば、コンプガチャが違法な景品提供に該当するといった事例などがあります。
具体的な規制内容は次の通りです。
①一般懸賞の場合
取引価格が5000円未満の場合、景品の最高額は取引価格の20倍まで、かつ景品の総額は売上予定総額の2%まで
取引価格が5000円以上の場合、景品の最高額は10万円まで、かつ景品の総額は売上予定総額の2%まで
②共同懸賞の場合
取引価格に関わらず、景品の最高額は30万円まで、かつ景品の総額は売上予定総額の3%まで
③総付景品の場合
取引価格が1000円未満の場合、景品の最高額は200円まで
取引価格が1000円以上の場合、景品の最高額は取引価格の20%まで
(2)不当な表示が制限・禁止される理由
実際よりも優良な品質である、又は実際よりも有利な価格であるといった宣伝広告がされた場合、消費者が商品やサービスを購入する際に判断を誤ってしまう恐れがあります。これを防止するために、優良誤認表示の禁止、有利誤認表示の禁止、指定告示による表示の禁止が定められています。例えば、IT業界での表示規制であれば、アフィリエイターやインフルエンサーを通じた広告配信に問題があった場合、広告主が景品表示法違反に基づく制裁を受けるといった事例などがあります。
具体的な規制内容は次で解説します。
景品表示法による表示規制
(1)不当な表示とは
景品表示法は「不当な表示」として、優良誤認表示、有利誤認表示、指定告示の3つを定めています。
①優良誤認表示
景品表示法第5条第1項第1号では、
「商品又は役務の品質、規格その他の内容について、一般消費者に対し、実際のものよりも著しく優良であると示し、又は事実に相違して当該事業者と同種若しくは類似の商品若しくは役務を供給している他の事業者に係るものよりも著しく優良であると示す表示であって、不当に顧客を誘引し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがあると認められるもの」
と定義されています。
端的に言えば、品質(内容)面を誇張し、消費者に誤解を与える宣伝広告と考えればイメージしやすいと思います。
具体的にどのような広告表示が優良誤認表示として取締り対象となっているのかについては、次の記事をご参照ください。
景品表示法に定める優良誤認表示とは何か? 具体例や考え方について解説
②有利誤認表示
景品表示法第5条第1項第2号では、
「商品又は役務の価格その他の取引条件について、実際のもの又は当該事業者と同種若しくは類似の商品若しくは役務を供給している他の事業者に係るものよりも取引の相手方に著しく有利であると一般消費者に誤認される表示であって、不当に顧客を誘引し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがあると認められるもの」
と定義されています。
優良誤認との相違点がやや分かりづらいかもしれませんが、優良誤認が品質(内容)面を誇張したものに対し、有利誤認は、価格面を誇張することで消費者に誤解を与える宣伝広告とイメージすれば区別しやすいと思います。
具体的にどのような広告表示が有利誤認表示として取締り対象となっているのかについては、次の記事をご参照ください。
景品表示法に定める有利誤認表示とは何か? 具体例や考え方について解説
③指定告示(内閣総理大臣が指定するその他の不当表示)
現時点で指定されているものは、次の7つになります。
・無果汁の清涼飲料水等についての表示
・商品の原産国に関する不当な表示
・消費者信用の融資費用に関する不当な表示
・不動産のおとり広告に関する表示
・おとり広告に関する表示
・有料老人ホームに関する不当な表示
・一般消費者が事業者の表示であることを判別することが困難である表示
ちなみに、業種を問わず意識すべき告示は、「おとり広告に関する表示」と「一般消費者が事業者の表示であることを判別することが困難である表示」となります。後者はいわゆるステルスマーケティング(ステマ)規制と呼ばれるものであり、後で解説します。おとり広告については、次の記事をご参照ください。
(2)景品表示法による規制対象とは
①景品表示法の規制対象となる事業者
自己の供給する商品・役務について、一般消費者向けに広告等の表示を行った者になります。
要は、法人化の有無、資本金や従業員数の大小、法人組織の形態の差異等を問わず、一般消費者向けに宣伝広告を行う全ての者が、景品表示法の規制対象になるということです。
②表示方法
結論から言いますと、一般消費者向けに行われた広告表示は全て対象になると考えて間違いありません。
ところで、景品表示法第2条第4項では、
「この法律で「表示」とは、顧客を誘引するための手段として、事業者が自己の供給する商品又は役務の内容又は取引条件その他これらの取引に関する事項について行う広告その他の表示であって、内閣総理大臣が指定するもの」
と定義されており、様々な広告手段の中でも一定範囲に絞られている(例外がある)と読めるような書きぶりとなっています。しかし、「不当景品類及び不当表示防止法第二条の規定により景品類及び表示を指定する件」という告示では、
・商品、容器又は包装による広告その他の表示及びこれらに添付した物による広告その他の表示
・見本、チラシ、パンフレット、説明書面その他これらに類似する物による広告その他の表示(ダイレクトメール、ファクシミリ等によるものを含む。)及び口頭による広告その他の表示(電話によるものを含む。)
・ポスター、看板(プラカード及び建物又は電車、自動車等に記載されたものを含む。)、ネオン・サイン、アドバルーン、その他これらに類似する物による広告及び陳列物又は実演による広告
・新聞紙、雑誌その他の出版物、放送(有線電気通信設備又は拡声機による放送を含む。)、映写、演劇又は電光による広告
・情報処理の用に供する機器による広告その他の表示(インターネット、パソコン通信等によるものを含む。)
が含まれるとされており、現時点で考え得るすべての広告手段をカバーするような形になっています。
したがって、景品表示法上の「表示」に該当しないから、景品表示法の規制対象ではない…といった発想を持つべきではありません。
ステルスマーケティング規制の追加について
前述した指定告示のうち、「一般消費者が事業者の表示であることを判別することが困難である表示」というタイトルが付されているものがステルスマーケティング規制と呼ばれ、令和5年10月1日より施行されています。
ところで、世間一般で言われている(非難・炎上対象となりやすい)ステマよりは、やや対象範囲が限定されており、
「事業者が自己の供給する商品又は役務の取引について行う表示であるにもかかわらず、事業者の表示であることを明瞭にしないことなどにより、一般消費者が事業者の表示であることを判別することが困難となる表示」
が景品表示法の規制対象となります。
ポイントは、次の2点です。
①事業者が自己の供給する商品又は役務の取引について行う表示であること
②一般消費者が事業者の表示であることを判別することが困難であること
まず①ですが、事業者がインフルエンサー等に対し、自社の商品やサービスを宣伝広告するよう依頼し、インフルエンサー等が依頼を受けたことを隠して、あたかも偶然を装ってその管理するSNS等に好意的なレビューを投稿した場合などが典型例です。逆に言えば、インフルエンサー等が事業者からの依頼もなく、たまたま利用して好意的なレビューを投稿したにすぎない場合は、景品表示法に基づくステマ規制に該当しません。
現場実務で悩ましいのは、事業者の依頼に基づく投稿とはどこまでのことを指すのか、すなわちインフルエンサー等が発信する表示内容の決定につき、何をすれば事業者が関与したといえるのかの線引きです。
この点、消費者庁が公表しているガイドライン(「一般消費者が事業者の表示であることを判別することが困難である表示」の運用基準)では、
「事業者と第三者との間の具体的なやり取りの態様や内容(例えば、メール、口頭、送付状等の内容)、事業者が第三者の表示に対して提供する対価の内容、その主な提供理由(例えば、宣伝する目的であるかどうか。)、事業者と第三者の関係性の状況(例えば、過去に事業者が第三者の表示に対して対価を提供していた関係性がある場合に、その関係性がどの程度続いていたのか、今後、第三者の表示に対して対価を提供する関係性がどの程度続くのか。)等の実態も踏まえて総合的に考慮し判断する」
と記述されていますが、具体性を欠くものと言わざるを得ません。
今後の推移を見守りながら線引きを考えるほかありませんが、現状では保守的な考え方である、有償無償を問わないことはもちろん、明確な依頼や直接間接の有無を問わず、事業者とインフルエンサー等との間に何らかの接触が認められる場合は、景品表示法に基づくステマ規制に該当する恐れありと考えたほうが無難かもしれません。
次に②ですが、消費者庁が公表しているガイドラインでは、
「一般消費者にとって事業者の表示であることが明瞭となっているかどうか、逆にいえば、第三者の表示であると一般消費者に誤認されないかどうかを表示内容全体から判断する」
と記述されています。
現場実務では、景品表示法に基づくステマ規制に該当しないよう、インフルエンサー等が投稿するレビュー等に「PR」「広告」「宣伝」「プロモーション」などと表示させることが重要となります。なお、当該表示を分かりづらくするといった小細工が許されないことは当然です。
景品表示法違反をした場合の制裁・罰則
事業者が不当な表示を行った場合、行政処分として「措置命令」を受けることになります。
具体的には、一般消費者に与えた誤認の排除、再発防止策の実施、今後同様の違反行為を行わないことなどが命じられます。措置命令に違反した場合は刑事罰を受けます。
なお、不当な表示とまでは断定できない場合であっても、不当な表示の恐れありと監督官庁が判断した場合は、指導措置を受けることがあります。
また、優良誤認表示と有利誤認表示に該当する場合、事業者は「課徴金納付命令」を受けることになります。
一種の罰金のようなものですが、原則として売上額の3%の支払いを命じられるため、事業者の負担は重いものとなります。なお、課徴金納付命令の詳細については、次の記事をご参照ください。
景表法における課徴金制度とは?予防策から対処法までそのポイントを解説
さらに、優良誤認表示と有利誤認表示に該当する場合、「刑事罰」を受けることもあります(景品表示法第48条)。
事業者が実施すべき景品表示法対策のポイント
事業者が景品表示法を遵守するためには、地道な対策を継続することが必要不可欠となります。
(1)優良誤認表示の場合
次の3点を意識することが重要です。
①表示から受ける一般消費者の認識を正しく把握する
②実際の商品等の内容を正確に認識する
③この2点を比較検討し、差異の有無及び程度を考察する
まず①ですが、事業者内部だけでは判断が偏りがちですので、できる限り弁護士等の第三者の見解を仰ぐことが望ましいといえます。
特に、業界常識にとらわれず、デメリットにつき不表示とすることで誤解を招かないか、打消し表示の記載場所・配置等が適切かは意識したいところです。
次に②ですが、記載されていることを形式的に抽出し、意味内容を確定させることが重要です。事業者による恣意的な希望的解釈を排除するためにも、やはり弁護士等の第三者の見解を仰ぎたいところです。
なお、不実証広告規制対策の意味も込めて、表示の裏付けとなる客観的かつ合理的な根拠資料を準備することも肝要です。
最後に③ですが、これも事業者だけでは判断しきれないところがありますので、公正競争規約や監督官庁のガイドラインがあれば、それを参照することが必須となります。また、消費者庁が公表している違反事例を確認し、類似事例を分析することも有用です。
(2)有利誤認表示の場合
優良誤認表示と比較した場合、有利誤認表示は一義的に決まり、客観的に判断可能であることを踏まえ、次の事項を意識したいところです。
まず、多くの事例で、事業者は内心「消費者は誤解するかもしれない」と分かっていながら、広告表示するようです。したがって、誘惑に負けないという事業者の決意が何より重要となります。
次に、違反の有無を形式的に審査することが可能である以上、社内での継続的な検証を怠らないことが重要となります。
さらに、過去の処分事例などを参照し、違法性を有する広告表示とは何かを常に情報収集することが重要となります。
弁護士に相談するメリット
事業者の皆様が景品表示法に関する課題を弁護士に相談することは、法令遵守を確実にし、企業の信頼性やブランド価値を守る上で極めて重要です。
具体的なメリットは次の通りです。
①リスクの早期発見と未然防止
景品表示法違反は、企業の信用失墜や多額の金銭負担(課徴金の支払いなど)に繋がります。
弁護士に相談することで、広告やキャンペーンの内容が法に抵触していないかを事前に確認でき、リスクを未然に防ぐことができます。
②法改正への迅速な対応
景品表示法は時代の変化に応じて改正されることがあり、法解釈も変化します。
弁護士は最新の法改正や判例に精通しており、企業が常に適切な対応を取れるようアドバイスします。
③競争優位性の確保
合法的かつ効果的なプロモーション戦略を設計することは、競争市場での優位性を高める鍵です。
弁護士の助言を受けることで、景品表示法の範囲内でクリエイティブかつ差別化されたマーケティングを実現できます。
④トラブル発生時の迅速な対応
万が一行政指導や消費者からのクレームが発生した場合、弁護士が早期に適切な対応策を講じることで、事態の拡大を防ぎます。
これにより企業のイメージダウンを最小限に抑えられます。
⑤社員教育によるコンプライアンス意識の向上
弁護士による研修やアドバイスを通じて、社員一人ひとりが景品表示法の基本を理解し、遵守できるようになります。
これにより、組織全体のコンプライアンスレベルが向上します。
消費者の法意識が高まる現代では、些細な表示ミスが炎上に繋がるリスクも増しています。また、SNSや口コミの拡散力により、問題が公になるスピードは従来よりも格段に早いです。このような背景から、適切な法的助言を受け、信頼される企業活動を行うことが求められています。
企業活動を成功に導くための重要なパートナーとして、ぜひ当事務所の弁護士をご活用ください。
当事務所でサポートできること
当事務所は、複数の広告代理店の顧問弁護士として、あるいはインターネット等で積極的に広告展開する通販事業者の顧問弁護士として、景品表示法を含む広告表示規制につきご相談を受け、対処法のご提案や関係各機関との折衝などの対応実績が多数あります。このため、実例を踏まえた数々の知見とノウハウを蓄積していますので、ご相談者様には経験に裏付けられたアドバイスをご提供することが可能です。
そして上記に加え、当事務所はさらに次のような特徴を有しています。
①専門知識に基づく理解
当事務所の代表弁護士は情報処理技術者資格を保有し、インターネット広告に関する専門用語を把握しています。このため、相談しても弁護士が理解できない・理解するまで時間がかかるといった問題が生じません。
②カスタマイズされたサポート
企業の規模や業種に応じた法的サポートを提供し、それぞれのニーズに合わせた柔軟な対応が可能です。
③早期解決を目指す交渉力
トラブルが発生した場合、法廷外での早期解決を目指した交渉に尽力します。
景品表示法などの法規制を意識しながら、訴求力を最大化する広告表示の実現に向け、当事務所の弁護士が全力でサポートします。
広告表示に関するお困り事や悩み事があれば、是非当事務所までご相談ください。
<2024年12月執筆>
※上記記載事項は弁護士湯原伸一の個人的見解をまとめたものです。今後の社会事情の変動や裁判所の判断などにより適宜見解を変更する場合がありますのでご注意下さい。