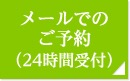IT企業に必要な契約書とは?弁護士が解説
Contents
- IT企業にとって契約書が必要な理由
- ①契約内容の明確化(認識のズレを防ぐ)
- ②法的トラブル・紛争の防止
- ③IT特有の法規制に対応するため
- ④取引先との信頼関係を強化
- ⑤事業成長に伴うリスク管理
- IT企業が手元に置いておきたい契約書とは
- 1.秘密保持契約書
- 2.PoC(技術検証・実証実験)契約書
- 3.業務委託契約書
- 4.フリーランスとの業務委託契約書
- 5.著作物制作契約書・著作物譲渡契約書・著作権ライセンス契約書
- 6.プライバシーポリシー
- システム開発企業が手元に置いておきたい契約書とは
- 1.システム開発契約書
- 2.システム保守運用契約書
- SES企業が手元に置いておきたい契約書とは
- 1.SES契約書
- 2.準委任契約書
- アプリ開発・アプリ提供企業が手元に置いておきたい契約書とは
- 1.アプリ利用規約
- 2.アプリ(ソフトウェア)ライセンス契約書
- 3.データ提供契約
- デジタルコンテンツ制作企業が手元に置いておきたい契約書とは
- デジタルコンテンツ制作契約書
- WEB制作・WEBマーケティング企業が手元に置いておきたい契約書とは
- 1.WEB制作契約書、WEB保守運用契約書、WEB広告運用代行契約書
- 2.SNS運用代行契約書
- ネット通販企業が手元に置いておきたい契約書とは
- 通販利用規約
- IT企業が弁護士に契約書作成・リーガルチェックを依頼するメリット
- ①リスク回避とトラブル防止
- ②IT業界特有の法律に対応
- ③取引先との信頼向上
- ④事業スピードの向上
- ⑤カスタマイズされた契約書を作成可能
- 当事務所でサポートできること
IT企業にとって契約書が必要な理由
IT企業は、システム開発、ソフトウェア(アプリケーション)提供、データ管理、ネット通販など、多様なビジネスを展開しています。しかし、これらのビジネスを包摂するような法律は存在しません。
この点を踏まえると、企業・経営者が取るべき選択肢は、自らが積極的に動き、法律の保護を受けられるよう対策を講じることになります。
この対策の根幹となるのが契約書の作成です。取引先や顧客との合意内容を明確化しておけば、法は双方の当事者に対し、その合意内容を遵守することを求めます。これにより、IT企業は、利益の確保やリスク回避を実現することが可能となります。
契約書を作成することで得られるメリットは、次の5点を挙げることができます。
①契約内容の明確化(認識のズレを防ぐ)
トラブルは当事者間での認識の相違に起因します。例えば、システム開発の納期や仕様について口頭のみのやり取りとなった場合、後からそのやり取りを見返すことができず、合意があったのか確認できないことがあります。
しかし、契約書があれば、納期・仕様・報酬などの合意内容が明確化されますので、言った言わない論争を防止することができ、スムーズに業務遂行できるといったメリットを享受することが可能となります。
②法的トラブル・紛争の防止
契約書がない状態で取引を行った場合、トラブル発生時の対処が困難になります。例えば、どちらが成果物(ソフトウェアなど)の権利を持つかで紛争に発展した場合、主張・反論の応酬となり、今後の取引にも悪影響を及ぼしかねません。
しかし、契約書があれば、著作権その他知的財産権の帰属などの合意内容が明確化されますので、そもそも紛争になりえず、良好な取引関係を継続できるといったメリットを享受することが可能となります。
③IT特有の法規制に対応するため
IT業界には特有の法律や規制が数多くあります。例えば、発注内容の書面交付義務を定める下請法やフリーランス法などに違反していた場合、監督官庁より指導を受けると共に違反企業として世間に公開され、自社のレピュテーションを大きく損なう事態に発展することもあり得ます。
しかし、契約書があれば、適切な文言を入れることでコンプライアンスを確保し、法規制を遵守していることの証拠を確保できるといったメリットを享受することが可能となります。
④取引先との信頼関係を強化
取引を開始するに当たり、契約書を提示できないことで取引先の心証を悪くすることがあります。例えば、IT業界ではスタートアップやベンチャーといった社歴が短い企業が多いためか、適切に取引条件を実行してくれるのか不信感を持つ取引先が多いという実情があります。
しかし、契約書があれば、適切に取引を遂行することを表明する証となりますので、取引先の不安要素を解消するといったメリットを享受することが可能となります。
⑤事業成長に伴うリスク管理
事業が順調に推移し取引規模が大きくなると、比例して契約リスクも増大することになります。例えば、従来の中小企業との取引であれば多少のミスがあっても人間関係でリカバリーができたものの、大手企業との取引でのミスはビジネスライクの判断となり、金銭賠償の要求を受けるなどして、一気に事業存続危機に発展することもあったりします。
しかし、契約書があれば、将来のリスクを想定した取引条件の設定ができますので、事業継続の可能性を高めるといったメリットを享受することが可能となります。
IT企業が手元に置いておきたい契約書とは
一口にIT企業といっても、システム開発、ソフトウェア(アプリケーション)提供、データ管理、ネット通販など多種多様なビジネスがあり、ビジネスごとで保持しておきたい契約書は異なってきます。
本記事では、まずは業態を問わずIT企業であれば手元に置いておきたい契約書とその契約書に関する解説記事を紹介します。なお、本記事後半では、個別業態ごとに必要となる契約書の紹介と解説記事を紹介しています。
ちなみに、IT企業が契約書を作成・確認する際、契約の標題や名称、契約当事者の正しい特定、基本契約と個別契約の関係など、そもそも論のところで意外と見落としがちなポイントがあります。
次の記事では、契約書の法的効力に影響を与える重要事項を解説し、紛争を未然に防ぐために注意したい事項を解説しています。契約リスクを回避し、スムーズな取引を実現するために、ぜひご覧ください。
1.秘密保持契約書
IT企業が新たな取引を開始する際、秘密保持契約(NDA)の締結は重要です。
しかし、例えば、秘密情報の定義が曖昧だと、保護すべき情報が適切に守られず、リスクが生じる可能性があります。
次の記事では、秘密情報の範囲設定、開示・利用制限、権利処理、契約期間の適切な設定方法など、NDAの実務上のチェックポイントを詳しく解説。契約締結時の注意点を押さえ、自社の機密情報を適切に守るために、ぜひご覧ください。
2.PoC(技術検証・実証実験)契約書
IT企業が新技術を開発し、これに興味を示した取引先が試験導入する際に締結されるのがPoC(技術検証・実証実験)契約です。
もっとも、目的が曖昧なまま締結すると、技術の持ち逃げや成果物の権利を巡るトラブルが発生するリスクがあります。
次の記事では、経産省のモデル契約をもとに、PoC契約の目的設定、技術検証の範囲、知的財産権の帰属、対価の設定、秘密保持条項など、実務で押さえるべきポイントを解説しています。自社技術を守りながら円滑に契約を進めるためのヒントがありますので、ぜひご覧ください。
3.業務委託契約書
おそらくIT企業が取引先と締結することが一番多い契約類型と思われます。
IT企業が業務委託契約を締結するに当たり、契約内容を適切に整理し、リスクを回避できるよう、次の記事では、業務委託契約の基本から、報酬や費用負担、契約解除時の清算、契約不適合責任、損害賠償など、特に注意すべき条項について詳しく解説しています。
適切な契約書を作成し、円滑な取引を進めるために、ぜひご覧ください。
4.フリーランスとの業務委託契約書
上記3.で紹介した業務委託契約書のうち、取引先がフリーランスに該当する場合、「フリーランス新法」(正式名称:特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律)に従う必要があります。
次の記事では、法律の適用範囲、企業側が遵守すべき取引条件の明示義務、支払期限のルール、禁止行為(買いたたき・受領拒否など)、契約書作成時の注意点を解説しています。
フリーランスとの取引適正化とコンプライアンス対応のために、ぜひご覧ください。
フリーランス新法のポイントと業務委託契約書の見直しについて解説
5.著作物制作契約書・著作物譲渡契約書・著作権ライセンス契約書
IT企業が事業活動を行う上で、ソフトウェアやコンテンツなどに発生する著作権の処理が重要なものとなります。
次の記事では、著作物の定義や著作権の範囲、ライセンス契約や譲渡契約のポイントを詳しく解説しています。特に、業務委託での著作権の帰属、プログラムの著作権の取り扱い、ライセンス契約の適切な締結方法など、実務に役立つ情報にも触れています。
契約トラブルを防ぎ、自社の権利を適切に守るための知識を身につけるためにも、ぜひご覧ください。
著作権に関する契約(利用許諾・ライセンス、譲渡、制作)のポイントについて解説
6.プライバシーポリシー
IT企業は個人情報を取扱うことが多く、顧客等より個人情報の管理体制に厳しい目が向けられています。
次の記事では、企業が公表すべき情報、取得した個人情報の適切な管理、安全対策、開示請求への対応、外国へのデータ移転規制など、実務に役立つポイントを詳しく解説しています。
個人情報の適正管理とコンプライアンス対応を強化し、トラブルを防ぐべく、自社のプライバシーポリシーの適正化を図るためにも、ぜひご覧ください。
プライバシーポリシー作成に際して注意するべき事項につき、弁護士が解説!
システム開発企業が手元に置いておきたい契約書とは
1.システム開発契約書
IT企業にとって、システム開発契約は事業の根幹を支える重要な取り決めです。しかし、契約の不備や認識の齟齬が原因でトラブルに発展するケースも少なくありません。例えば、「どこまでの業務を含むのか」「追加対応はどのように扱われるのか」といった点が曖昧だと、後々の紛争につながる可能性があります。
次の記事では、システム開発契約においてよく見られる条項を解説し、契約書作成・チェック時に注意すべきポイントを詳しく説明しています。IT企業の皆様がスムーズな開発プロジェクトを実現するべく、ぜひご覧ください。
ちなみに、上記記事は個々の条項ごとに詳細な解説を行っていますが、ざっくり要点だけを押さえたい場合は、次の記事をぜひご覧ください。
開発者・ベンダーが検討するべきシステム開発契約書のポイントを弁護士が解説!
なお、システム開発の現場では、多段階契約と一括契約のどちらを選択するべきなのかという悩みも多いようです。
多段階契約と一括契約の違いや、それぞれのメリット・デメリット、案件の特性に応じた適切な契約選択のポイントについては、次の記事をぜひご覧ください。
システム開発契約における多段階契約・一括契約の選択ポイント等を解説
2.システム保守運用契約書
保守運用事業を行う中で、想定外の追加対応や契約の範囲を超えた業務を無償で求められることはないでしょうか。保守契約の内容が曖昧だと、ユーザとの認識の違いからトラブルに発展しやすく、収益を確保するどころか負担が増えてしまうリスクもあります。
次の記事では、システム保守運用契約について、業務範囲の明確化、緊急対応の取り決め、追加作業の費用請求など、トラブルになりやすい点を中心に適切な契約設計ができるポイントを紹介していますので、ぜひご覧ください。
システム保守契約・運用契約書作成に際し、特に意識したい条項について解説
SES企業が手元に置いておきたい契約書とは
1.SES契約書
SES契約は、エンジニアを提供することで開発・運用を支援する重要な契約形態ですが、適切に管理しなければ、想定外の業務負担や契約リスクを抱えることになりかねません。特に、業務範囲の曖昧さ、指揮命令権の取り扱い、報酬の算定方法、知的財産権の帰属など、契約内容によっては後々のトラブルにつながる可能性があります。
次の記事では、SES契約の基本的な仕組みを整理し、派遣契約や請負契約との違い、契約書に明記すべきポイント、偽装請負を回避するための実務的対策について詳しく解説しています。
SES契約を適正に運用し、エンジニアリソースを有効活用するために、ぜひご覧ください。
SES契約を検討する上でのポイントをSES事業者の視点で解説
2.準委任契約書
SES契約の法的性質は、準委任契約といわれています。
請負契約や派遣契約と異なり、業務の成果物ではなく作業自体に対して報酬が支払われるという特性が十分に浸透していないためか、契約上のトラブルに発展することが多い契約類型です。
次の記事では、準委任契約の基本的な仕組み、請負・派遣契約との違い、中途解約時のリスク、報酬の算定方法、印紙税の適用など、実務上押さえておくべきポイントを詳しく解説します。
適切な契約管理を行い、予期せぬ業務負担や法的リスクを回避するために、ぜひご覧ください。
準委任契約(業務委託契約)とは何か? 契約書作成時の注意点と共に解説
アプリ開発・アプリ提供企業が手元に置いておきたい契約書とは
アプリ開発に関する契約書については、システム開発契約書の解説が当てはまりますので、「システム開発企業が手元に置いておきたい契約書」をご参照ください。
開発以外の契約書については、以下の通りです。
1.アプリ利用規約
アプリを提供する際、利用規約の整備は欠かせません。ユーザとの契約関係を明確にし、責任範囲の限定、データの取り扱い、サービス変更時の対応などを適切に定めることで、不要なトラブルを防ぐことができます。しかし、規約の内容が不十分、あるいは事業の実態に合っていないと、予期せぬリスクを招く可能性もあります。
次の記事では、アプリ開発者が利用規約を作成・運用する際に押さえるべきポイントや、利用規約に含めるべき条項、事業内容に応じた適切な設計方法について分かりやすく解説しています。
安心してアプリサービスを提供するために、ぜひご覧ください。
アプリリリース時に必要となる利用規約の条項例について、弁護士が解説!
2.アプリ(ソフトウェア)ライセンス契約書
クラウドサービス(SaaS、ASP)を提供する際、適切なライセンス契約を締結しなければ、想定外のトラブルや権利関係の不備、支払い遅延などのリスクを抱えることになります。特に、ライセンスの範囲、ユーザの義務、ID・パスワードの管理、禁止事項、責任制限条項などを適切に定めておくことが重要です。
次の記事では、クラウド型を念頭に、ライセンサー側が注意すべき契約条項のポイントを詳しく解説しています。ユーザとの不要なトラブルを回避し、適切に権利を保護しながらサービスを提供するために、ぜひご覧ください。
ソフトウェア使用許諾(ライセンス)契約書作成のポイントについて解説
3.データ提供契約
データを提供・受領する契約では、権利関係や利用範囲を明確にしておかないと、契約トラブルや想定外のリスクを抱えることになります。データ提供契約には譲渡、ライセンス、共同利用といった異なる形態があり、それぞれ契約上の注意点が異なります。
次の記事では、データ提供契約の基本から、ライセンス契約を中心とした実務上の留意点と共に、データの利用範囲、派生データの権利帰属、契約終了後の取扱いなど、契約締結時に押さえておくべきポイントを整理しました。
データ取引の適正な契約管理のために、ぜひご覧ください。
デジタルコンテンツ制作企業が手元に置いておきたい契約書とは
デジタルコンテンツ制作契約書
コンテンツ制作を受託する際、契約内容によっては成果物の著作権がすべて譲渡対象となる、追加作業が無償で求められるといったトラブルに直面することがあります。特に、知的財産権の帰属や修正対応の範囲が曖昧なまま契約を結ぶと、後々の活用が制限される可能性もあります。
次の記事では、制作者側が契約締結前に確認すべき重要ポイントを解説しています。著作権をどこまで保持できるのか、追加作業や修正対応の範囲を明確にする方法、適正な報酬の確保につながる契約交渉のコツなど、実務に役立つ情報を詳しく紹介します。
自分のクリエイティブを守りながら、適正な条件でコンテンツを制作するために、ぜひご覧ください。
コンテンツ制作契約を進める場合の注意点とは?IT業界に精通した弁護士が解説
WEB制作・WEBマーケティング企業が手元に置いておきたい契約書とは
1.WEB制作契約書、WEB保守運用契約書、WEB広告運用代行契約書
WEBサイト制作(更新)、WEBサイトの保守運用、WEB広告運用代行業務を受託する際、契約内容を適切に定めていないと、想定外のトラブルや追加費用が発生することがあります。特に、権利関係の整理、業務範囲の明確化、契約不適合責任の取り扱いなどは、後々のリスクを回避するために慎重に確認すべきポイントです。
次の記事では、WEBサイトに関連する業務を受託するに際して重要な契約条項を解説し、注意するべき事項を整理しました。適正な契約を結び、安全かつ円滑にサイト運用を進めるために、ぜひご覧ください。
Web制作(更新)、保守運用、広告運用代行に関連する契約書作成のポイントを解説
2.SNS運用代行契約書
SNS運用代行を受託する際、契約内容が不明確だと追加業務の負担増や報酬未払いのリスクに直面することになります。特に、業務範囲の曖昧さや免責条項の不備が原因で、トラブルが発生するケースは少なくありません。
次の記事では、SNS運用代行契約において受託者が注意すべき契約内容、特に業務内容の明確化、免責・非保証条項の工夫、著作権の帰属、契約終了時の対応など、適正な契約を結ぶための実務的なポイントを紹介します。
適切な契約でリスクを回避し、安心してSNS運用代行を行うために、ぜひご覧ください。
知らないと危険!SNS運用代行で法的トラブルを防ぐ契約書のポイント
ネット通販企業が手元に置いておきたい契約書とは
通販利用規約
通販事業を行う上で、利用規約の適切な整備は不可欠です。契約条件が曖昧だと、注文キャンセルのトラブルや返品対応の混乱、損害賠償請求のリスクにつながる可能性があります。また、2020年の民法改正により、定型約款のルールが適用されるようになり、規約の運用に注意が必要になっています。
次の記事では、通販サイトの運営者が利用規約を作成・更新する際に押さえるべき重要ポイントと共に、契約の成立要件、返品・キャンセルの取り扱い、消費者契約法への対応など、トラブルを未然に防ぐための実務的な対策を詳しく紹介しています。
安心して通販ビジネスを運営するために、ぜひご覧ください。
ネット通販事業者が利用規約・約款を作成するための法的ポイントを弁護士が解説!
IT企業が弁護士に契約書作成・リーガルチェックを依頼するメリット
IT企業は、技術革新のスピードが速く、取引の種類も多様です。そのため、契約書の内容に不備があると、法的リスクやビジネス上のトラブルにつながる可能性があります。
弁護士に契約書の作成やリーガルチェックを依頼することで、以下のようなメリットが得られます。
①リスク回避とトラブル防止
契約書の文言が曖昧、抜け漏れがあると、紛争が発生した際に不利になる可能性があります。弁護士がリーガルチェックを行うことで、契約リスクを事前に排除できます。
また、事前に適切な契約を整備することで、訴訟リスクを最小限に抑えられます。
②IT業界特有の法律に対応
ITビジネスは、他の業界に比べて知的財産権、個人情報保護法、下請法、独占禁止法など、特有の法律が多く関わります。
例えば、システム開発契約やアプリ開発契約では、著作権の帰属が曖昧であることに起因して、後に知財トラブルに発展することがあります。弁護士が適切な条項を盛り込むことで、貴社の権利を確実に保護できます。
また、個人情報保護法など、データの取り扱いに関する法律は厳格です。弁護士が最新の法改正に対応した契約書を作成し、コンプライアンスリスクを軽減します。
③取引先との信頼向上
契約書がしっかり整備されている企業は、取引先からの信頼も高まります。特にスタートアップやベンチャー企業にとっては、法的に適正な契約を交わすことで、投資家やパートナー企業との関係構築にもプラスになります。
④事業スピードの向上
弁護士があらかじめリスクのない契約書を作成しておけば、取引先との交渉がスムーズになり、契約締結までの時間を短縮できます。
また、法務部門を持たないスタートアップや中小企業でも、外部の弁護士を活用することで、法務の負担を軽減できます。
⑤カスタマイズされた契約書を作成可能
ネット上で無料のテンプレートが入手できますが、ビジネスの実態に合っていない、重要な条項が抜けていることがあります。弁護士に依頼すれば、貴社の事業に最適な契約書をオーダーメイドで作成できます。
当事務所でサポートできること
当事務所はIT企業へのサポートを重視しており、顧問弁護士としてお取引のある企業のうち約3分の1がIT企業となります。
このため、多種多様な相談実例を踏まえた数々の知見とノウハウを蓄積していますので、IT企業の皆様には経験に裏付けられたアドバイスをご提供することが可能です。
そして上記に加え、当事務所はさらに次のような特徴を有しています。
①専門知識に基づく理解:当事務所の代表弁護士は情報処理技術者資格を保有し、IT企業が必要とする契約書の内容はもちろん、そこに潜むIT独特の技術リスク等を把握しています。このため、相談しても弁護士が理解できない・理解するまで時間がかかるといった問題が生じません。
②カスタマイズされたサポート:企業の規模や業種に応じた法的サポートを提供し、それぞれのニーズに合わせた柔軟な対応が可能です。
③早期解決を目指す交渉力:トラブルが発生した場合、法廷外での早期解決を目指した交渉に尽力します。
弁護士に契約書の作成やリーガルチェックを依頼することで、IT企業は本業に集中することができます。
法的リスクを回避し、スムーズな事業運営が可能になります。貴社の成長を法的側面からサポートいたしますので、ぜひリーガルブレスD法律事務所までご相談ください。
- IT企業に必要な契約書とは?弁護士が解説
- 商用利用は大丈夫? ChatGPTと切っても切れない著作権の関係について解説
- システム開発取引に伴い発生する権利は誰に帰属するのか
- IT企業特有の民事訴訟類型と知っておきたい訴訟対応上の知識
- ホームページ、WEBサイトに関する著作権の問題について解説
- メタバースをビジネス・事業で活用する上で知っておくべき著作権の問題
- 画面表示(UI)は著作権その他法律の保護対象になるのか?
- 令和5年改正不正競争防止法のポイントを解説
- オープンソースソフトウェア(OSS)利用時に注意すべき事項について(法務視点)
- ソフトウェア・エスクロウとは何か? 活用場面とポイントを解説