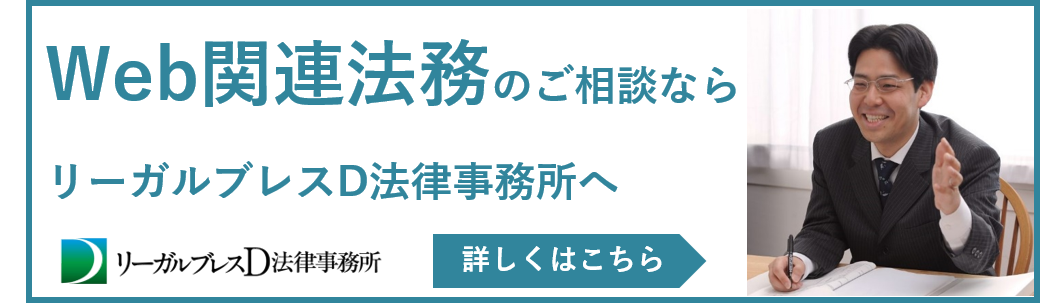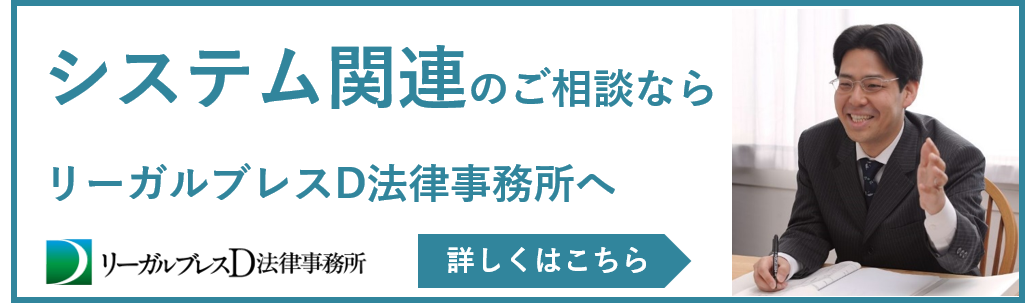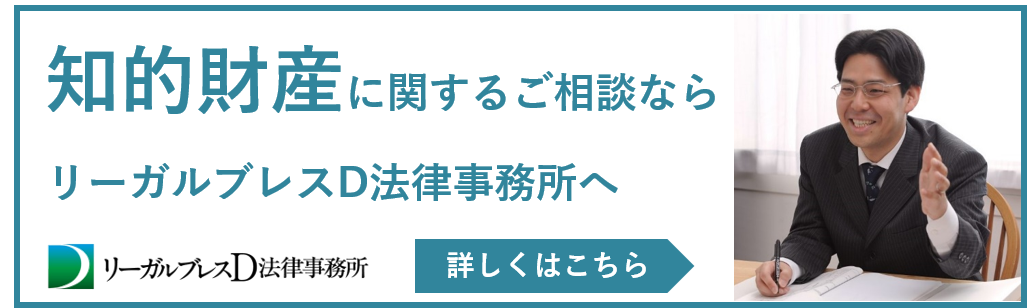IT企業特有の民事訴訟類型と知っておきたい訴訟対応上の知識
【ご相談内容】
当社は、これまでトラブルがあっても、粘り強く話合うことで解決を図ってきました。しかし、先日どうしても話合いができず、訴訟に頼るしかないという案件が発生しました。
初めて民事訴訟を行うのですが、どういった点に注意をすればよいのでしょうか。
【回答】
民事訴訟を自ら行う場合はもちろん、弁護士を代理人として選任する場合であっても、民事訴訟の流れを知っておいて損はありません。
大まかには、訴訟提起、争点整理(書面と証拠の出し合い)、尋問、判決というフローとなりますが、IT企業に特有の事件類型によっては、必ずしもこのフローが当てはまらないこともあります。
本記事では、一般的な民事訴訟の流れと対処法のポイントに触れた上で、IT企業特有の事件類型として3パターン(システム開発訴訟、情報漏洩訴訟、コンテンツ侵害訴訟)を挙げ、一般的な民事訴訟とどこが異なるのか、特徴に応じた対処法につき解説します。
【解説】
1.一般的な民事訴訟の流れ
民事訴訟の多くは次のようなフローで進んでいきます。
①事前準備
訴えを提起しようとする者は、まずは訴状を作成する必要があります。
訴状に決まった書式はないのですが、裁判所のホームページ等で一定の事件類型(貸金請求、交通事故に基づく損害賠償請求など)については参考書式が掲載されていますので、それらを参照することも一案です。なお、弁護士が訴状を作成する場合、参考書式の使いづらさを知っているため、オリジナルの書式を用いることが通常です。
訴状を作成する際に重要となるのは、「請求の趣旨」の特定と、「請求の原因」の説得性です。請求の趣旨とは、裁判所を通じて相手方(被告)に命じてほしい内容をいいます。また請求の原因とは、請求の趣旨を導くための根拠となる内容をいいます。これらの記載方法・内容には色々とルールがあるため、非法律家が裁判を利用しづらい原因の1つになっているのが実情です。
②訴えの提起
訴状の作成が終了した場合、その訴状を裁判所に提出することになります。
ここで事前に検討しておかなければならないのは、どの裁判所に提出するのかという管轄に関する問題です。
大雑把にいうと、請求額が140万円以下の場合は簡易裁判所、請求額が140万円を超える場合は地方裁判所に提出する必要があります。また、各地域にある裁判所のうち、相手方(被告)の住所地を管轄する裁判所に提出するのが原則となります(なお、管轄裁判所については様々な例外があります)。
どの裁判所に訴状を提出するか決まった後、訴状と共に印紙と郵券を裁判所に納める必要があります。印紙については請求額に応じて納める額が全国統一化されていますが、郵券については各裁判所によって異なることに注意を要します。
訴状を裁判所に受け取ってもらった後、裁判所において訴状審査を行います。
③第1回弁論期日の調整
訴状審査は、訴状を提出したその場で直ぐにやってもらえません。通常は7~10日程度かけて行われます。
その訴状審査が終了した後、裁判所より電話連絡があります。
その際に訴状に問題があれば修正するよう指示があります。問題が無ければ、1回目の裁判をいつ実施するのか日時調整を行います。
日時調整完了後、訴状は裁判所を通じて相手方(被告)に送達されることになります。
④答弁書の提出
第1回目の裁判実施日の1週間前くらいに、相手方(被告)より答弁書が提出されることが一般的です(裁判所が訴状を送達する際に、1週間前までに答弁書を提出することを促す書類を同封しているため)。
訴えを提起した者(原告)としては、相手方(被告)の言い分を確認し、どの点で食い違いが生じているのか、今後どのような反論を行うべきか等を頭の中で整理することになります。
※被告となった者が取るべき初期対応については次の記事を参照してください。
⑤第1回弁論期日の実施
訴状を提出した裁判所に出向き、予め指定された日時に法廷に出頭します。
法廷にいる裁判官と双方の主張内容の確認、証拠として提出された書類の取調べ、次回までに準備するべき事項、次回の裁判日時の調整を行い、第1回目の裁判は終了となります。
⑥第1回弁論期日後の動き(主張整理)
1~2ヶ月程度に1回の割合で裁判が実施されます。
被告が提出した主張書面に対して原告が反論書面を提出する、原告が提出した反論書面に対して被告が再反論書面を提出する…といった具合で何度か主張書面を出し合うことで、裁判官は、根本的な対立点はどこにあるのか(争点の確認)、どちらの言い分に分があるのか(心証)を整理していきます。
そして、ある程度機が熟したところで、裁判官より和解による解決可能性を打診されます(必ず打診されるわけではありません)。
⑦和解の試み
原告と被告の双方が和解協議に応じる旨回答した場合、裁判官主導での和解協議が開始されます。
その結果、双方が和解による解決に合意した場合は、合意内容を和解調書と呼ばれる書面にまとめ、裁判所が和解調書を発行することで裁判が終了することになります。
一方、原告と被告のいずれか又は双方が和解協議に応じない旨回答した場合、和解協議を行ったものの合意に至らなかった場合、和解協議が打ち切られます。
その後、判決に向けた裁判手続きを再開し、当事者や関係者(証人)の取調べ=尋問手続きに向けた準備を行うことになります。
⑧尋問手続き
提出された証拠書類だけでは裏付けることができない主張につき、双方の当事者にとって都合の良い関係者(原告や被告本人を含む)を出廷させ、裁判官の面前で証言(原告や被告本人の場合は陳述)する尋問手続きを実施します。
なお、人は思ったように話をすることができませんので、尋問手続きを実施するために、想定問答集を作成し、事前に尋問テストを行うなどして、多大な労力と時間をかけることが通常です(特に、対立する当事者からの反対尋問に耐えうるのかを重点的に検証します)。
⑨弁論終結
尋問手続き終了後、当事者の希望により、これまでの主張等をまとめた主張書面を提出する場合もありますが、裁判官はすでに結論を出していますので、双方当事者による主張立証活動の打止めと、2~3ヶ月後に判決の言渡しを行うことを宣言します。
なお、場合によっては、尋問手続き終了後に(再度の)和解の試みが実施されることもあります。ただ、上記⑦の場面と比較すると、裁判官が結論を出していることもあり、かなり白黒はっきりさせた意見を裁判官は表明した上での和解協議になることが多いようです。
⑩判決言渡し
裁判官が指定した日時・場所(法廷)にて、判決主文のみ口頭で言い渡されます(判決理由は判決書に記載されているので省略されることが通常です)。
ちなみに、ニュース等で話題になっている裁判であれば、判決言渡し日にも当事者が出頭して判決を聞くということが行われますが、多くの場合は判決言渡し日に出頭することはありません。特に弁護士が代理人として就いている場合、弁護士は裁判所に電話して判決主文だけを聞き取り、後で判決書を取りに行く(遠方であれば郵送してもらう)という対応が多いようです。
もちろん、判決言渡し日に出頭し、その日に判決書の交付を受けても何ら問題ありません。ただ、もし敗訴判決だった場合、控訴期限が交付を受けた日の翌日から起算して2週間以内となる関係上、非常にタイトなスケジュールとなってしなうことに注意を要します。
⑪控訴する場合
上記⑩でも記載した通り、判決書の交付を受けた日の翌日から起算して2週間以内に控訴状を提出する必要があります。
控訴状には決まった書式はありませんが、記載内容が定型化されているので、裁判所等のホームページで公開されている参考書式を用いることが多いようです。
控訴状を提出する先は、第一審の裁判所となります。控訴に際しては、印紙と郵券を納める必要がありますので、裁判所の指示に従って納付します。
後日、裁判所より第1回目の控訴審を実施する日時を調整するための電話がありますので、日時調整を行います。
控訴状を提出してから50日以内に、控訴理由書を裁判所に提出する必要があります。この控訴理由書は、第一審判決のどの点に問題があるのかを指摘し、控訴人が考える結論に導くための理由を説得的に記載する必要があります。
第1回目の控訴審の実施日時の1週間前くらいに、控訴答弁書が提出されますので、内容を確認し検証することになります。
⑫第1回目の控訴審の実施
控訴審を実施する裁判所に出向き、予め指定された日時に法廷に出頭します。
法廷にいる裁判官と双方の主張内容の確認、新たに証拠として提出された書類の取調べを行った後、多くの場合は裁判官が弁論終結と控訴審による判決言渡し期日を宣言し、控訴審での裁判手続きを終了させます。
第一審と異なり、控訴審は事実上1回で裁判が終了することが多いことに注意を要します(そのため、主張したいことや提出したい新たな証拠があるのであれば、第1回目の控訴審で全て出し尽くす必要があります)。
なお、場合によっては、引き続き第2回目の控訴審の実施、当事者双方の意向を確認の上、裁判官主導の和解協議が行われることもあります。
⑬控訴審での判決言渡しと上告
上記⑩でも触れた通り、控訴審でも同様に、裁判官が指定した日時・場所(法廷)にて、判決主文のみ口頭で言い渡されます。
控訴審での判決内容に不服がある場合、上告を検討することになります。
上告期限は控訴審の判決書の交付を受けた日の翌日から起算して2週間以内となりますが、上告に際しては上告理由が存在するのかという法的論点を検討する必要があります。なぜなら、上告理由は法定化されているからです(憲法解釈に誤りがある、憲法に違反するといった理由です。なお、民事訴訟法第312条参照)。
このため、事実上控訴審での結論を争う手段はないと考えたほうがよいかもしれません。
なお、上告受理申立てという制度も存在します。これは、控訴審の判決内容が最高裁判例に違反する場合や、控訴審で争われた事件が法令の解釈に重要な事項を含む場合に、最高裁判所が裁量で上告を認めるという制度です。あくまでも裁量であること、法令解釈ではなく単に事実認定に不服があるに過ぎない場合には利用できません。
2.IT企業が気を付けておきたい特殊訴訟の代表例
一般的な民事訴訟の内容・流れは上記1.で解説した通りです。
IT企業が民事訴訟を利用する場合も同様なのですが、IT企業特有の訴訟では、少し特色のある訴訟となることがあります。
代表的なものは次の3つです。
(1)システム開発訴訟
システム開発に関するトラブルとしては、例えば、プロジェクトが頓挫したことを巡っての責任追及(ベンダはユーザに対して報酬請求、ユーザはベンダに対して支払い済みの代金返還請求など)、納品された成果物の不具合を巡っての責任追及(ベンダはユーザに対して報酬請求、ユーザはベンダに対し契約不適合責任又は損害賠償請求など)、追加発注を巡っての責任追及(ベンダはユーザに対して追加報酬を請求、ユーザは支払い義務なしとして拒絶など)等様々なものがあります。
ただ、用いられる言葉が難解であり、IT業界の実情を知らないことには理解ができない取引慣行などがあるため、複雑難解な訴訟と位置付けられています(要は、裁判官は法律の専門家ではあっても、ITに関する知識をほぼ持ち合わせていないため、理解ができず適切な判断ができないということです)。
このため、民事訴訟を進めていく上で、いくつか特殊な手続きが用いられます。
【専門委員の利用】
一般的な民事裁判の場合、上記1.で解説した⑤から⑦までのフローにおいて、裁判官が主体的に関与しながら手続きが進められていることが前提となっています。
しかし、システム開発訴訟は複雑難解であるため、裁判官が特有の知見を得るべく、専門委員と呼ばれる者に関与させ、手続きを進めていく場合があります。
ちなみに、この専門委員とは、裁判所より選任されたITの専門家(民間人)です。そして、専門委員は、当事者双方の主張を把握し、必要に応じて当事者双方よりヒアリング等を行った上で、裁判官に適宜アドバイス等を行うことから、裁判の帰趨につき非常に大きな影響力を有することになります。
もちろん、専門委員を選任するに際しては、当事者双方に利害関係のない者を選任する建前にはなっています。しかし、中立公平性は公務員である裁判官とは身分が異なる以上、どうしても不安感を拭い去ることはできません。
専門委員が就いた場合は、より慎重に訴訟手続きを進めていく必要があります。
【調停手続きの活用】
民事訴訟を選択している以上、なぜ調停手続きが出てくるのかと疑問に思われるかもしれません。しかし、システム開発訴訟の場合、上記1.で解説した⑤~⑦までのフローを順次進めるのではなく、いったん訴訟手続きを中断し、あえて調停手続きに移行させて当事者双方よりざっくばらんに話を聞くということが行われたりします。
これは、訴訟手続きの場合、どうしても厳格な手続きが要請されるため本音を語りづらいのですが、調停手続きは裁判所という場所を用いた協議の場の設定となりますので、本音を言いやすく、争点整理や和解解決に馴染むことが多いからです。
もっとも、判決で白黒つけたいと考えている当事者からすれば、調停手続きは回避したいと考えることも想定されます。その場合は、調停手続きに移行させることにつき反対の意思表明を行うといった訴訟戦術が必要となります。
【技術説明会の開催】
上記1.で解説した⑤~⑦までのフローにおいて、百聞は一見に如かず…ではありませんが、裁判官が実際のシステムを見て検討したいと提案してくる場合があります。
この提案を受け入れる場合、裁判所の施設内に問題となっているシステムと同じものを再現した上で実証実験を行うことになります。
もちろん、裁判官の理解促進を図る上では有用な方法なのですが、ユーザがシステムを使用する際の環境を構築することは、技術的に難しい場合も想定されるところです。このため、技術説明会の実施を受け入れるか否かについては、相当慎重に判断する必要があると考えられます。
その他にも、システム開発訴訟は証拠資料が膨大になりやすく、争点が多岐にわたることになりがちであるため、主張整理一覧表を適宜作成し、裁判官の理解促進を図るといった工夫が必要となります。このため、システム開発訴訟では、一種のプレゼン能力を求められることになり、一般的な民事訴訟よりも手間・労力をかけなければならないことを押さえておく必要があります。
(2)情報漏洩(セキュリティ)訴訟
近時はシステムの脆弱性や設定ミスによる個人情報等の漏洩が後を絶たず、この漏洩を巡って裁判沙汰になるということが増えてきています。
このような情報漏洩に起因する民事訴訟は、基本的には上記1.で解説したフローに従って進んでいくことになりますが、やや特殊な対応が求められます。
【訴訟告知】
訴訟告知とは、訴訟当事者が第三者に対し、裁判所を通じて民事訴訟が行われていることを伝達する制度です。
要は、民事訴訟の当事者となっていない第三者を、当該訴訟に巻き込むための手続きなのですが、情報漏洩訴訟では、上記1.の⑤から⑥のフローの中で、この訴訟告知手続きが頻繁に用いられます。なぜなら、情報漏洩の原因を探求していけばいくほど、関係者が多数存在することが判明し、誰が最終的に責任を負うのかにつき、一種の責任の押し付け合い状態になってしまうからです。
例えば、ECサイトより個人情報の漏洩が発生した場合、ECサイト運営者は顧客に対して何らかの責任を負うことになりますが、運営者はECサイトの保守運用を別事業者に委託していたのであれば、その別事業者の保守運用に問題があったとして訴訟告知を行うことになります。その別事業者がセキュリティ対策について下請けに出していた場合、別事業者は下請け業者に対して更に訴訟告知を行う…といった具合です。
関係当事者が参加するたびに訴訟は事実上ストップしますし、様々な主張が飛び交うことで複雑化、関係当事者全員の都合をつけながら裁判を行うための日程調整も難しくなりがちです。
このため、裁判の実施回数の割には時間がかかるといった事態が起こりえることを認識する必要があります。
【機密情報の公開】
民事訴訟を遂行する上で当事者が裁判所に提出した主張書面や証拠は、原則として誰でも閲覧可能とされています。しかも、この閲覧は、上記1.で解説した①から⑬までの期間中のみならず、民事訴訟が終了してから5年の間は閲覧可能とされています。
このため、セキュリティ上必要な技術情報や非公開としている情報を閲覧者は入手することが可能であり、場合によってはマスコミ等で周知されてしまうリスクがあります。
一定の事由がある場合、裁判所に対して閲覧制限を申立てることができるとはいえ、実際のところなかなか裁判所は認めないのが実情です。
訴訟を有利に進める戦略はもちろんのこと、情報が公開されることで別に困った事態とならないかを考えながら、手続きを進めていく必要があります。
(3)コンテンツ侵害訴訟
この記事では、コンテンツ侵害訴訟とは、文章や画像はもちろん、プログラムなども含めています。
コンテンツを保護する法律の代表例は著作権法ですが、この著作権法に基づく民事訴訟を進める場合、少し特殊な事情があることを知っておく必要があります。
【管轄】
上記1.②で解説した管轄ですが、著作権を根拠に民事訴訟を提起する場合、留意するべき事項があります。
プログラム著作物に関する訴訟を提起する場合ですが、実は東京と大阪の2ヶ所のみしか認められていません。すなわち、札幌から名古屋までの高裁管轄地域は東京地裁、大阪から福岡までの高裁管轄地域は大阪地裁と制限されていることに注意を要します。ちなみに、プログラム著作物以外の著作物については、上記制限は課されません。
また、上記1.⑪で解説した控訴審での管轄ですが、プログラム著作物については東京にある知財高裁のみとなります(プログラム著作物以外の著作物については、この制限はありません)。
プログラム著作物を対象とする民事訴訟の場合、管轄制限があることに要注意となります。
【審理の進め方】
上記1.⑤から⑥までの手続きの進め方につき、法律上の根拠はないのですが、裁判所は先に侵害論(=著作権侵害が成立するか否かの判断)を検討し、侵害成立の場合に限って損害論(著作権侵害に基づく損害発生の有無、額の算定)を検討するという、二段階審理を行っています。
この審理の進め方を知らずに、先に損害論の主張立証(損害論への反論)を行っても、裁判官から苦言を呈されますし、場合によっては侵害論に関する主張立証が不十分であるとして一方当事者に不利に作用することもあり得ます。
基本的には裁判官より説明があるとは思われますが、無駄な訴訟活動を防止するためにも知っておきたい知識となります。
3.当事務所でサポートできること
IT企業が対応する訴訟は、技術的な専門知識が要求されることが多く、残念ながら弁護士であれば、誰でも対応可能という訳にはいかないのが実情です。この点、当事務所の代表弁護士は情報処理技術者資格を有しており、高度な技術的問題にも対応可能です。
また、顧問契約を結ぶことで、IT企業は日常的に法律の相談ができる体制を整えることができます。これにより、紛争を防止できる契約書の作成や交渉の進め方に関する知見を得ることができ、訴訟リスクを未然に防ぐことができます。
当事務所では、さらに次のような強みとサポートを行っています。
①IT企業からの相談対応に多数の実績があること
当事務所の代表弁護士は、2001年の弁護士登録以来、複数のIT企業の顧問弁護士として活動し、紛争予防から訴訟対応まで幅広く関与し、解決を図ってきました。
これらの現場で培われた知見とノウハウを活用しながら、ご相談者様への対応を心がけています。
②時々刻々変化する現場での対応を意識していること
弁護士に対する不満として、「言っていることは分かるが、現場でどのように実践すればよいのか分からない」というものがあります。
この不満に対する解消法は色々なものが考えられますが、当事務所では、例えば、法務担当者ではなく、営業担当者や制作担当者等との直接の質疑応答を可としています。
現場担当者との接触を密にすることで、実情に応じた対処法の提示を常に意識しています。
③原因分析と今後の防止策の提案を行っていること
弁護士が関与する前にトラブル対応を開始したところ、法的判断の誤りにより、ご相談者様が思い描いていたような結論を得られず、以後の対応に苦慮している場合があるかもしれません。
こういった場合に必要なのは、方針・対処法の軌道修正をすることはもちろんのこと、なぜ思い描いた結論に至らなかったのか原因検証し、今後同じ問題が発生しないよう対策を講じることです。
当事務所では、ご相談者様とのやり取りを通じて気が付いた問題点の抽出を行い、改善の必要性につきご提案を行っています。そして、ご相談者様よりご依頼があった場合、オプションサービスとして、社内研修やマニュアルの整備、契約書の常時チェックなども行っています。
事業の適正化とトラブル防止のための継続的なコンサルティングサービスもご対応可能です。
<2024年9月執筆>
※上記記載事項は弁護士湯原伸一の個人的見解をまとめたものです。今後の社会事情の変動や裁判所の判断などにより適宜見解を変更する場合がありますのでご注意下さい。
- IT企業に必要な契約書とは?弁護士が解説
- 商用利用は大丈夫? ChatGPTと切っても切れない著作権の関係について解説
- システム開発取引に伴い発生する権利は誰に帰属するのか
- IT企業特有の民事訴訟類型と知っておきたい訴訟対応上の知識
- ホームページ、WEBサイトに関する著作権の問題について解説
- メタバースをビジネス・事業で活用する上で知っておくべき著作権の問題
- 画面表示(UI)は著作権その他法律の保護対象になるのか?
- 令和5年改正不正競争防止法のポイントを解説
- オープンソースソフトウェア(OSS)利用時に注意すべき事項について(法務視点)
- ソフトウェア・エスクロウとは何か? 活用場面とポイントを解説