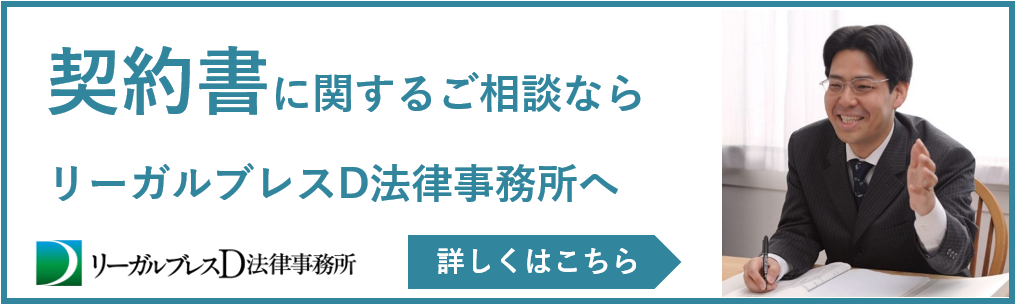契約書の電子化は有効?電子契約の利用価値や疑問について弁護士が解説
【ご相談内容】
取引先より、「今後契約を締結する場合、電子契約にて行いたい」との申し入れがありました。メリットについて色々と説明を受けたものの、電子契約で本当に契約を締結したといえるのか、新たな費用負担が生じるのではないか等の不安があり、電子契約の導入に決心が付かない状態です。
電子契約を導入・運用するにあたっての法的注意点について教えてください。
【回答】
誤解が多いのですが、契約書に署名押印を行わない電子契約であっても、法的には有効な契約として取り扱われるのが原則です。
なぜなら、民法第522条第2項では、「契約の当事者は、法令の制限内において、契約の内容を自由に決定することができる。」と定められており、電磁的方法でサインすること、契約書を電子データで取り扱うことも当事者間で合意する限り自由だからです。但し、法改正により年々減少しているとはいえ、一部の契約については電子契約が認められない場合があります。やや細かい話となりますので、例外に該当するかについては弁護士に確認したほうが無難です。
ところで、一口に「電子契約」といっても、電子署名と呼ばれる技術手段を用いた電子契約もあれば、単に契約締結手続きが電子化されているに過ぎないというものまで様々です。
そこで、本記事では、まずはどのような電子契約が利用されているのか、その種類について解説します。そして、電子署名を用いた電子契約の有効性と取扱い上の注意点について解説を行います。最後に、電子契約に関係する法制度について触れます。
【解説】
1.電子契約とは
上記【回答】でも触れた通り、電子契約それ自体について法令上の定義は存在しません。
一般的には、これまで紙媒体を用いて行っていた契約締結手続きを改め、インターネット上で契約手続きを完結させ、契約書という紙媒体を作成しない方式を「電子契約」と呼ぶことが多いようです。
2.電子契約の種類
電子契約は、電子署名に対する「本人確認を、誰がどのようにして行うのか」によって、2つの種類に分類することができます。
①契約当事者本人が発行する電子証明書を用いるもの(当事者型電子署名)
契約当事者が特定認証業務を行い、当該当事者が行う電子署名につき、自ら発行する電子証明書=本人の電子署名であることを証明する書類を添えて、契約を締結する方式のことをいいます。
特定認証業務については、電子署名法2条以下に定めがあります。同法によれば、一定の技術的水準が求められるところ、この技術的水準を満たす民間事業者はごく一部であるため、当事者型電子署名はあまり普及していないと考えられます。
②当事者以外の第三者が本人確認を行うもの(立会人型電子署名)
契約当事者以外の第三者(電子契約サービスを提供している事業者)が、契約を締結しようとする者の本人確認を行った上で、当該第三者が電子契約に電子署名を行う方式のことをいいます。
要は、契約書に電子署名を行うのは当事者ではなく、当事者から依頼を受けた第三者が行うというものであり、現在流通しているサービスのほとんどはこの立会人型電子署名といわれています。
さて、電子契約を検討する場合、電子署名法と関連付けて上記2つを検討することが通常なのですが、電子契約を書面以外の方法で契約を締結する場合と広義に考えた場合、次のような方法も電子契約といえるかもしれません。
(a)電子サインを利用する方法
保険契約などで用いらえることが多いのですが、端末(タッチパネル)上に電子ペンで契約者本人が署名することで契約を締結する方法です。
この方式の場合、電子ペンで顕出された文字が契約者本人のものといえるのか(筆跡が同一であるか)が重要となる点で、紙媒体の契約書と同様の問題が生じます。このため、事前に契約者本人の署名を登録し、その登録した筆跡と比較照合することで本人確認を行うといった方法が取られるようです。
技術的な導入ハードルが高く、特定の業界以外では普及していないように思われます。
(b)ID・パスワードによる本人確認とクレジットカードを併用する方法
インターネット上の通信販売で用いられることが多い方法となります。
この方法は、契約当事者による署名がなく、ID・パスワードによるアクセス権確認とクレジットカードの利用権確認による二重の確認を行ったことをもって本人確認に代えるというものであるため、事実上の本人推定は働くものの、100%の裏付けを取ることは困難というジレンマがあります。
もっとも、簡易迅速性が要求されるネット通販では、この方法が主流となっています。
(c)契約書をPDF化して交換する方法
紙媒体の契約書に一方当事者がサインし、それをPDFにして相手当事者にメール送信する、相手当事者は当該PDFをプリントアウトしサインした上で再度PDF化し、当該PDFを一方当事者にメール返信するという方法が典型例です。
現実に自署又は記名押印された紙媒体の契約書が入手できないという点で、やや信用性を欠くことは否めません。もっとも、紙の契約書で契約手続きを進める場合の欠点である“時間がかかる”問題を克服できるという点では、一定のメリットがあります。
ところで、契約書を紙媒体としてプリントアウトする以上、(特に後からサインする当事者にとっては)印紙税の問題は避けて通れないのではないかという疑問が残ります。
この点を考慮し、双方当事者がサインした契約書をPDF化し、それぞれ相手当事者にメール送信し、当事者は相手がサインした契約書のPDFデータを保有するという方法が取られる場合があります。要は、相手のサインのみ行われた契約書データが手元に残るという方法なのですが、相手のサインが相手本人であることが確認できれば問題がないとはいえ、やや信用性に劣る契約書であることは上記と同様です。
3.電子化できる契約書とできない契約書
日本国内では電子契約の普及が遅れていたのですが、新型コロナの流行を機に、一気に契約の電子化が進み、政府も法改正や法令解釈の変更・明確化等を通じて後押ししている状況です。
このため、ほとんどの契約書は電子化できるといって過言ではありませんが、厳密には各法令を参照し、必要に応じて監督官庁に問い合わせて確認するほかありません。
なお、本記事作成時点(2024年2月追記)において、電子化できない契約書の典型例をあげるとすれば、公正証書の作成が要求されている契約書が想定されます。例えば、事業用定期借地契約や任意後見契約などは電子契約とすることはできません。
4.電子契約のメリット・デメリット
(1)メリット
電子契約を利用するメリットは、おおよそ次の3点にあるとされています。
①印紙代その他経費節約
紙媒体の契約書の場合、印紙税法に従い、一定額の印紙を契約書に貼付ける必要があります。
一方、電子契約の場合、印紙は不要とされています。
例えば、取引先と継続的取引に関する契約を締結した場合、4000円の印紙負担が発生するところ、複数の取引先との間で継続的取引に関する契約を締結するとなると、その都度4000円を印紙負担する必要があり、無視できない負担額となります。また、取引額が大きくなればなるほど印紙額は高額となるところ、例えば請負契約で1億5000万円の取引を行った場合、その印紙税額は10万円であり、かなり重い負担となります。
電子契約では、このような印紙負担から解放されるという点で、経済的なメリットが大きいといえます。
また、印紙代削減以外にも経済的なメリットがあるとされています。
例えば、契約書を保管する物理的な場所が不要となる、契約を締結するに際しての経費(印刷代、封筒代、切手・配送代、場合によっては印鑑証明や登記簿謄本取得費用など)が不要となる、契約締結手続きや管理に要する人件費が不要となる、といった具合です。
1つ1つは少額かもしれませんが、塵も積もれば山となるということで、相応の経費削減効果が見込まれることになります。
②迅速性・事務作業の効率化
紙媒体の契約書の場合、一方が他方に契約書を送付し署名押印する、その署名押印した契約書を返送してもらうという手順を取ることが多く、契約締結手続きが完了するまでに数日の時間を要します。一方、電子契約の場合、電気通信設備を用いて契約データを送信するため、当日中に契約締結手続きを完了させることが可能です。
この点で契約締結手続きの迅速化を図ることができると共に、上記手順にかかる事務作業が無くなるという点で、効率化を図ることができます。
また、紙媒体の契約書の場合、どの契約書がどこに保管されているのか、契約書に何が書かれているのか、現場での煩雑な確認作業が必要となるのに対し、電子データの場合、電子端末を用いることで、容易に契約書を探し出すことができ、その内容をキーワード等で検索することが可能です。
このような契約管理の点でも、作業効率化を図ることが可能となります。
③コンプライアンス強化
紙媒体の契約書の場合、原本の紛失や劣化が生じうること、事後的な改ざんが行われうること、契約書それ自体を隠蔽することが可能であること、といったコンプライアンス上の問題を抱えることになります。
一方、電子契約の場合、電子データであることから紛失・劣化は考えにくいこと、タイムスタンプを用いることにより改ざんの有無につき識別可能であること、電子データであるが故に探索可能であること、といった問題を技術的に解決することが可能です。
この点から、電子契約を利用した場合、コンプライアンス対策が講じやすくなります。
なお、電子契約の場合、自然災害等による契約書原本の喪失防止につながるという点ではBCP対策にもなりますし、ペーパーレスを実現するという点ではSDGs対策にもつながると考えることもできます。
(2)デメリット
一方で電子契約を用いることによるデメリットもあります。大まかには次の3点です。
①電子契約が認められない取引類型が存在すること
例えば、特定商取引法に該当する訪問販売等で必要となる契約書面については、紙媒体での契約書が要求されており、電子契約は認められていません(2023年1月執筆時点。なお、将来的には一定条件を満たすことで電子契約が認められるものと予想されます)。
大部分の契約書については電子契約が可能となっているものの、上記のような消費者保護の観点等から一部については電子契約が認められない類型が存在することに注意が必要です。
②契約の変更(バックデート、意思表示の撤回など)が困難であること
例えば、契約書を取り交わす以前より、実際に契約はスタートしているという場面は現場実務ではままある事象であるところ、紙媒体の場合、契約書作成日付を遡らせて、契約スタート日に合致させるという対処を行ったりします。
しかし、立会人型電子署名と呼ばれる電子契約システムを利用する場合、契約書の作成日付がデフォルトで当日のみに固定されていることがあります。このため、実際の契約スタート日に作成日付を合わせることができないといった問題が起こったりします。
あるいは、契約締結後に誤字脱字その他修正箇所が見つかった場合、些細な修正であれば、契約書原本に直接加除修正して訂正印を押すといった簡易策で済ませることが多いと思われます。しかし、電子契約の場合、改ざん防止の観点から、技術的に一度締結した契約内容を修正することが予定されていません。
このため、契約内容を修正する場合、再度契約締結手続きをし直す必要があり、やや柔軟性を欠くところがあります。
③契約締結手続きを変更することに対する抵抗感
これは電子契約を導入しようとする事業者内部で問題となり得ることもあれば、取引先からの拒絶反応により問題となり得ることもがあります。
まず、事業者内部の問題としては、電子契約を導入するために必要となる新たな費用負担に対する抵抗が当然に想定されます。また、従前の手続きを大きく変更することから、変化を嫌う心理や変更準備等への負担感、パソコンを含めた電子機器を上手く操作できないといったスキル不足などを感じる従業員からの抵抗もあり得る話です。
一方、取引先等からすれば、コストや手間に対する負担感はもちろんのこと、そもそも電子契約で本当に契約が成立したといえるのかという不安感(不信感)を拭い切れないというのもあります。
5.電子契約に関係する法律
電子契約を検討する上で、避けて通れない法律がいくつかあります。
ここでは代表的な4つの法律を取り上げます。
(1-1)民事訴訟法(二段の推定)
署名押印のある契約書は、民事訴訟法上特別な効力が認められています。
法学上は「二段の推定」と呼ばれている理論ですが、具体的には…
(a)当事者本人が保有する印鑑が契約書に押印されていた場合、本人が押印したものと推定する
(b)本人による押印がある以上、契約書は本人が作成したものと推定する
というものです。
誤解を恐れずに端的に説明すると、本人持参の押印があれば、本人は契約書に定められていた内容につき了解していたと強く推定できるので、よほどのことがない限り、本人は契約の成立を否定することはできないとイメージしておけば、おおよそ間違いではありません。
ところで、電子契約の場合、押印がないため上記の二段の推定が及ばないのではないかという疑問が生まれます。いろいろ議論はあるのですが、現時点は次のように整理しておけば良いかと思います。
・電子署名法の要件を満たす当事者型電子署名の場合…原則二段の推定は及ぶと考えてよい
・立会人型電子署名の場合…二段の推定が及ぶかは不明確(※)
※令和2年9月4日に総務省、法務省、経済産業省の連名で「利用者の指示に基づきサービス提供事業者自身の署名鍵により 暗号化等を行う電子契約サービスに関するQ&A (電子署名法第3条関係)」と題する見解を公表しています。ただ、法解釈の最終判断権者は裁判所であり、本記事執筆時点(2023年1月)では裁判例が存在しないようなので、この見解を絶対的拠り所とするのはやや危険なところがあります。また、この見解では、一定条件を満たした立会人型電子署名であれば二段の推定が及ぶと記述されていますが、果たして現在流通している立会人型電子署名がその条件を満たすといえるのか、慎重な判断が必要と考えられます。
さて、上記のように記述すると、現在普及している立会人型電子署名による電子契約の場合、二段の推定が及ばないので特に裁判の場では不利になってしまうのではと考える方がいるかもしれません。しかし、二段の推定が及ばないから、電子契約は無意味であるという結論にはなりません。
なぜなら、推定が及ばないなら、他の手段で立証(=契約書は相手本人が作成したものであり、内容につき了解していること)すればよいからです。
例えば、契約締結に至る交渉経緯を示した電子メールその他電子媒体上の記録(チャット等)から、問題となっている内容の契約を締結することは合理的であるといった立証方法が考えられます。あるいは、電子契約で用いられた電子メールアドレスその他電子媒体上の連絡先が、日常的に相手当事者の意思表明に用いられていたことを裏付けることで、相手の同一性を立証するという方法も考えられます。さらには、電子契約サービスを提供する事業者に申告すれば、電子契約締結時のアクセスログ等の本人確認書類を発行してくれますので、その書類を証拠代わりにすることも考えられます。
以上のように、電子契約において二段の推定が及ばない可能性がある点をネガティブに捉える必要はないと考えられます。ただし、契約締結前の交渉段階を含めた契約管理はやや気を配る必要があります。
(1-2)民事訴訟法(電子契約の証拠提出方法)
紙媒体の契約書の場合、原本とコピーを裁判所持参の上、コピーが原本と相違が無いことを裁判官に確認してもらってから、契約書のコピーを証拠提出するという取扱いで裁判手続きは進行します。では、電子契約の場合、裁判所にどうやって契約書(データ)を証拠提出すればよいのか疑問に思われるかもしれません。
この点、契約の成立自体争いがない場合は、①電子契約のデータを記録媒体に記録し、当該媒体を証拠提出する方法、②電子契約をプリントアウトし、その印刷物を証拠提出する方法、の2種類が考えられ、結論としてはどちらでもよいと考えられます。ちなみに、執筆者が経験した限りでは、②の方法を用いていることが一般的なように思います。
なお、テーマからは外れてしまうのですが、②の方法を採用した場合、税務上は印紙税負担の問題が生じるのではないかという疑義がある点は注意が必要です。
(2)電子署名法
上記(1-1)で少し触れましたが、電子契約の信用性を担保するためには避けては通れない法律となります。
電子署名とは、紙媒体の契約書で用いる印鑑の電子版のようなものをイメージすればよいのですが、次のように整理することが可能です。
・本人だけが保持するもの…印鑑(紙)、秘密鍵(電子契約)
・保持するもので行うこと…押印(紙)、プログラムによる暗号処理(電子契約)
・結果として生じる成果物…印影のある契約書(紙)、電子署名(暗号処理)された電磁的契約書(電子契約)
・本人性担保の裏付け資料…印鑑証明書(紙)、電子証明書(電子契約)
・本人性を確認しうる手段…印鑑証明書の印影と契約書の印影の比較(紙)、電子証明書にある公開鍵と電子署名された電磁的契約書(秘密鍵)とのプログラム上での照合
このように、電子署名という技術を用いることで、電子契約における本人性の確認(本人が契約書に署名を行ったことと同視すること)を行うことになるのですが、事業者が勝手に電子署名をあれこれ作出してしまうと、色々と混乱を招くことになります。
そこで、電子署名の規格や技術的水準等について定めた法律が電子署名法ということになります。
ただ、電子署名がない電子契約は当然に無効となるものではありません。上記(1-1)で記述した通り、二段の推定が及ぶのかという点に意義がありますので、電子署名がない又は電子署名法が定める水準を満たさない電子署名である場合、他の方法を用いて当事者が電子契約を作成したことを証明すれば問題はありません。
あくまでも電子契約成立の証明を簡易にするための恩恵的な法律にすぎないと考えておけば事足ります。
(3)電子帳簿保存法
2022年1月1日より電子帳簿保存法が改正される旨アナウンスされたものの、対応期間が不十分であることから多方面からクレームが発生し、事実上の延長措置が余儀なくされたというニュース等で名前は聞いたことがあるという方も多いかもしれません。
電子帳簿保存法は、電子契約の有効性の観点から語られる法律ではなく、法人税などの税務上の観点から、電子契約を電子データのまま保存しても税務上の根拠資料として利用することが可能なのか、逆に電子契約をプリントアウトした場合に税務上の根拠資料として使用不可となるのはどのような場面なのか等につき、定めている法律と考えればイメージしやすいかもしれません。
電子帳簿保存法の内容については、次の記事をご参照ください。
改正電子帳簿保存法について法務視点でのポイントを弁護士が解説!
(4) e-文書法
電子帳簿保存法が、電子契約を税務上の根拠資料として取り扱う方法に絞って定めているのに対し、e-文書法は税務以外の分野における取扱い、例えば、商法や会社法に基づき保存するべき契約書類の保存方法について定めた法律となります。
この法律も電子契約の有効性に直接関係する法律ではありません。
6.電子契約を導入する際の注意点
上記4.(2)で記載したデメリットを克服することが可能かという点はもちろんとして、契約である以上、相手方当事者の都合を考えることも重要な視点となります。
特に、電子契約を導入するに際して、何らかの費用負担(設備導入費用や維持費用など)が生じるにもかかわらず強制することは、場合によって下請法及び独占禁止法違反と言われかねないことに注意を要します(一昔前のEDI導入時の問題と同じです)。
また、社内都合にも意識する必要があります。電子契約化した場合、社内フローが変わることは必然ですし、システム操作に慣れていない従業員からすれば負荷のかかる作業が新たに発生することになります。従業員の納得を得る必要があることも注意したいところです。
さらに、上記5.(3)でも触れましたが、電子帳簿保存法に対応した電子契約システムかという視点も忘れてはなりません。万一非対応の場合、かえって業務の非効率化を招き、デメリットの方が大きいという状況になりかねません。
7.当事務所でサポートできること
電子契約の導入は今後拡大していき、事業者は否が応でも対応しなければならないと予想されます。
ただ、上記でも解説した通り、現在普及している電子契約サービスは「立会人型電子署名」と呼ばれるものであり、二段の推定が及ぶのか疑義が残るなど、紛争の場面ではやや使い勝手が悪いところがあります。
当事務所では、電子契約を前提にした裁判事例も複数扱った実績があり、実際の裁判手続きを通じて得られた知見をもとに、電子契約を導入するにあたっての注意事項や運用に際してのポイント等について、情報提供やアドバイスを行うことが可能です。
また、上記1.で記載したような、広い意味での電子契約、すなわち電磁的方法を用いた契約締結方法の使い分けや実践例などをご紹介することも可能です。
電子契約を含む契約の電子管理をご検討されている、あるいは悩みを持っている事業者様は是非当事務所にご相談ください。
<2023年1月執筆、2024年2月追記>
※上記記載事項は弁護士湯原伸一の個人的見解をまとめたものです。今後の社会事情の変動や裁判所の判断などにより適宜見解を変更する場合がありますのでご注意下さい。
- その「免責条項」は本当に意味があるのか?契約リスクを左右する責任条項の考え方
- そのSLA、本当に機能していますか? 弁護士が教えるSLAの法的リスクと設計の勘所
- 契約書は誰が作成すべきか? 作成側・受領側が押さえたいポイントを弁護士が徹底解説!
- 偽装請負に該当するとどうなる? 契約形態・運用・制裁・是正策を弁護士が徹底解説
- IT取引の契約解消トラブル-無効・取消し・解除の実務対応
- 「中途解約で泣き寝入りしない!」WEB制作の未払い報酬を回収する方法
- 利用規約とは?作成・リーガルチェックのポイントについて弁護士が解説
- なぜテンプレートの利用規約はダメなのか?弁護士が教えるテンプレートの落とし穴
- 契約書のAIレビュー・チェックだけで万全!? 弁護士のリーガルチェックとの異同を解説
- アプリ事業者必見!スマホソフトウェア競争促進法で変わるスマホ市場の競争環境