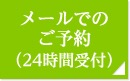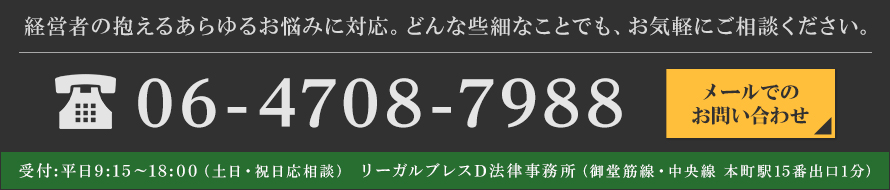ホームページを作成する場合の注意点
ホームページ・WEB制作でトラブルが発生する原因
ホームページ・WEB制作に関する多くのご相談事例より分析した場合、多くは次のような事項に起因します。
①業務範囲が不明確
受託者が提供するサービス範囲を明確にしないと、委託者との間で「期待していたものと違う」というトラブルが発生しがちです。
例えば、受託者はホームページ・WEB完成後の手直しや調整業務、保守や運用サポート業務、SEO対策業務を含まないと認識していたのに対し、委託者はこれらの業務を含むと認識していたといったものがあります。
②コミュニケーション不足
委託者の意向確認が不十分なまま制作を進めた場合、後で最初からやり直しになるといったトラブルが発生しがちです。
例えば、委託者の曖昧な指示を受託者が勝手に解釈し、そのまま進行してしまうといったものがあります。
③修正依頼の範囲が過大
委託者の当初要望以外の追加要求に受託者が安易に応じることで、納期に間に合わない場合や、追加費用の負担を巡ってのトラブルが発生しがちです。
例えば、当初は静的サイトを制作することで合意があったにもかかわらず、後で動的サイトへの変更要求があり、作業工程や作業量が大きく異なってしまったというものがあります。
④技術的な誤解や制約
受託者が選定した技術やツールが委託者の期待と合致しない場合、トラブルが発生しがちです。
例えば、ホームページ・WEBの記事更新に際し、委託者はWordPressのような自ら簡単に記事更新ができる機能が実装されることを想定していたにもかかわらず、実際には受託者に依頼しないことには技術的に記事更新が困難といったものがあります。
⑤権利帰属
制作物に関する権利を巡って、当事者双方の認識が異なる場合、トラブルが発生しがちです。
例えば、委託者は代金を支払った以上、ソースコードを含むホームページ・WEBに関するデータは全て自分のものであるとして引渡しを要求するといったものがあります。
ホームページ・WEB制作時に注意するべき法律や権利
ホームページ・WEBには様々な法律が関係してきますが、代表的なものとして次の3つを取り上げます。
(1)著作権
例えば、ホームページ・WEBのデザインや内容を決める際、他人のホームページ・WEBを参照するということは無いでしょうか。そして、「一般的に公開されているものである以上、真似ても特に問題にならない」と思っていないでしょうか。
これは大きな間違いであり、場合によっては犯罪にもなりかねません。なぜなら、著作権法という法律があるからです。
この著作権法ですが、端的に説明すると、他人の著作物を無断で利用することはNGであるということを定めている法律です。
ちなみに、著作物とは、思想又は感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものと法律上は定義されています。しかし、別に芸術作品に限定されるわけではなく、例えば素人が作成した文章・絵画・音楽等も著作物に該当します。
したがって、他人のホームページ・WEBに記載されている文章コンテンツや画像をコピペして利用する、他人のホームページ・WEBの特徴的なデザインを真似てしまった場合、著作権法違反で訴えられかねない事態となります。
なお、ネット通販などでよくある事例なのですが、仕入れた商品を販売するに当たり、製造者が公開している商品画像を無断で利用した場合、製造者より著作権侵害の警告が来たりします。製造者の商品を売っているだけであり、何ら違法な商売など行っていないのに…と思われるかもしれませんが、商売の適法性と著作権侵害に相関関係はありません。理論的には著作権侵害となる以上、注意が必要です。
(2)肖像権・パブリシティ権
ホームページ・WEBにインパクトを与える目的その他様々な目的で、有名スポーツ選手や芸能人等の著名人の名前や写真をホームページ・WEB上に掲載したいと考えることがあるかもしれません。
そして、実際に掲載している方の中には、著作権法については十分注意しており、例えば、写真画像であれば、自ら撮影した画像あるいは撮影者の了解を得た画像を利用しているので、法律違反の問題は無いと考えている方もいらっしゃるかもしれません。
しかし、残念ながら間違っていると言わざるを得ません。
なぜなら、著作権法違反の問題がクリアーされても、他の法律に違反してしまうからです。
本件のように、有名スポーツ選手や芸能人については、CMで商品宣伝広告を行っている事実からもお分かりの通り、独自の顧客吸引力を有しています。そしてこの顧客吸引力については法的保護に値するとされ、「パブリシティ権」と呼ばれています。
したがって、スポーツ選手や芸能人はパブリシティ権を保持する以上、無断で顧客呼び寄せのために名前・写真等を利用した場合、このパブリシティ権の侵害であるとして訴えられてしまうことになります。
このパブリシティ権は、裁判例の積み重ねで認められた権利であり、どこかの法律に明文化されているわけではないため、気が付かないかもしれませんが、十分注意する必要があります。
一方、有名人を使わなければ他人様の写真(例えば自社の従業員等)を掲載しても良いのか?という疑問が生じます。
しかし、これも場合によっては法律違反になりえます。
なぜなら、有名人以外の方であっても肖像権を保持しており、無断でホームページ・WEB上に写真が掲載されていた場合、肖像権侵害であるとして訴えることができるからです(なお、写真の掲載方法如何によっては、肖像権以外にもプライバシー権侵害や名誉毀損という問題も生じます)。
この肖像権と呼ばれる権利は、パブリシティ権と同じく法律上明記されたものではありません。しかし、裁判所は、人間はむやみに姿を撮られたくない、公にされたくないという心情があり、この心情は法的保護に値すると認定しています。
したがって、人間の名前・写真等を用いる場合は、必ず本人からの了解を得る必要があります。
なお、近時は自社従業員を自社の宣伝広告目的で用いることが多くなっていますが、対象となる従業員の承諾を得ていない場合はもちろん、その従業員が退職した場合に肖像権トラブルが発生しがちであることに注意を要します。
(3)その他
例えば、ECサイトであれば、ユーザに対して利用規約に記載した内容で契約が成立したと主張するためには、民法の定型約款に関する規定を意識してホームページ・WEBを制作する必要があります。また、特定商取引法に定める表記事項をホームページ・WEBに記載する必要があります。
ECサイトに限らず、ホームページ・WEB上にプライバシーポリシーを公開するのであれば、個人情報保護法を意識したホームページ・WEB制作が必要となります。
何らかのロゴをホームページ・WEBに掲載する場合、そのロゴが他人の商標権を侵害しないのか、十分に確認する必要があります。
ホームページ・WEB制作に関するご相談事例
様々なご相談をお受けしていますが、例えば、次のような事例に関するご相談を受け、解決を図ってきました。
・ホームページ・WEB制作に関する契約内容の修正交渉が問題となった事例
・注文書交付前に作業を開始したところ、契約交渉が頓挫したことで、作業代の清算が問題となった事例
・契約には至らなかった取引先に対して提案した企画内容が模倣されていたことで、損害賠償請求が問題となった事例
・受注したホームページ・WEB制作につき、途中で想定外の業務追加要求があり、追加費用の支払いが問題となった事例
・注文者都合でホームページ・WEB制作が打ち切られたことに伴う、報酬の清算が問題となった事例
・納品が完了したにもかかわらず、注文者の拘りによる修正要求への対応が問題となった事例
・検査合格した後に見つかった不具合に対する無償修正要求への対応が問題となった事例
・ホームページ・WEB不稼働に対する責任追及が問題となった事例
・ホームページ・WEBから個人情報が漏洩し、事後対応が問題となった事例
・ホームページ・WEBに蓄積されたデータが消失し、原因追及が問題となった事例
・制作代金の未払いに対する、債権回収が問題となった事例
・業者変更に伴うデータの開示及び引継作業の必要性が問題となった事例
・営業時間外の保守要求に対する対応が問題となった事例
弁護士に相談するメリット
ホームページ・WEB制作に関するトラブルを未然に防ぎ、ビジネスを円滑に進めるために、弁護士を活用したほうが良い理由は次の通りです。
①法的に安心できる契約書の作成とチェック
ホームページ・WEB制作におけるトラブルの多くは、契約内容の不備や曖昧さに起因します。弁護士に相談することで、例えば、次の点を網羅した契約書を作成することができます。
・業務範囲の明確化:提供サービスを詳細に記載し、スコープクリープを防止。
・修正対応の範囲と回数:無制限の修正依頼を防ぐための具体的な条件設定。
・著作権や知的財産権の取り決め:制作物の権利帰属を明確にし、後のトラブルを防ぐ。
・キャンセル時のペナルティ:途中解約時に適切な補償を得られる規定を盛り込む。
法的に適切な契約書を整えることで、依頼者との間で認識のズレを防ぎ、トラブル発生時の交渉を有利に進めることができます。
②トラブル時の迅速かつ適切な対応
万が一トラブルが発生した場合、弁護士に相談することで次のようなメリットが得られます。
・依頼者との交渉支援:報酬未払い、納期遅延などの問題に対し、弁護士が代理で交渉。
・法的手続きの対応:裁判や調停が必要な場合でもスムーズに進行。
・証拠整理のアドバイス:契約書やメールなど、法的に有効な証拠の準備を支援。
弁護士の関与があることで、相手方も適切な対応をせざるを得なくなり、問題が早期に解決しやすくなります。
③著作権法その他法規制への対応
制作時に使用する画像やフォント、プライバシー関連の法律について、知らないうちに違反してしまうケースも少なくありません。弁護士のサポートを受けることで、次のリスクを回避できます。
・著作権侵害の回避:使用可能な素材やライセンス条件を正確に確認。
・プライバシーポリシーの整備:依頼者の個人情報管理に関する規定を適切に策定。
・景品表示法や取引法への対応:依頼者が商品販売やマーケティング目的で制作する場合の法的要件を確認。
これにより、後々の訴訟や損害賠償リスクを大幅に軽減できます。
④ビジネスの信頼性を向上
弁護士のサポートを受けることで、クライアントとの信頼関係を構築しやすくなります。
特に、法的に整備された契約書や手続きにより、受託者の「プロフェッショナル性」をアピールできると共に、相手方に対して「法的にも適切に対応できる業者」という印象を与え、競争優位性を高めることが可能となります。
⑤業務効率の向上
トラブルが発生するたびに時間を割かれると、他のプロジェクトや顧客対応に支障が出ます。弁護士に相談することで、問題を効率的に解決し本業に集中できること、不必要な時間やコストの浪費を防止できることで、結果として、事業運営全体の効率が向上します。
リーガルブレスD法律事務所でサポートできること
当事務所は、複数のホームページ・WEB制作事業者の顧問弁護士として、日常的にホームページ・WEB制作に関する課題やトラブルに接し、対処法のご提案や代理人活動などの対応実績が多数あります。このため、実例を踏まえた数々の知見とノウハウを蓄積していますので、ご相談者様には経験に裏付けられた実践的なアドバイスをご提供することが可能です。
そして上記に加え、当事務所はさらに次のような特徴を有しています。
①専門知識に基づく理解
当事務所の代表弁護士は情報処理技術者資格を保有し、ホームページ・WEBに関する専門用語を把握しています。このため、相談しても弁護士が理解できない・理解するまで時間がかかるといった問題が生じません。
②カスタマイズされたサポート
企業の規模や業種に応じた法的サポートを提供し、それぞれのニーズに合わせた柔軟な対応が可能です。
③早期解決を目指す交渉力
トラブルが発生した場合、法廷外での早期解決を目指した交渉に尽力します。
なお、近時はIT導入補助金に関連するご相談事例が増加しています(委託者の立場であれば補助金の返還に関するご相談、受託者の立場であれば登録取消しに関するご相談など)。
手順を間違えると、かなり大きな事業損失となりますので、早急なご相談をお勧めします。
ホームページ・WEB制作に関する経営課題やトラブルでお悩みがあれば、是非リーガルブレスD法律事務所までご相談ください。