IT企業で事業譲渡を実行する場合のポイント
Contents
【ご相談内容】
当社はこれまでWEB制作のみを請負ってきましたが、WEBの活用法に関するコンサルティングサービスを追加することで付加価値を作り、同業他社との差別化を図る経営戦略を考えています。
そこで、某社のコンサルティング部門を買収しようと考えているのですが、どのような手段を用いればよいのか、手続きを進めるにあたって何に注意をするべきなのか等につき、アドバイスをお願いします。
【回答】
事業者の一部門のみを買収する手段としては、事業譲渡と会社分割の2つの手法が考えられます。ただ、会社分割は重い法律上の規制があるため、必ずしも使い勝手の良い制度ではありません。
そこで、本記事では事業譲渡を実行することを念頭に、手続きの流れや注意するべきポイントを解説します。
なお、以下の解説では、株式上場を行っている大企業ではなく、中小企業間での事業譲渡手続きを想定しています。
【解説】
1.事業譲渡とは
(1)意義・目的
事業譲渡の定義については諸説ありますが、現場実務では「会社の事業の全部又は一部を契約により他の会社・事業者に移転すること」という定義が一番しっくりくるように思います(ちなみに、最高裁判例によると、上記定義に加えて「譲渡人が競業避止義務を負うこと」を要件としていますが、おそらく現場実務では競業避止義務の有無によって事業譲渡該当性を判断していないと思われます)。
さて、上記定義にある「事業」ですが、一定の事業目的のために組織化され、有機的一体として機能する財産であり、事業を構成する物理的な財産だけではなく、得意先関係やノウハウといった無体財産などを含む、経済的価値のある事実関係を含むものとされています。このため、単に譲渡人が保有する工場建物を売渡すといった取引に留まるのであれば、それは不動産売買取引であって事業譲渡には該当しません。
事業譲渡が行われる目的ですが、典型的には事業の再生や事業承継のためが挙げられますが、IT業界に絞るのであれば、次の3点が考えられます。
①業界での人材不足を解消するため
IT業界は慢性的な人材不足であり、実際のところ人材募集を行っても人が集まらない、人材紹介会社を利用したくても紹介手数料が高すぎて利用できない、といった問題が発生しています。そこで、事業を譲り受けることでそこに紐づく人材を獲得するといったことが行われます。
②事業規模を拡大するため
近時はWEB制作事業者がインターネット広告事業に参入したり、システム開発事業者が保守運用業務に力を入れ始めたりといった、事業を多角化し付加価値をあげるという経営方針をとるIT事業者が続出しています。そこで、一から事業を作り上げるより、既に出来上がった事業を買い取ることで、手っ取り早く事業の多角化を実現するといったことが行われます。
③事業の内製化を図るため
IT業界は建設業界と同じく多重下請け構造になっています。たしかに、一口にIT事業と言っても各種専門分野があるため、専門分野ごとに事業者を割り当てて成果を実現することにも合理性はあります。しかし、近時は、例えば、多重下請け構造であるが故に委託者の管理監督が届かず、個人情報の漏洩事故が発生するといった負の側面も目立ち始めてきました。そこで、このような状況を改善するために、事業を買い取ってコントロール下に置くといったことが行われています。
(2)メリット・デメリット
事業譲渡は、複数あるM&A手法の1つに過ぎません。M&Aを実行する上で事業譲渡を選択するか否かについては、そのメリットとデメリットを押さえておくのが有用です。
【メリット】
・譲渡対象範囲を選択できること
譲渡人からすれば残しておきたい事業を選択でき、譲受人からすれば欲しい事業だけを選択できます。合併手続きのようなオールオアナッシングにならない点が事業譲渡の魅力となります。
・簿外債務を回避できること
DD(デューディリジェンス)を実施しても、譲渡人が抱え込むすべての債務を発見することは困難です。しかし事業譲渡の場合、事業の範囲を選択できることはもちろん、債務を承継するか否かについても選択することが可能です。つまり、譲受人は欲しいものだけ選択できるという点が事業譲渡の魅力となります。
・法定の手続き規制が少ないこと
事業を対象とするM&A手法には、事業譲渡以外にも合併や会社分割があります。ただ、合併や会社分割は債権者保護手続きが法律上義務付けられている点で負担が重く、機動性を欠くという難点があります。しかし、事業譲渡では、法定の債権者保護手続きが存在しないため、簡易に進めることができる点が事業譲渡の魅力となります。
【デメリット】
・資金が必要となること
事業譲渡の法的性質は売買となります。売買である以上、譲受人は売買代金を支払う必要がありますので、必然的にキャッシュアウトを伴います。このため、売買代金の捻出と資金繰りを考慮しなければならない点が悩ましいところとなります。
・実行手続きが煩雑となること
上記メリットの中で、債権者保護手続きが不要であることに触れました。たしかに、法定手続きが不要とされているのですが、一方で、事業譲渡は、その事業を構成する個々の財産の売買取引となるため、個別対応が必要となります。例えば、不動産であれば登記手続きを行う、債権であれば債権譲渡の通知を行う、契約上の地位の移転であれば取引先の承諾を得る、といった具合です。対象となる事業を構成する個々の財産が多ければ多いほど、関係各所との調整が必要となる点が悩ましいところとなります。
・税金が発生すること
事業譲渡は売買取引である以上、その対象となる事業に含まれる資産に課税対象がある場合は消費税を負担する必要があります。一方、合併手続きの場合、消費税は課税されません。譲受人にとっては思わぬ追加負担となり得る点が悩ましいところとなります。
(3)他のM&A手続きとの違い
事業者が保有する特定の一事業を取得する方法としては、事業譲渡以外にも会社分割があります。両手法の相違点は次の通りです。
| 事業譲渡 | 会社分割 | |
| 決定手続き | 譲渡人:株主総会特別決議(※)
譲受人:なし |
分割側:株主総会特別決議
承継側:株主総会特別決議 |
| 債権者保護手続き | 不要 | 必要 |
| 取引関係の承継 | 取引先の承諾が必要 | 取引先の承諾不要(但し、COC条項などに注意) |
| 労働関係の承継 | 個々の労働者の承諾が必要 | 労働者の承諾不要(但し、労働者保護手続きの実施要) |
| 財産の承継 | 個々の財産に応じて手続きが必要(不動産登記など) | 個々の財産に応じて手続きが必要(不動産登記など) |
| 許認可承継 | 不可 | 一部可(監督官庁に要確認) |
| 簿外債務 | 承継リスク小 | 承継リスク大 |
(※)譲渡資産の帳簿価額が総資産額の20%を超えない場合は株主総会特別決議が不要(会社法第467条第1項第2号)。また、現場実務では、売上高・利益・将来性・従業員数等の要素を総合的に考慮して、事業全体の10%程度を超えない場合は「事業の『重要な』一部」に該当しないとして、株主総会の特別決議不要として取り扱われることが多い。
なお、事業者が保有する全事業を取得する合併の場合も、上記表とほぼ同様となります(相違点としては、事業譲渡の決定手続きにおける譲受人の対応として、株主総会の特別決議が原則として必要となる点です。但し、簡易事業全部譲受及び略式事業全部譲受に該当する場合、株主総会特別決議は不要となります)。
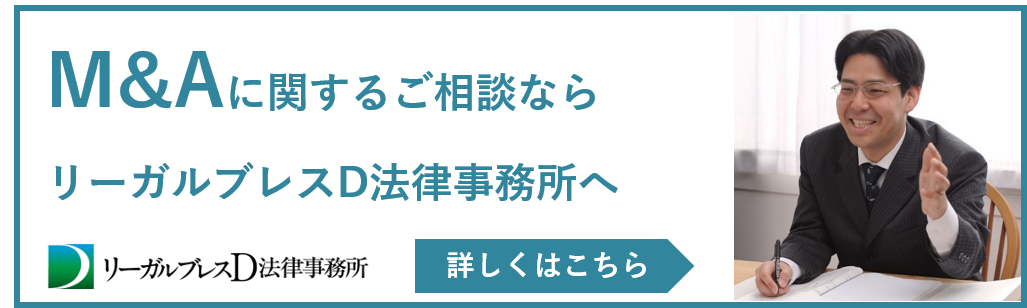
2.事業譲渡の手続き
中小企業同士で事業譲渡手続きを行う場合、一般的には次のようなフローとなります(取締役会設置会社を想定したフローです)。
(1)取締役会での報告
中小企業同士で事業譲渡の協議を進める場合、最初から社長(代表取締役)同士で協議を進めることも有りますが、担当役員が交渉を担う場合もあります。ただ、いずれの場合であっても、事業者に与えるインパクトが大きい交渉となりますので、職務の執行状況につき取締役会に報告を行うべきです(会社法第363条第2項)。
(2)事業譲渡に関する覚書
法律上作成が義務付けられている書類ではありません。ただ、ある程度規模の大きな事業譲渡契約の場合、譲渡人による売渡しの意向、譲受人による買受けの意向を表明する書類として、作成し締結する場合があります。
もちろん、この時点では詳細な取引条件が定まっていないため、交渉内容の秘匿性の確認、DD(デューディリジェンス)の条件、事業譲渡の対象となる事業の特定、従業員の処遇方針、譲渡価格などといった大枠を定めるだけに留まるのが通常です。
ちなみに、DD(デューディリジェンス)には、財務、税務、ビジネス、法務、労務など複数の分野がありますが、法務DDの場合、次のような事項を重点的に調査します。
| ①許認可
対象事業の運営にあたって必要な許認可や登録等の確認と譲受に際して必要となる手続きの把握。 ②資産 不動産であれば、権利関係の確認、担保設定の有無、第三者の使用権原の有無、境界紛争等の近隣関係、建築基準法や消防法等の法令順守状況の確認。 動産であれば、利用形態の確認、担保設定の有無、損害保険の内容などを確認。 知的財産権であれば、権利関係の確認、登録状況、ライセンスの内容、第三者侵害の有無などを確認。 ③負債 譲渡対象となる事業により発生する負債の内容と状況の把握。 ④契約関係 COC条項の有無、契約違反の可能性、契約期間などを把握し、継続性の可否につき確認。 ⑤人事労務 労働法規の順守状況、対象事業に従事する従業員との関係性、未払い賃金等の簿外債務可能性などを確認。 ⑥環境 産廃、有害物の取扱い状況、土壌汚染の可能性、行政からの指摘事項の確認。 ⑦紛争 現在進行形の紛争内容の把握と解決可能性、過去の紛争による影響度、潜在的な紛争の有無などを把握。 |
(3)事業譲渡契約書の作成
上記(2)の覚書締結後、協議を重ねていき、取引条件が整った段階で事業譲渡契約書を作成することが通常です。なお、事業譲渡契約書も法律上作成することが義務付けられているわけではありませんが、一般的には多額の金銭のやり取りが発生しますので、契約書を作成したほうが無難です。
事業譲渡契約書は、その取引条件に応じて内容が異なってきますが、最低でも次のような事項を定めているのが通常です。
| 第×条(事業譲渡)
譲渡人は、次条以下の条件に従って、●に関する事業(以下「本事業」という。)及び本事業に係る一切の財産(以下「譲渡財産」という。)を譲受人に譲渡し、譲受人はこれを譲り受ける(以下「本件譲渡」という。)。
第×条(譲渡日) 本件譲渡は●年●月●日(以下「本件譲渡日」という。)とする。
第×条(本件譲渡の対価および支払方法) 1 本件譲渡の対価(以下「本件対価」という。)は金●万円(消費税別)とする。 2 前項に定めた本件対価については、譲受人が一括にて譲渡人の指定する口座及び支払期日に振り込んで支払い、その振込み手数料は譲受人が負担する。
第×条(契約上の地位の移転) 1 譲渡人は、本事業に関する契約(以下「本承継契約」という。)に係る契約上の地位及びこれに基づく権利義務(但し、本件譲渡日において既に発生している債務及び本件譲渡日以前の原因に基づき本件譲渡日以後に発生する債務を除く。)を、本件譲渡日をもって従前と同一の取引条件で譲受人に承継させ、譲受人はこれを承継する。 2 譲渡人は、本件譲渡日までに、本承継契約にかかる契約上の地位の移転に必要な措置をとる。
第×条(従業員の取扱い) 1 譲受人は、譲渡財産に関する譲渡人の従業員(嘱託社員、契約社員、アルバイト、パートタイマー等正社員以外の者を含む。以下同じ。)のうち、本件譲渡日までに、譲受人への転籍について承諾し、転籍承諾書を提出した者(以下「承継従業員」という。)について、本件譲渡日をもって新たに雇用する。なお、承継従業員の労働条件は譲受人が定め、譲渡人による従前の労働条件は引き継がれない。
第×条 (競業避止義務) 譲渡人は、本件譲渡日以後●年間は、譲受人の事前の書面による承諾を得た場合又は本契約で別途定める場合を除き、自ら又はその親会社・子会社及び関連会社等を通じて、本事業と同一又は同種の事業その他譲渡財産と競合し又は競合するおそれのある事業に直接又は間接を問わず一切関与しない。但し、本契約締結日において既に譲渡人の親会社・子会社及び関連会社等が現に行っている事業についてはこの限りでない。 |
(4)取締役会の決議
取締役会は、事業譲渡の意思決定を行います(会社法第362条第4項第1号)。そして、①譲渡人において、譲渡対象が「事業の『重要な』一部」に該当する場合、②譲受人において、譲受対象が譲渡人の事業の全部に該当する場合、それぞれ株主総会の招集決議を行うことになります(会社法第298条第4項)。
(5)株主総会招集手続
2週間前までに株主総会の招集通知を発送すること、招集通知に議案の概要を記載することなど、一般的な株主総会招集手続きと同様です。
(6)株主総会の決議
特別決議が必要となります(譲渡人は会社法第467条第1項第1号及び同第2号、会社法第309条第2項第11号が根拠。譲受人は会社法第467条第1項第3号、会社法第309条第2項第11号が根拠)。
(7)反対株主の株式買取請求
事業譲渡に反対する株主が、会社法の定めに従って反対の意思表明を行った場合、会社は当該株主より、公正な価額で株式を買い取る必要があります(会社法第469条)。
(8)債権者との関係
上記1.(2)で解説した通り、事業譲渡を実施するに当たり、法定の債権者保護手続きは存在しません。
しかし、事業譲渡が濫用されるなどした場合、債権者が不利益を被ることが想定されます。
そこで、債権者は次のような手段を用いて、事業譲渡手続きに対抗してくる可能性があることを認識しておく必要があります。
①詐害行為取消権(民法第424条以下)
②破産管財人による否認(破産法第160条以下)
③法人格否認の法理(判例により形成された権利濫用の一類型)
④詐害的事業譲渡に係る譲受人に対する債務の履行請求(会社法第23条の2、商法18条の2)
⑤譲渡側の商号を続用した場合の譲受人に対する債務の履行請求(会社法第22条、商法17条)
3.対象事業に含まれる個々の財産に対する留意点
上記1.(2)で解説した通り、事業譲渡の法的性質は売買契約であり、事業譲渡の対象となる事業を構成する財産については、個別に譲渡手続きを行う必要があります。
主な財産の譲渡手続きにおいて留意したい点は次の通りです。
(1)不動産
移転登記を別途行う必要があります。
移転登記に要する費用をだれが負担するのかについて、忘れずに交渉したいところです。
(2)動産
原則的には、その動産を貰い受ければ足ります。
ただし、自動車などの登録制度があるものは移転手続きが、会員権等は名義変更手続きが、受取手形は裏書譲渡がそれぞれ別途必要となります。
(3)債権
確定日付のある証書による債権譲渡通知を行う必要があります。
(4)債務
併存的債務引受け(譲渡人は引き続き、譲受人は新たに債権者との関係で債務を負担するもの)であれば、特段の手続きは不要です。
一方、免責的引受け(譲渡人は負担を免れ、譲受人のみが債務を負担するもの)の場合、債権者の同意が必要となります。
なお、当然のことですが、譲受人は、譲渡人の債務を引き受けない(事業譲渡の対象から債務を除外する)ことも可能です。
(5)担保
譲渡人が担保権者である場合、債権の譲渡によって担保も移転するのが原則です。ただし、抵当権のような対抗要件を必要とする担保権については、抵当権の移転登記を別途行う必要があります。また、元本未確定の根担保については、担保権設定者の承諾を得る必要があります。
一方、譲受人が担保権設定者である場合、事業譲渡によって担保設定物件が移転したとしても、担保は付されたままとなります。譲受人において担保権の抹消を希望する場合、個別に債権者と交渉するほかありません。
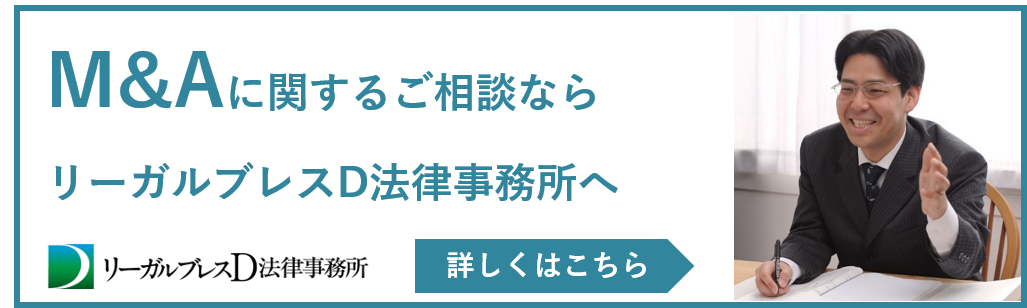
4.IT企業特有の注意点
上記1.から3.までは、IT業界だけに留まらない全業界に関係する内容となります。
ここでは、IT企業特有の問題として、システム開発業とEC事業の事業譲渡を行う場合の留意事項を解説します。
(1)システム開発業
システム開発業における資産といえば、スキルを有する技術要員に限られるといっても過言ではありません。もっとも、上記1.(3)でも解説した通り、技術要員(労働者・フリーランス)は、事業譲渡により当然に譲受人が取得できるわけではありません。このため、譲渡人に承継実現のための協力義務を課すなどして、技術要員の承継をいかにして実現させるのか工夫が求められます。
また、技術要員=人が資産である以上、譲受人は労務コンプライアンスの順守状況に気を配る必要があります。例えば、フリーランスとして従事させている者が労働者に該当しないか、時間外労働はどの程度発生しているのか、専門業務型裁量労働制は正しく運用されているか、偽装請負は発生していないか等々の事前調査を尽くし、偶発債務を承継する可能性がないかを十分に見極める必要があります。
さらに、IT業界は多重下請け構造となっているところ、中小企業間でも発注者・受注者の関係に立つことが珍しくありません。この場合、発注者が下請法を全く意識しておらず、必要な対策を講じていないということもあり得ますので、協力先等との取引条件が適正なのかについても、十分に確認したいところです(なお、2024年11月1日からはフリーランス法による取引適正化についても意識する必要があります)。
(2)EC事業
ここではEC事業の中でも、譲受人が運営する販売サイトが存在するパターンを想定します。
さて、EC事業における主たる資産といえば、顧客名簿となります。顧客名簿には個人情報が含まれていますので、個人情報保護法を意識する必要があるところ、個人情報保護法では事業譲渡による個人情報の承継は第三者取得に該当しないと定めています。したがって、法律上は、顧客の同意を得ることなく顧客情報を取得することが可能です。
ただ、その顧客情報をどこまで活用できるかは確認が必要です。
なぜなら、個人情報を活用するに際しては利用目的の範囲内で行うという制限がつくからです。譲受人が活用したいと考えている場面が、果たして譲渡人が定めている利用目的の範囲内に収まるのか、事前に確認することが重要となります。
次に、EC事業における顧客は、よほどのことがない限り消費者をターゲットとするのが通常であるところ、消費者と取引を行うのであれば、各種法令による規制を順守できているのかを確認する必要があります。例えば、特定商取引法に基づく表示は適切か、消費者契約法に則った利用規約が制定されているか、景品表示法等の広告表示規制が守られているか、資金決済法に基づく必要な措置が講じられているか等については、譲受人において実際のECサイトを検証しておきたいところです。
さらに、事業譲渡の対象となるEC事業の風評(炎上リスクを含む)についても、できる限り調査したいところです。なぜなら、譲渡人が運営していた時代での悪評であったとしても、顧客からすれば現在の運営者は譲受人である以上、譲受人が取扱う商品・サービス全体に対して疑念を抱くようになり、譲渡対象以外の事業分野にまで風評被害をもたらすリスクがあるからです。
なお、プラットフォーム内に出店してEC事業を運営する場合、事業譲渡によって運営に障害が発生しないか(典型的にはCOC条項によりプラットフォームの利用が制限されないか等)についても、忘れずチェックしたいところです。
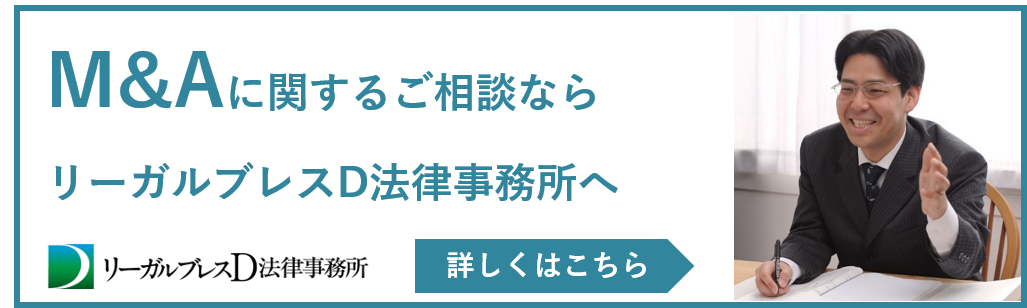
5.弁護士に依頼するメリット
事業譲渡は、単に契約を結ぶだけでなく、さまざまな法律的・実務的な問題を含む複雑なプロセスです。特にIT企業の場合、知的財産権やライセンス契約、顧客情報の取扱いなど、特有のリスクと配慮が求められます。これらの複雑な要素を管理し、適切な対応をするためには、弁護士の専門的なサポートが不可欠です。
弁護士に依頼することで、例えば、次のようなサポートを得ることができます。
①契約書の作成と確認
事業譲渡契約書は、譲渡する資産や知的財産、負債、顧客契約などの詳細を明記する必要があります。弁護士は、これらの内容を適切に盛り込み、法的に問題が発生しないよう確認します。
②デューディリジェンスの実施
譲渡する事業の評価やリスク分析を行い、譲渡先企業との条件交渉に必要な情報を整理します。これにより、潜在的な法的リスクや財務上の問題を事前に把握することが可能です。
③法的リスクの軽減
顧客データや個人情報保護に関する問題など、譲渡に伴う法的リスクを分析し、適切な対策を講じます。
また、弁護士と顧問契約を締結しておくことで、さらに次のようなサポートを受けることができます。
①継続的な法的サポート
譲渡のプロセス全体において、法律的な問題が発生した際に迅速に対応できる体制を整えることができます。特に、譲渡の交渉や契約内容に関する調整が必要な場合、顧問弁護士が即時対応できる点は大きな利点です。
②法改正への対応
IT業界は法改正が頻繁に行われる分野であり、個人情報保護法や労働法など、企業が遵守すべき法規制は多岐にわたります。顧問弁護士がいることで、これらの最新の法規制に即座に対応し、法的リスクを軽減することができます。
③ビジネス戦略への助言
事業譲渡の計画段階から弁護士と密に連携を取ることで、譲渡後のトラブルを未然に防ぎ、スムーズなPMIを実現することができます。
6.当事務所でサポートできること
当事務所の代表弁護士は情報処理技術者資格を保有し、IT業界との付き合いも多いため、IT業界特有の取引慣行や実情に関する深い知識と経験を持っています。また、IT業界内外での事業譲渡を含むM&Aにも数多くの実績があります。
上記以外にも、次のような強みとサポートを行っています。
①IT企業の顧問弁護士として多数の実績があること
当事務所の代表弁護士は、2001年の弁護士登録以来、複数のIT企業の顧問弁護士として活動し、紛争予防から訴訟対応まで幅広く関与し、解決を図ってきました。
これらの現場で培われた知見とノウハウを活用しながら、ご相談者様への対応を心がけています。
②時々刻々変化する現場での対応を意識していること
弁護士に対する不満として、「言っていることは分かるが、現場でどのように実践すればよいのか分からない」というものがあります。
この不満に対する解消法は色々なものが考えられますが、当事務所では、例えば、法務担当者ではなく、現場の交渉担当や実務担当者等との直接の質疑応答を可としています。
現場担当者との接触を密にすることで、実情に応じた対処法の提示を常に意識しています。
③原因分析と今後の防止策の提案を行っていること
弁護士が関与する前にトラブル対応を開始したところ、法的判断の誤りにより、ご相談者様が思い描いていたような結論を得られず、以後の対応に苦慮している場合があるかもしれません。
こういった場合に必要なのは、方針・対処法の軌道修正をすることはもちろんのこと、なぜ思い描いた結論に至らなかったのか原因検証し、今後同じ問題が発生しないよう対策を講じることです。
当事務所では、ご相談者様とのやり取りを通じて気が付いた問題点の抽出を行い、改善の必要性につきご提案を行っています。そして、ご相談者様よりご依頼があった場合、オプションサービスとして、社内研修やマニュアルの整備、契約書の常時チェックなども行っています。
事業の適正化とトラブル防止のための継続的なコンサルティングサービスもご対応可能です。
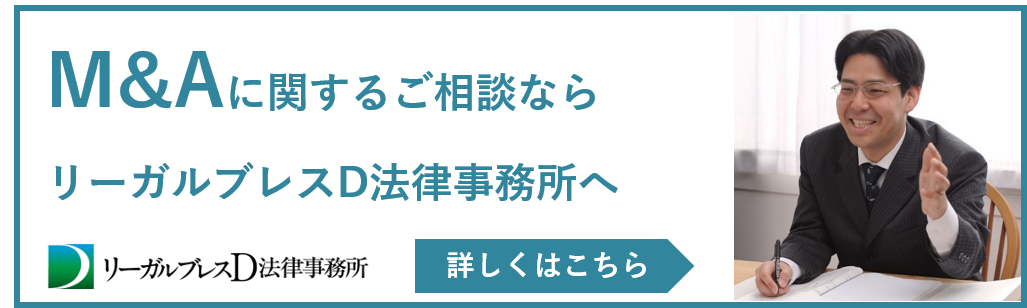
<2024年9月執筆>
※上記記載事項は弁護士湯原伸一の個人的見解をまとめたものです。今後の社会事情の変動や裁判所の判断などにより適宜見解を変更する場合がありますのでご注意下さい。


