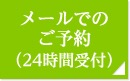「中途解約で泣き寝入りしない!」WEB制作の未払い報酬を回収する方法
Contents
- 【ご相談内容】
- 【回答】
- 【解説】
- 1.中途解約であっても報酬請求は可能か
- (1)可分な部分の給付
- (2)注文者が利益を受けるとき
- (3)利益の割合に応じた報酬(報酬額の算定方法)
- 2.一部報酬(≒出来高報酬)以外の請求は可能か
- (1)民法第641条に基づく損害賠償請求
- (2)民法第641条は簡単に発動しない?
- 3.中途解約をめぐる紛争の予防策
- (1)中途解約を禁止する
- (2)中途解約に際しては一定の予告期間を設ける
- (3)前払いにする
- (4)中途解約を念頭に置いた清算ルールを設ける
- (5)補足
- 4.中途解約をめぐるトラブルの解決事例
- 【相談企業の業種・規模】
- 【相談経緯・依頼前の状況】
- 【解決までの流れ】
- 【解決のポイント】
- 【解決までに要した時間】
- 【担当弁護士からの若干のコメント】
- 5.弁護士に依頼するメリット
- ①トラブルの早期解決
- ②法的リスクの回避
- ③交渉力の強化
- ④訴訟や強制執行への対応
- ⑤経営資源の有効活用
- 6.リーガルブレスD法律事務所における中途解約トラブル対応への強み
【ご相談内容】
WEB制作作業を行っていたところ、突如ユーザより、「今回の話はなかったことにしてほしい」として、WEB制作の打ち切りを通告してきました。
中途解約はやむを得ないとして受け入れたものの、当社としては、これまでの作業に見合った報酬の支払いは受けたいと考えています。
ユーザとはどのように交渉を進めていけばよいでしょうか。
【回答】
ご相談内容を踏まえると、WEB制作に関する請負契約が成立していたものと考えられます。
また、現時点ではWEB制作事業者に何らかの契約違反があったとは考えにくいように思われます。
そうであれば、作業遂行によって生じた成果物に応じた一部報酬を請求できる可能性が高いといえます。
以下では、一部報酬を請求できる法的根拠と注意点などを解説しつつ、実際にリーガルブレスD法律事務所で対応した事例なども取り上げながら、解決に向けたフローなどを紹介します。
【解説】
1.中途解約であっても報酬請求は可能か
WEB制作に関する契約は請負契約と考えられます。
そうすると、民法第632条では、「その仕事の結果に対してその報酬を支払うこと」が請負契約の要件となっている以上、WEBが未完成の状態の場合は報酬請求不可という結論にならざるを得ません。
しかし、2020年4月1日より施行された改正民法では、中途解約の場合であっても報酬の一部(≒出来高報酬)を請求できることが明文化されました。
民法第634条(注文者が受ける利益の割合に応じた報酬)
| 次に掲げる場合において、請負人が既にした仕事の結果のうち可分な部分の給付によって注文者が利益を受けるときは、その部分を仕事の完成とみなす。この場合において、請負人は、注文者が受ける利益の割合に応じて報酬を請求することができる。
①注文者の責めに帰することができない事由によって仕事を完成することができなくなったとき。 ②請負が仕事の完成前に解除されたとき。 |
本事例の場合、民法第634条第2号が適用できないかが問題となります。
具体的には「可分な部分の給付」と「注文者が利益を受けるとき」という2つの要件です。
(1)可分な部分の給付
取引実情にもよりますが、一般的なWEB制作では、①企画設計、②デザイン作成、③開発・コーディング、④納品という工程をたどります。
この工程を前提に「可分な部分の給付」とは何かを考えた場合、例えば…
・ワイヤーフレームが完成し、ユーザが了承している場合
・デザインが完成し、そのデータをユーザに引渡し可能な状態である場合
・HTML/CSSのコーディング作業が完了している場合
といった各工程における作業結果(成果)を提供できることが「可分な部分の給付」と考えられます。
要は、WEB制作の作業内容を細分化し、細分化された中で成果物が存在するのであれば、その成果物が「可分な部分」に該当するか、該当するのであればその成果物をユーザに「給付」可能かを検討することになります。
なお、上記では、分かりやすくするために工程を例に記述しましたが、実際に「可分」か否かは法的評価を伴います。WEB制作事業者が可分と考えても、法的には可分ではないという場面も想定されますので、必ず弁護士等の専門家に相談した上で判断するべきです。
(2)注文者が利益を受けるとき
上記(1)で「可分な部分の給付」を満たしたとしても、提供された成果物が注文者にとって無益なものであれば、民法第634条に基づく報酬の一部請求(≒出来高報酬)は認められません。
もっとも、ここでいう「利益」とは、注文者の主観で判断されるものではなく、客観的な判断です。例えば、デザインデータを注文者が受領しても、注文者だけでは活用しようがないので「利益」がないという判断にはなりません。他のWEB制作事業者に依頼すれば転用可能なデータであったというのであれば、注文者は「利益」を受けたことになります。
他にも、次のような場合は「注文者が利益」を受けたものと考えられます。
・WEBサイトのフロントエンド開発まで完了し、注文者側でそのコードを活用できる場合
・すでに納品されたHTMLやプログラムを活用して、他社に開発を続行させる場合
・制作済みのコンテンツを部分的に利用する場合
なお、「注文者が利益を受けるとき」という要件は、多分に法的評価を伴うものであり、往々にしてWEB制作事業者の考えと相反することがあり得ます。必ず弁護士等の専門家に相談した上で判断するべきです。
(3)利益の割合に応じた報酬(報酬額の算定方法)
上記(1)と(2)の要件を満たしたとしても、現場実務で頭を悩ませるのは「割合」をどのように算定するのかという点です。
民法第634条は抽象的に定めるのみであり、どこにも具体的な算定方法は定められていません。このため、過去の裁判例などを分析しながら「割合」を検討することになりますが、この点は弁護士等の専門家に相談することをお勧めします。
なお、一般論としては、「割合」を検討する上で、次のような事情を考慮することになります。
・進捗状況はどの程度か
(例えば、進捗率が算出可能であれば、報酬×進捗率で報酬額を算定するなど)
・一部成果物が完成物に占める割合はどの程度か
(例えば、デザイン制作がWEB制作の30%を占めるのであれば、報酬×30%で報酬額を算定するなど)
2.一部報酬(≒出来高報酬)以外の請求は可能か
(1)民法第641条に基づく損害賠償請求
上記1.では、WEB制作事業者の作業成果に見合った報酬の可否につき検討を行いました。
では、仮にWEB制作事業者に何らの責任がないにもかかわらず、ユーザが一方的に契約を解消した場合、WEB制作事業者は契約を遂行することで本来得られた利益(逸失利益)や、無駄になった経費(例えば、サーバ代や外注費など)を請求することができないかが次の問題となります。
この点、民法第641条では、次のように規定されています。
民法第641条(注文者による契約の解除)
| 請負人が仕事を完成しない間は、注文者は、いつでも損害を賠償して契約の解除をすることができる。 |
民法第641条は、ユーザがWEB制作事業者に対して損害賠償義務を負うという書き方になっていますが、裏を返せば、WEB制作事業者はユーザに対し、民法第641条に基づいて損害賠償請求が可能ということになります。
そして、ここでいう「損害」は、逸失利益や無駄になった経費も含まれますので、結論としては請求が可能になります。ただし、中途解約されたことで、WEB制作事業者が本来負担するはずであった費用の支出を免れている以上、その分は損害より控除されることになります。
ちなみに、作業成果に見合った報酬について、民法第634条に基づき請求できる場合があることを上記(1)で解説しましたが、作業成果に見合った報酬相当額の損害を被ったとして、民法第641条に基づき損害賠償請求することも理論的には可能です(その場合、当然のことながら民法第634条に基づく一部報酬請求はできません)。
ただし、民法第634条は、契約の解消につきWEB制作事業者に責任がある場合であっても報酬の一部請求(≒出来高報酬)を可能とする清算ルールを定めた規定であるのに対し、民法第641条は、WEB制作事業者に責任がない場合のみ適用がある一種の制裁規定です。
このため、次の(2)で解説するように、現場実務では民法第641条が適用されるのかを巡って双方の見解に隔たりが生じることが通常ですので、安易に民法第641条のみを根拠とするのは危険です。
法的な落とし穴と言うべき内容ですので、WEB制作事業者がユーザに対して、何をどこまで請求するのかを検討する場合は、やはり弁護士等の専門家に相談することをお勧めします。
(2)民法第641条は簡単に発動しない?
上記(1)でも触れましたが、現場実務ではユーザより…
・WEB制作事業者がユーザの要望に従った作業を行っていない以上、むしろWEB制作事業者に契約違反があり、民法第540条以下に基づく解除である。
・WEB制作事業者の作業に不備がある以上、契約不適合責任に基づく解除である(民法第562条)。
・WEB制作契約に定められた解除権の行使である。
といった主張が展開され、民法第641条に基づく解除なのかを巡って論争となることが多いように思われます。
WEB制作事業者としては、上記のようなユーザの主張に反論できるよう、例えば、
・請負った作業内容の特定(提案書、仕様書、契約書などの確保)
・作業の遂行状況を示す資料等の収集(報告書、打ち合わせ内容の録音・録画データ、メールやチャット等のやり取り履歴の確保など)
・ユーザの主張内容の整理(主張に矛盾や変遷がないか等の確認)
を準備しておくことが重要です。
3.中途解約をめぐる紛争の予防策
上記1.及び2.では、中途解約に伴う紛争となった場面で、WEB制作事業者がどのように対応するべきかを検討しました。
しかし、可能な限り紛争を抑止することが、双方にとって有用です。
そこで、たとえ中途解約の申入れがあったとしても、淡々粛々と対処できるよう事前ルールを整備することが、予防策のポイントとなります。
様々な方法が考えられますが、ここでは4つ挙げておきます。
(1)中途解約を禁止する
そもそもの根幹を断ち切ってしまうという事前予防策となります。
例えば、WEB制作に関する契約書に次のような条項を定めておくことが考えられます。
(条項例)
| 委託者は、本契約に別途定める場合を除き、本契約を解約することができない。 |
ただ、ユーザがWEB制作を不要と考えているにもかかわらず、実際に制作を続けても社会経済的には無意味です。また、WEB制作事業者としても、せっかく制作したWEBが委託者の都合で公開されないとなると、達成感を得られない等の心理的な問題が生じるかもしれません。さらに、法的に許されるものではありませんが、ユーザが不要と判断したものに対して支払いを渋る可能性も否定できません。
したがって、理論的には中途解約を禁止するという予防策は考えられるものの、現実的な対応とは言い切れないところがあります。
もし、中途解約を禁止する旨の条項を設定するのであれば、例えば、「××の工程に至った場合は中途解約を禁止する」、あるいは「本契約成立後、×ヶ月以内は中途解約を禁止する」といった部分的なものに留めたほうが良いのかもしれません。
(2)中途解約に際しては一定の予告期間を設ける
中途解約それ自体を禁止することが難しい場合、中途解約は認めるにしても、一定の予告期間を経過しない限りは契約解消の効果が生じないとする事前予防策を講じることが考えられます。
これは、突如解約されるとWEB制作事業者に想定外の損害が発生することから、一定の予告期間を設けることで損害の発生を抑止できるようにすることで、ソフトランディングを図ろうとするものです(要は、WEB制作事業者において損害発生の抑止策を講じられるよう機会を付与するという意味です)。
例えば、WEB制作に関する契約書に次のような条項を定めておくことが考えられます。
(条項例)
| 委託者は、×ヶ月の予告期間をもって受託者に書面で通知することにより、本契約を中途解約することができる。 |
もっとも、WEB制作事業者としては、将来的な損害発生を抑止できるとしても、無駄となった作業分については適切に清算して欲しいと考えるのではないでしょうか。
このため、一定の予告期間を設けて中途解約を可能とするという事前予防策だけでは不十分であり、後述の(4)で解説する清算ルールの明記とセットで契約書の整備を図る必要があります。
(3)前払いにする
中途解約においてトラブルになるのは、WEB制作事業者が適切な報酬を得られていないからです。
そうであれば、民法第633条では「報酬は、仕事の目的物の引渡しと同時に、支払わなければならない。」と後払いがルールとされているものの、双方合意の上で前払いとする特約を定めておけば、事前予防策になり得ます。
例えば、WEB制作に関する契約書に次のような条項を定めておくことが考えられます。
(条項例)
| 委託者は受託者に対し、本契約の成立と同時に報酬金×円を支払う。 |
ちなみに、当然のことながら、中途解約となった場合、WEB制作事業者は前払い金を返還する必要があります(なお、特約で全額返金しないと定めておくことも原則有効と考えられます)。
返還額を巡ってトラブルになる可能性はあるものの、WEB制作事業者は既に報酬を確保している以上、非常に有利な立場と言えます。
ただ、前払いと定めることができるか否かは、ユーザとの関係性次第と言わざるを得ませんし、前払いにこだわり過ぎて取引を見送られてしまっては元も子もありません。
したがって、理想的な予防策ではあるものの、現実的には利用しづらいところがあります。
なお、全額前払いではなく、システム制作でいう多段階契約を参照して、WEB制作の工程を細分化し、各工程が開始するごとに報酬の一部を支払うといった分割して前払いしてもらうといった方法であれば、ユーザの抵抗感を減らすことができるかもしれません。
(4)中途解約を念頭に置いた清算ルールを設ける
おそらく一番現実的な予防策ではないかと考えられます。
ただ、現実的ではあるのですが、具体的な清算ルールをどのように設定すればよいのかとなると、実は悩ましいという問題を抱えています。
様々なバリエーションが考えられますが、例えば、WEB制作に関する契約書に次のような条項を定めておくことが考えられます。
(条項例)
| 本契約が終了した場合、委託者は受託者に対し、次の各号に従って算出された金額を清算金として支払う。
①受託者が企画設計業務を開始し、当該業務が終了するまでの間に本契約が終了した場合は、報酬額に×%を乗じた額 ②企画設計業務が完了し、受託者がデザイン制作業務を開始し、当該業務が終了するまでの間に本契約が終了した場合は、報酬額に×%を乗じた額 ③企画設計業務及びデザイン制作業務が完了し、受託者が開発・コーディング業務を開始し、当該業務が終了するまでの間に本契約が終了した場合は、報酬額に×%を乗じた額 |
上記条項例は、WEB制作における工程に応じて割合を定めることで清算する内容となっています。
これ以外にも、形式的に「違約金として×円を支払う」といった清算ルールを定めることも考えられますし、他にも「全体の制作期間を分母、経過期間分を分子とした料率に法数学を乗じて算出する」といった清算ルールなども考えられます。
一義的な清算ルールがないため、かえって契約書に定めづらいというWEB制作事業者からの声もあるのですが、トラブル回避のためにもここは踏ん張って契約書に落とし込みたいところです。
なお、契約書の作成は、高度な専門知識を要しますので、可能な限り弁護士に相談しながら進めていくべきです。
(5)補足
本事例のように、ユーザより当初と異なる要望事項が出たことで、WEB制作事業者の対応が難しくなり、結果的に中途解約トラブルになってしまったというパターンは後を絶ちません。
こういったトラブルを防止するためには、
①契約時に作業範囲を確定する。作業範囲の確定が難しいのであれば、確定している作業内容、別途協議して定める作業内容、対象外の作業内容を契約書に明記する。
②仕様変更などの要望が出た場合、変更ルールを契約書に明記する(変更ルールに従わない要望にWEB制作事業者は応じる必要がない旨明記する)。
といった工夫を盛り込むこともポイントとなります。
4.中途解約をめぐるトラブルの解決事例
【ご相談内容】に記載した事例ですが、リーガルブレスD法律事務所では、例えば次のような対応実績があります。
【相談企業の業種・規模】
■業種:IT(WEB制作)
■規模:10名以下
【相談経緯・依頼前の状況】
WEB制作に関する契約を締結し、コンテンツ等の制作作業を順次進めていたところ、ユーザよりページ追加や機能変更などの多くの要望が出てきたため、契約書で定めた金額では要望を満たすことができない旨の説明を行った。
そうしたところ、ユーザは一方的にWEB制作に関する契約を解約すると主張し、以後一切の交渉に応じなくなった。
当社としては、契約を終了させること自体はやむを得ないと考えているものの、作業内容に応じた清算を行って欲しいと考えている。法的に認められるものなのか教えてほしい。
【解決までの流れ】
ユーザの要望事項が、WEB制作に関する契約に定める受託業務内容に含まれている場合、ベンダが業務の遂行を拒絶したことになりかねないことから、まずは契約締結時点での業務内容を確定するべく、契約書以外にも仕様書や提案書などの関係書類をご準備いただくようお願いした上で、第1回目の法律相談に臨みました。
この点、ユーザの要望事項は、契約締結時点での業務内容に含まれていないことが確認できました。そこで、ご相談者様の責任のない事情により解約となっている以上、損害賠償を請求できる可能性が高いこと、もっとも法律上の損害を算定する上で、作業分に相当する額をどのように算定するのかやや厄介な問題があること、損害の算定に当たっては別の考え方もあること等をご説明し、一度持ち帰って検討していただくことになりました。
数日後、ご相談者様より、弁護士名義で損害賠償の支払いを求める内容証明郵便を出してほしいとのご要望を受け、今後の方針等を確認するべく、第2回目の法律相談に臨みました。
第2回目の法律相談の際、損害算定に関係する資料を検証すると共に、ユーザが万一支払ってこない場合の対処法につき協議を行ったところ、訴訟やむなしという結論に至りました。
この方針を踏まえ、弁護士名義の通知書をユーザに送付しましたが、支払いもなく無反応であったことから、即時に訴訟を提起しました。
ユーザは様々な主張を展開してきましたが、あまり裁判官には響かなかったようで、裁判官は一定額の支払いはやむを得ないという心証を開示しました。これを踏まえ、和解手続きに入り、最終的には一定額の支払いを受けることで和解解決を図ることになりました。そして、和解金の支払いが行われたことを確認し、弁護士による作業は完了となりました。
【解決のポイント】
弁護士に委託し裁判まで行うとなると、どうしても費用対効果の問題を考えざるを得なくなります。
本件では、その点を考慮しつつも、泣き寝入りは避けたいというご相談者様の強い意向があったことから、訴訟提起という手段を用いることで、逃げ切ろうとする相手方を表舞台に引っ張り出すことができたことが解決のポイントとなりました。
【解決までに要した時間】
約1年(第1回目の法律相談から、和解金の支払い完了まで)
【担当弁護士からの若干のコメント】
法律論としては、損害賠償請求権が成立するのかという責任論と、法律上の損害及び損害額を立証できるのかという損害論の両方を検証する必要があります。
また、本件のようなWEB制作、あるいはシステム開発といったIT業界は、独特の取引実情とこれに応じた裁判理論が形成されており、専門性の強い領域となります。
リーガルブレスD法律事務所は、複数のベンダの顧問弁護士として活動しており、裁判はもちろん交渉案件等を通じて獲得した知見とノウハウを多数保有しています。そして、ご相談者様にこれらの知見とノウハウを積極的に活用することで、実践的なアドバイスとご提案を行うよう努めてまいります。
中途解約による報酬清算問題にお悩みであれば、是非当事務所にお声掛けください。
5.弁護士に依頼するメリット
ビジネスを進める上で、契約トラブルや未払い問題、取引先との交渉難航など、法的な問題に直面することは少なくありません。こうした問題を適切に解決し、企業の利益を守るためには、弁護士への相談・依頼が重要です。
弁護士に相談・依頼するメリットは次の通りです。
①トラブルの早期解決
法的問題は、対応が遅れるほど解決が難しくなり、損害が拡大することもあります。弁護士に相談することで、早期に適切な対応策を講じ、リスクを最小限に抑えることが可能です。
②法的リスクの回避
契約書の作成や内容のチェックを弁護士に依頼することで、不利な条項を事前に防ぎ、将来的なトラブルを未然に防ぐことができます。特に専門的な業界では、適切な契約が企業の安定経営につながります。
③交渉力の強化
相手方との交渉において、法的知識に基づいた主張ができるかどうかは、結果を大きく左右します。弁護士を通じた交渉は、相手に対する説得力やプレッシャーを高め、有利な解決へと導く力を持っています。
④訴訟や強制執行への対応
万が一、交渉が決裂し法的手続きが必要になった場合でも、弁護士が対応することで、的確な主張や証拠の整理を行い、裁判での勝訴や適切な解決を目指すことができます。
⑤経営資源の有効活用
法的な問題に時間と労力を割くことは、本業に集中する妨げになります。弁護士に依頼することで、法務対応を専門家に任せ、企業活動に専念できる環境を整えることができます。
「こんなこと相談してもいいのか?」 と思われるかもしれませんが、法的な問題は小さな疑問や違和感から生じることが多いものです。
「トラブルが発生してから」ではなく、「トラブルを防ぐために」早めのご相談をおすすめします。企業の健全な発展を支えるため、ぜひ弁護士の活用をご検討ください。
6.リーガルブレスD法律事務所における中途解約トラブル対応への強み
IT業界、とりわけWEB制作やシステム開発の案件では、契約途中での仕様変更や追加要望により、報酬請求や契約解除のトラブルが発生することが少なくありません。
しかし、適切な法的対応を行うことで、不当な契約解除に対して正当な報酬を確保することが可能です。
リーガルブレスD法律事務所では、今回の事例のように、
・契約内容の精査を通じて、請求可能な範囲を明確化
・損害賠償の可能性について法的見解を提供
・交渉や訴訟を通じて、適切な金額の回収を実現
といった支援を行い、ご依頼者様の権利を守るための戦略を共に考えます。
なお、代表弁護士は情報処理技術者資格を保有しています。、また、リーガルブレスD法律事務所では、多数のトラブル事例に対応したことでIT業界に特化した知見を持っています。これにより、
・業界特有の取引慣行を踏まえた法的主張
・相手方の出方を想定した実践的な解決策をご提案
が可能となり、ご相談者様が不当な損害を被らないよう徹底サポートいたします。
泣き寝入りせず、正当な報酬を確保するために、ぜひ一度ご相談ください。
ご相談は早い段階で行うほど、有利な選択肢を確保できます。
<2025年3月執筆>
※上記記載事項は弁護士湯原伸一の個人的見解をまとめたものです。今後の社会事情の変動や裁判所の判断などにより適宜見解を変更する場合がありますのでご注意下さい。
- 「中途解約で泣き寝入りしない!」WEB制作の未払い報酬を回収する方法
- 利用規約とは?作成・リーガルチェックのポイントについて弁護士が解説
- なぜテンプレートの利用規約はダメなのか?弁護士が教えるテンプレートの落とし穴
- 契約書のAIレビュー・チェックだけで万全!? 弁護士のリーガルチェックとの異同を解説
- アプリ事業者必見!スマホソフトウェア競争促進法で変わるスマホ市場の競争環境
- 知らないと危険!SNS運用代行で法的トラブルを防ぐ契約書のポイント
- サイバー攻撃による情報流出が起こった場合の、企業の法的責任と対処法とは?
- システム開発取引に伴い発生する権利は誰に帰属するのか
- 押さえておきたいフリーランス法と下請法・労働法との違いを解説
- システム開発の遅延に伴う責任はどのように決まるのか?IT業界に精通した弁護士が解説