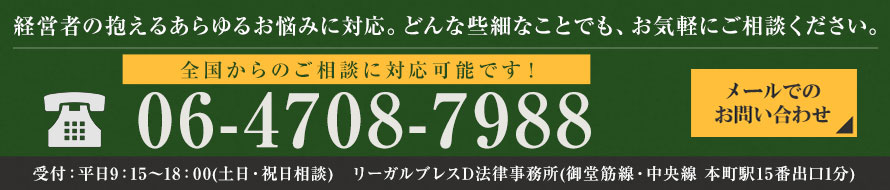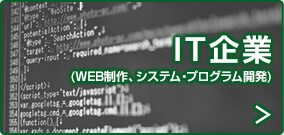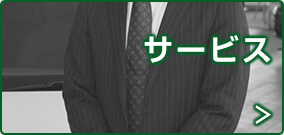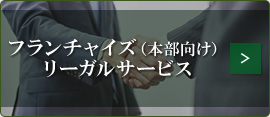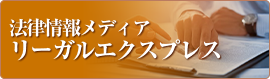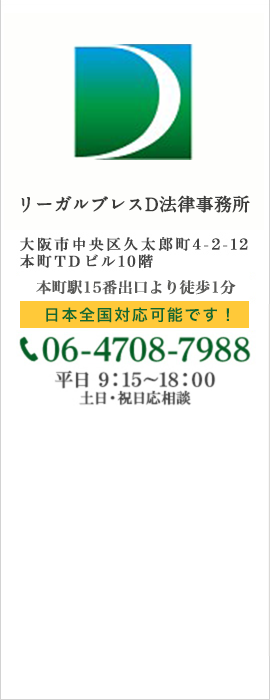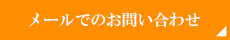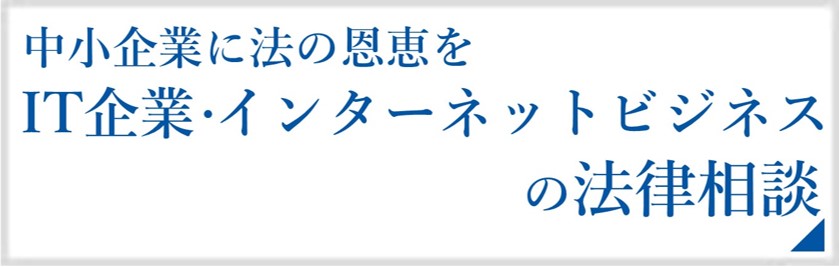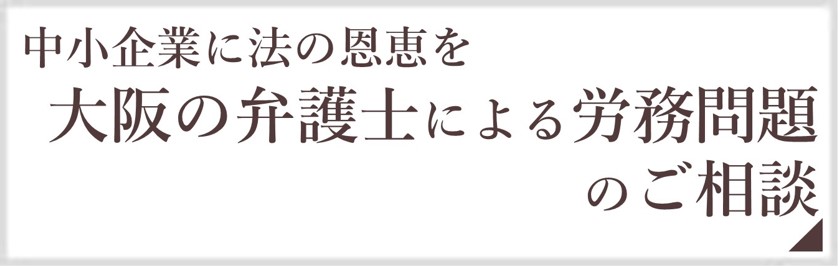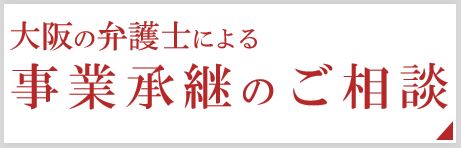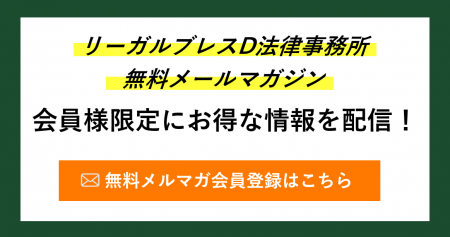経営権・支配権争いは悲劇の始まり! その原因と回避策を弁護士が解説
【ご相談内容】
当社創業者である会長の死去に伴い、後継者で現場を取り仕切る長男と、一定の株式を保有する配偶者・次男との間で経営方針の食い違いが表面化し、一触即発の状態となっています。
これ以上の紛争化を回避する方法や、紛争化した場合の対処法などを教えてください。
【回答】
いわゆるお家騒動と呼ばれるものとなります。
この種の紛争の場合、誰が経営権を握ることができるのか、支配権を持つのは誰なのかに焦点が当たりがちであるところ、実は法律上は経営権や支配権といった用語は用いられていません。
一般的には、経営権とは会社を思い通りに動かす経営者の権限、支配権とは会社の意思決定に及ぼす影響力という意味で用いられることが多いようですが、法的にはどちらについても多数の株式を保有する者が経営権も支配権も有することになっています。したがって、経営権・支配権をめぐる紛争は、株式を取得し、多数派を築き上げることで終結することが可能となります。
本記事では、経営権・支配権紛争が発生する具体的な原因に触れつつ、その回避策として株式の取得方法や多数派の構築の仕方につき解説を行います。また、紛争化した場合、どのような権利行使が行われるのか、この権利行使に対してどういった対抗措置が考えられるのかについてポイントを解説します。
【解説】
1.経営権・支配権紛争が発生する原因及び影響
非上場会社・中小企業における経営権・支配権争いは、上場企業とは異なる特徴を持ちます。特に創業者、オーナー家、共同経営者、親族、従業員株主などの間で発生しやすく、企業の存続や成長に大きな影響を及ぼします。
(1)経営権・支配権争いの原因
様々な原因が考えられますが、非上場会社・中小企業を対象とした場合、次の5つが主な原因と考えられます。
①創業者の後継者問題(事業承継トラブル)
例えば、創業者が経営権を手放したくないため後継者への権限移譲が進まない中、複数の親族(兄弟や親戚など)が後継者の席を巡って争いとなっていたところ、創業者が死亡したことで、経営権・支配権争いが勃発するというパターンです。
他にも、創業者が後継者として親族外の者を指名したものの、創業者の親族がこの指名に反対し、経営権・支配権争いが表面化するというパターンもあります。
②共同創業者や役員の対立
例えば、創業時は協力関係が維持できたものの、企業の成長とともに経営方針の違いが表面化し、主導権を取るために経営権・支配権争いが勃発するというパターンです。
他にも、出資比率や経営の貢献度を巡る不満(例:自分のほうが貢献しているのに報酬が低い)、あるいは共同創業者の一人が会社を乗っ取ろうとすることで経営権・支配権争いが表面化するというパターンもあります。
③株主間の対立(持株比率の変化)
例えば、株式が分散化し複数の株主が存在する状況下において、もともと友好的だった株主が経営陣の方針に反発し、経営改革の一環として経営権・支配権争いが勃発するというパターンです。
他にも、事業資金を提供した際に株式を取得した外部株主による経営介入、あるいは従業員持株制度を導入したことで経営者と従業員株主との対立による経営権・支配権争いが表面化するというパターンもあります。
④経営陣の不正・ガバナンス問題
例えば、資金の私的流用、粉飾決算、不透明な取引などが発覚し、他の役員や株主が代表者を責任追及する一環として経営権・支配権争いが勃発するというパターンです。
他にも、創業者のワンマン経営が続き、他の役員や従業員の不満が爆発したことで経営権・支配権争いが表面化するというパターンもあります。
⑤M&Aや出資を巡るトラブル
例えば、事業拡大のために外部企業や投資家からの出資を積極的に受け入れたことで創業者の持株比率が低下していたところ、これに乗じて経営権・支配権争いが勃発するというパターンです。
他にも、買収された企業の旧経営陣と新経営陣の対立により、経営権・支配権争いが表面化するというパターンもあります。
(2)経営権・支配権争いによるデメリット・悪影響
紛争が生じた場合、何らかのデメリット・悪影響は避けられませんが、経営権・支配権争い特有のデメリット・悪影響としては、次のようなものが考えられます。
①会社の経営が混乱し、業績が悪化
例えば、経営陣同士が争っている間に事業戦略の決定が遅れ、競争相手に市場シェアを奪われるといった悪影響が生じます。
他にも、現場の従業員が混乱し、業務効率が低下するといったこともあります。
②取引先や金融機関の信用を失う
例えば、金融機関が正常な経営状態ではないと判断した場合、融資条件を見直す、追加融資を拒絶するといった悪影響が生じます。
他にも、取引先が「この会社は大丈夫か?」と不安になり、取引関係の見直しや取引を縮小するといったこともあります。
③社内の人間関係が悪化し、優秀な人材が離れる
例えば、経営陣の派閥争いが激化することで、従業員の士気やモラルの低下、職場秩序の混乱といった悪影響が生じます。
他にも、優秀な従業員が退職し、競合企業に流出するといったこともあります。
④訴訟や法的トラブルのリスク
例えば、経営権・支配権を巡るトラブルが訴訟や株主代表訴訟に発展することで、会社の資金が訴訟費用に充当され、財務状況が悪化するといった悪影響が生じます。
他にも、長期的な法廷闘争により、会社の評判が悪くなるといったこともあります。
⑤相続トラブルによる会社の分裂・崩壊
例えば、事業承継がうまくいかず、親族間で争いが発生することで、会社が分裂する、最悪の場合は売却や廃業に追い込まれるといった悪影響が生じます。
2.予防策(株式の集中)
経営権・支配権争いが発生するのは、経営権・支配権を獲得できていないからです。
したがって、経営権・支配権争いを予防する最良の策は、経営権・支配権の源泉である株式を多く取得し、多数派を形成することになります。
株式の取得方法には様々なものが考えられますが、非上場会社・中小企業の場合、次のような方法が考えられます。
(1)任意での買取り交渉(既存株主からの株式買取)
会社や経営者が既存の株主と交渉し、株を買い取る方法となります。
例えば、創業者が高齢になり、後継者に経営権・支配権を譲ろうとする場面において、後継者が創業者より株を買い取るといったことが行われます。あるいは退職する役員や従業員が持っている株式の外部流出を防止するべく、経営者が当該株式を買い取るといったことが行われます。
この方法の注意点としては、非上場会社・中小企業の場合、定款で「株式の譲渡には取締役会の承認が必要」などの譲渡制限が通常設定されているため、この承認が得られるのかに留意する必要があります。また、非上場会社・中小企業の株式は市場価格が存在しないため、売買代金の設定が難しい(特に税務負担を意識する必要あり)という点にも留意する必要があります。
(2)自己株式の取得(会社が自社の株を買い戻す)
会社自らが株主より株式を買い取る方法となります。会社が保有する株式は議決権を行使できないため、経営者の持ち株比率を相対的に増やすことができます。
例えば、親族経営の会社で、相続対策として相続人が持つ株を会社が買い戻すといったことが行われます。
この方法の注意点としては、自己株式を取得するだけの資金が必要となること、会社法上の財源規制をクリアする必要があること、株主総会の特別決議が必要となるといった点に留意する必要があります。なお、自己株式の取得は自己資本の減少を招くことから、金融機関などが設定している与信に影響を及ぼさないかも事前に確認する必要があります。
(3)相続人等に対する売渡請求(会社が強制的に株を買い取る)
会社法第174条以下の規定に従い、株主の相続人に対し、会社が強制的にその株式を売渡すよう請求することで、株式を取得する方法となります。
この方法の注意点としては、上記(2)の自己株式取得に関する注意点がそのまま当てはまりますが、さらに注意するべき事項として、事前に定款に売渡請求ができる旨定めておく必要があることに留意が必要です。
(4)スクイーズアウト(少数株主を排除する)
ときどきニュースなどでこの言葉を聞いたことがあるかもしれませんが、別に上場企業だけで行われる方法ではありません。これは、会社法を活用して、少数株主より強制的に株式を買い取る方法となります。
例えば、経営者が90%以上の株式を保有しているのであれば、会社法第179条以下に基づく株式売渡し請求権を行使することでスクイーズアウトを実施することがあります。また、株式を併合し、招集株主が保有する株式を端株にした上で、その端株を会社が買取ることでスクイーズアウトを実施することがあります。さらに、発行株式を全部取得条項付株式に変更し、会社が株式を買い上げることでスクイーズアウトを実施することもあります。
これらの方法の注意点としては、買取り資金の確保はもちろんのこと、いずれも会社法に関する専門的な知識と手続きの実施が必要不可欠となることに留意する必要があります。また、少数株主が買取り価格に不満を表明した場合、訴訟に発展するリスクが高くなる点も留意する必要があります。
(5)募集株式の発行(新株発行による議決権強化)
会社が新規で株式を発行し、経営者又は経営者の意向に従う者が株式を取得することで、議決権を増やす方法となります。
この方法の注意点としては、会社法の手続きに従う必要があること(取締役会又は株主総会の決議など)はもちろん、議決権の希薄化の影響を受ける他の株主の反発を招かないか、法廷闘争となった場合に株式発行の正当性を証明できるのかといった点に留意する必要があります。
(6)種類株式(議決権のコントロール)
これは色々なことが考えられますが、例えば、黄金株と呼ばれる1株で拒否権を持つ株式を経営者が保有することで、決定権を維持する方法となります。
この方法の注意点としては、会社法に従った複雑な手続きや要件を満たす必要があるため、会社法に必ずしも明るくない経営者が実施した場合、有効性を担保できないリスクが高い点に留意する必要があります。
(7)定款による属人的株式(特定の人だけ議決権を強くする)
これについても色々なことが考えられますが、例えば、経営者が保有する株式のみ、1株を10議決権にするといった取り決めを行うことで、決定権を維持する方法となります。
この方法の注意点としては、上記(6)と同様となります。
(8)従業員持株会(会社の支配権を強化するための仕組み)
会社の従業員が自社の株式を持つための制度を構築し、経営者の意向に近い人々(従業員)に株式を持たせることで、経営権の安定を図る方法となります。
この方法の注意点としては、従業員持株会の設立・運営にコストを要すること、従業員に対して参加動機を促すことが難しい場合があること、ルールを整備すること(従業員が退職する場合は会社が買い戻すなど)、労使関係に問題が発生した場合は経営者に反対する株主に転嫁する恐れがあることなどに留意する必要があります。
3.少数派(少数株主)による権利行使と経営者の対抗措置
経営権・支配権争いが激化した場合、法的措置の応酬となることが多いのですが、ここでは代表的な法的措置を挙げておきます。
(1)臨時株主総会の招集請求(経営陣の不正追及)
議決権の3%以上を持つ株主は、取締役に対して臨時株主総会の招集を請求できます。
株主総会を通じて、経営者の不正行為を指摘し、経営者以外の株主の賛同を得ることで、経営権・支配権争いを有利に進めようとすることが考えられます。
これに対し、経営者は、招集権の濫用であることを指摘しつつ、法廷闘争に持ち込みながら時間を稼ぎ、一方で株主総会の開催を見込んで、自らが多数派となるべく他の株主への働きかけを行うといった対抗措置を検討することになります。
なお、株主総会の招集請求があった場合の処理方法については、次の記事を参照してください。
株主総会の開催要求があった場合の処理方法について、弁護士が解説!
(2)株主提案権
6ヶ月前より議決権の1%以上等の要件を充足する株主は、株主総会で議案を提出できます。
例えば、新たな取締役の選任議案を提出し、株主総会での議案審議過程において、経営陣の問題行動による会社へのダメージを指摘し、経営陣以外の株主の賛同を得ることで、経営権・支配権争いを有利に進めようとすることが考えられます。
これに対し、経営陣は、自らが多数派となるよう他の株主に働きかけることで議案を否決するといった対抗措置を検討することになります。
(3)法的責任追及措置(株主代表訴訟、取締役の第三者責任など)
経営者による不正行為や、会社の運営に問題がある場合、少数株主であっても株主代表訴訟(会社法第847条以下)や取締役の第三者責任(会社法第429条)の追及などを行うことができます。
なお、株主代表訴訟は会社が被った損害を取締役に賠償させる制度、取締役の第三者責任は株主が被った損害を取締役個人に賠償させる制度です。
これに対し、経営者は、自らの行動に不正はないとして、訴訟対応を行うことになります。
(4)株式買取請求
会社の重要な方針(組織再編など)に反対した株主は、会社に株式の買い取りを求めることができます。経営権・支配権争いから一歩引くことにはなりますが、経済的利益を確保するために用いられる方法となります。
これに対し、経営者は、株式価値の算定方法を争うことで、会社のキャッシュアウトをできる限り防止することになります。
(5)解散請求
経営者が著しく不適切な経営をしている場合、少数株主であっても、会社法第833条に基づき、会社の解散を裁判所に求めることができます。いわば最終手段と言えます。
これに対し、経営者は、会社経営の健全性を主張立証し、解散請求の棄却を求めて応訴することになります。
4.弁護士に依頼するメリット
会社の経営権・支配権争いに関して、弁護士に相談・依頼するメリットは多数ありますが、代表的なものは次の通りです。
なお、経営権・支配権紛争を解決するための法律である会社法は、様々な対処法を定めているものの、どれも短い権利行使期間を設定しているため、迅速な対応が必要となります。したがって、紛争の芽がある段階で弁護士との関係性を構築することを強く推奨します。
(1)法的知識と戦略の提供
経営権・支配権争いは、会社法などの専門的な法律知識を必要とします。弁護士は、株式取得の立案、株主総会の運営、訴訟対応などの戦略をアドバイスできます。
(2)交渉力と紛争解決
弁護士が介入することで、冷静かつ客観的な視点から相手方と交渉ができます。必要に応じて、調停や訴訟に進む前に、和解や交渉で解決する方法を模索できます。
(3)訴訟や法的手続きの対応
争いが激化した場合、株主代表訴訟や取締役の違法行為を巡る訴訟に発展することがあります。弁護士がいれば、法廷戦略の策定や裁判での対応がスムーズになります。
(4)ステークホルダーとの調整
経営権争いには、株主、取締役、従業員、金融機関など様々な利害関係者が関与します。弁護士が介入することで、各ステークホルダーとの調整をスムーズに進めることができます。
(5)会社の長期的な安定と成長を支援
法的な混乱を最小限に抑えつつ、会社の成長と安定を図るための助言を受けることができます。特に、紛争後の経営再建や、ガバナンスの強化を弁護士がサポートできます。
5.リーガルブレスD法律事務所における経営権紛争対応への強み
リーガルブレスD法律事務所の代表弁護士は、2001年より弁護士活動を開始すると同時に多くの経営権・支配権をめぐる予防策の構築や紛争対応を行ってきました。その中には、事業承継対策もあれば、兄弟間での主導権争い、遺産分割(相続)に絡んだものなども含まれます。
また、通算200社を超える顧問弁護士としての活動実績もあり、日常的に経営権・支配権トラブルの事例に接することから、多くの知見とノウハウを有しています。
さらに、法律知識のブラッシュアップはもちろんのこと、心理学や交渉術などの研鑽を積んでいます。
その上で、当事務所では、形式的な法律論だけで経営権・支配権問題を処理しないよう心がけています。なぜなら、非上場企業・中小企業における経営権・支配権をめぐる問題は人間関係(心情・感情など)が深く関わっており、形式的な法律論だけでは感情を逆なでにし、かえって問題解決が困難となる可能性が高いからです。
そこで、当事務所では、クライアント様にとって真のゴールはどこにあるのかを見定め、法律はゴールに導くための一手段に過ぎないと捉え、時間・労力・カネ等の合理性を勘案しつつ、クライアント様にとって最も痛みを伴わない柔軟な対処法をご提案するようにしています。
そして、ゴールに最短でたどり着けるのであれば、弁護士がステークホルダーとの直接交渉などを行うことにも厭いません。
クライアント様の不安、困惑、面倒を取り除き、最良のゴールに導くことができるよう尽力しますので、経営権・支配権紛争についてお悩みがあれば、是非リーガルブレスD法律事務所へお問い合わせください。
<2025年3月執筆>
※上記記載事項は弁護士湯原伸一の個人的見解をまとめたものです。今後の社会事情の変動や裁判所の判断などにより適宜見解を変更する場合がありますのでご注意下さい。