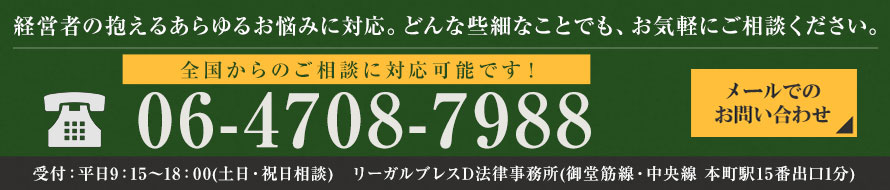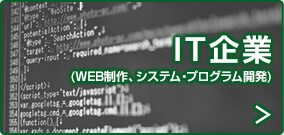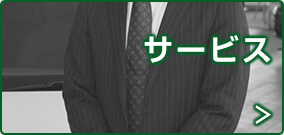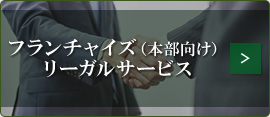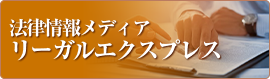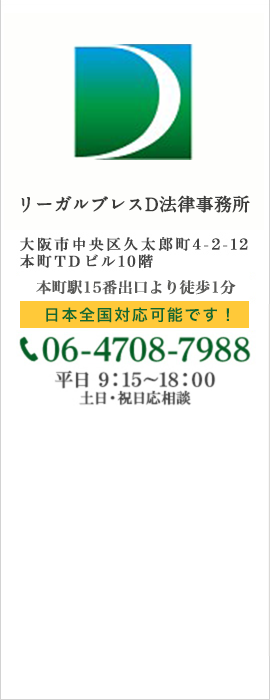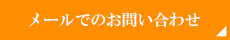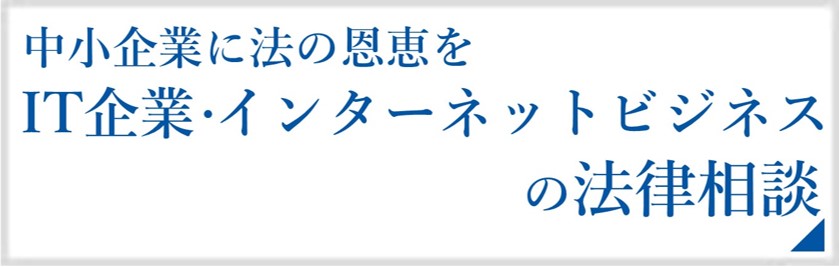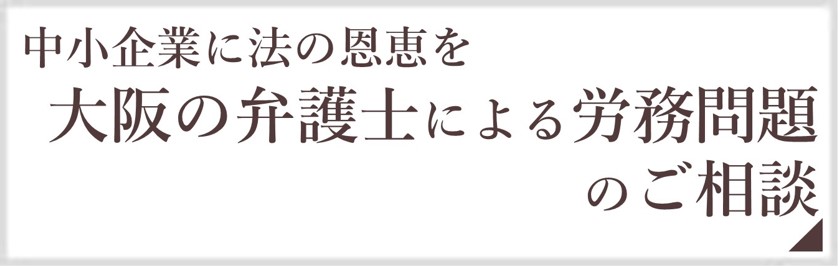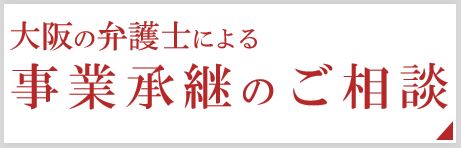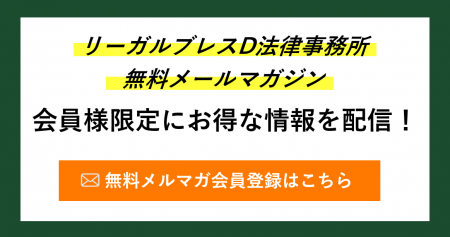役員(取締役)同士が対立したら会社はどうなる?会社が崩壊する前に知りたい法的知識
【ご相談内容】
現状維持派の役員と改革派の役員とで深刻な対立が発生しており、一触即発の状態となっています。
今度どういった事態が起こり得るのか、その対処法などを含めて教えてください。
【回答】
経営陣・役員(取締役)の対立は、反対派が会社内より一掃されるまで徹底的に行われることが多く、熾烈を極めます。
例えば、①通常時であれば誰も指摘をしなかった細かな手続き上のミス(ただし法令上は明らかに違反)を取り上げて、有利な結果を得ようとする、②過去の失敗を蒸し返し、相手を追い詰める手段として徹底的な責任追及を行う、③法令上利用可能な対抗手段がある限り、とにかく権利行使することで相手を困惑させる、といった特徴があります。
権利行使するにせよ、防衛策を発動するにせよ、会社法上どういった手段が存在するのかを知らないことには、上手く対処できません。
そこで、本記事では、経営陣・役員(取締役)間の対立でよく見かける4つのパターンを取り上げ、パターンごとで繰り広げられる法的紛争内容につき解説を行います。
本記事を読むことで、今後どういった事態が起こり得るのか予測可能となり、どのように対処するべきか道筋が見えるかと思います。
なお、本記事に出てくる会社は、取締役会設置会社を前提とします。
【解説】
1.なぜ経営陣・役員(取締役)間で対立が生じるのか
様々な原因が考えられますが、執筆者がこれまで取り扱った経験を踏まえると、おおよそ次の4つのパターンに分類されます。
①意思決定・方針を巡る対立
例えば、成長戦略・新規事業・リスク管理などといった経営方針、M&Aや大型投資の判断、
事業撤退やコスト削減策などへの対応を巡って、経営陣・役員(取締役)が対立する場合が該当します。
②業務執行を巡る対立
例えば、代表取締役の独断的な経営、他の取締役への情報共有不足、特定取締役の業務妨害行為などの対応を巡って、経営陣・役員(取締役)が対立する場合が該当します。
③経営責任を巡る対立
例えば、粉飾決算や法令違反行為、背任行為、利益相反や競業行為などへの対応を巡って、経営陣・役員(取締役)が対立する場合が該当します。
④地位・処遇を巡る対立
例えば、特定の取締役の解任要求、不当な解任や辞任の強要、役員報酬などの待遇などへの対応を巡って、経営陣・役員(取締役)が対立する場合が該当します。
以下では、それぞれのパターンで発生しうる法的紛争の概要等を見ていきます。
2.会社の意思決定・方針を巡る経営陣・役員(取締役)の対立
(1)意思決定のルール
会社法では、取締役会の権限につき次のように規定しています。
【会社法第362条】
| 1 取締役会は、すべての取締役で組織する。
2 取締役会は、次に掲げる職務を行う。 ①取締役会設置会社の業務執行の決定 ②取締役の職務の執行の監督 ③代表取締役の選定及び解職 3 取締役会は、取締役の中から代表取締役を選定しなければならない。 4 取締役会は、次に掲げる事項その他の重要な業務執行の決定を取締役に委任することができない。 ①重要な財産の処分及び譲受け ②多額の借財 ③支配人その他の重要な使用人の選任及び解任 ④支店その他の重要な組織の設置、変更及び廃止 (以下省略) |
そして、取締役会の決議は、原則として「出席取締役の過半数の賛成」によって行われます(会社法第369条第1項)。つまり、出席している取締役の過半数が賛成すれば、その決議は成立するという形での意思決定ルールを採用しています。
なお、取締役会においては、取締役の議決権を他人に委任することはできないと解釈されています。
(2)紛争類型
会社の意思決定・方針を巡る経営陣・役員(取締役)が対立した場合、次のような紛争が起こりがちです。
①取締役会決議の有効性を巡る紛争
取締役会で決議するためには、会社法上の細かな手続きを遵守する必要があるところ、上場企業を含め結構な割合で守られていないという実情があります。
例えば、次のような手続きです。
・適切な招集権者が招集したか(原則は定款等で招集権者となる取締役が決められている。それ以外の取締役が招集する場合は会社法第366条第2項、同条第3項に従う必要あり)
・適切な招集手続きが実施されたか(原則として1週間前に招集通知を出す必要あり)
・現実に会議を開催したか(いわゆる持ち回り決議は原則不可。なお、会社法第370条の要件を充足する定款の定めがあれば持ち回り決議が認められるものの、会社法第372条第2項に基づく3ヶ月に1回以上の割合で開催しなければならない職務執行状況の報告については持ち回り決議不可)
・決議に参加できない者が含まれていないか(会社法第369条第2項に定める特別利害関係人は、決議はもちろん、取締役会に出席、合議に参加すらできない)
経営陣・役員(取締役)が対立した場合、上記のような“手続き漏れ”を指摘して、取締役会決議の効力を争う、不適切な取締役会決議に基づく業務執行の有効性を争うという紛争が頻発します。
会社外の取引先等から見れば、“コップの中の嵐”であり関与したくないと思うものの、場合によっては取引行為が無効となるリスクもあることから放っておくわけにもいきません。とはいえ、迷惑な話であることは間違いなく、嫌気がさした取引先が離れていくといった悪影響も見られるところです。
②株主総会の開催を巡る紛争
経営陣・役員(取締役)の対立は、究極的には経営権・支配権争いに他なりませんので、株主総会にも波及します。
特に、取締役が少数派の株主である場合、真正面から株主総会決議で争うと負けてしまいますので、株主総会の開催自体を中止するべくあらゆる策を講じることになります。例えば…
・株主総会開催禁止の仮処分
・株主総会決議禁止の仮処分
といった裁判手続きを行うことがあります。
裁判を行うこと自体は止めようがありませんので、会社としては裁判手続きに対応せざるを得ません。ただ、時間・労力・金銭の負担が発生することはもちろん、何より機動的な会社運営ができないといった悪影響が生じます。
3.業務執行を巡る経営陣・役員(取締役)の対立
(1)業務執行のルール
取締役会設置会社の場合、業務を執行する者は次のように規定されています。
【会社法第363条第1項】
| 次に掲げる取締役は、取締役会設置会社の業務を執行する。
①代表取締役 ②代表取締役以外の取締役であって、取締役会の決議によって取締役会設置会社の業務を執行する取締役として選定されたもの |
そして、代表取締役等は、3ヶ月に1回以上の割合で、取締役会に対して職務の執行状況を報告する義務が課せられています(会社法第363条第2項)。
これに対し、取締役会は、代表取締役等の職務の執行状況を監督します(会社法第362条第2項第2号)。
(2)紛争類型
業務執行を巡る経営陣・役員(取締役)が対立した場合、次のような紛争が起こりがちです。
①代表取締役の解任
取締役会は代表取締役の職務執行に対して監督する義務があります。このため、代表取締役の職務執行に問題があると判断した場合、代表取締役の解任を検討することになります。
この点、代表取締役の解任は取締役会決議で対応するところ(会社法第362条第2項第3号)、取締役会決議は多数決原理が働きますので(会社法第369条第1項)、如何にして反代表取締役の多数派にするのかという駆け引きが発生します。
こうした駆け引きにエネルギーを取られると、どうしても会社経営が疎かになりますので、会社に深刻な被害を与えてしまうことは論を俟ちません。
ちなみに、仮に多数派を形成できたとしても、手続き上の不備などが生じ、上記2.(2)①で解説した取締役会決議の有効性を巡る紛争も起こったりします。
なお、代表取締役の解任は、代表権をはく奪するに過ぎず、取締役としての地位は残ったままです。取締役としての地位をはく奪するのであれば、株主総会の決議を経る必要があるところ、今度は株主総会の開催を巡る紛争が起こったりします。そして、株主総会で解任が否決された場合、少数株主による取締役解任請求訴訟(会社法第854条)が提起されるといった事態にもなったりします。
ここまでくると会社内部は混乱状態となり、取引先が離れることはもちろん、従業員も逃げ出すような事態に陥り、会社としての存続自体が危ぶまれることにもなりかねません。
②業務執行の差止め等
代表取締役の解任が難しい場合、少数派の取締役は、代表取締役による業務執行を中止させることができないかを考えることになります。
そこで、次のような裁判手続きを取れないか検討することになります。
・違法行為差止仮処分
・取締役職務執行停止の仮処分
・職務代行者選任の仮処分
まず、違法行為差止仮処分は株主及び監査役の権利であり、取締役の権利ではありません。このため、取締役が株主ではない場合は株主に権利行使を要請する、又は監査役に権利行使を働きかけることになります。なお、差止ですので、当然のことながら違法行為が行われる“前”に裁判手続きを実施する必要があります。
次に、取締役職務執行停止の仮処分は、文字通り取締役としての職務それ自体の停止を目指す手続きとなります(違法行為差止仮処分は、特定の業務執行の中止を目指す手続きです)。この仮処分が認められた場合、会社代表者としての業務執行が認められないことはもちろん、取締役会への参加、株主総会へ取締役として参加することなどが禁止されることになります。
最後の職務代行者選任の仮処分は、取締役職務執行停止の仮処分が認められた場合、会社を代表する者がいなくなる等の支障が生じますので、その代わりとなる者を選任するという手続きです。
いずれの裁判手続きにおいても、大変な労力と時間とお金を要することになりますので、会社の体力を奪うことは論を俟ちません。
③会社帳簿類・議事録の閲覧請求
経営陣・役員(取締役)の対立が生じた場合、相手を陥れるための証拠収集が必要となります。
そこで、会社の重要書類へアクセスし、情報収集を行うべく
・帳簿閲覧権
・株主総会議事録、取締役会議事録閲覧権
の行使が行われます。
もっとも、帳簿閲覧権は株主の権利として会社法で定められており、取締役の権利としては定められていません。取締役が帳簿閲覧権を有するかは解釈上の争いがあるところ、現場実務の影響力が大きい東京地裁の運用では、取締役の帳簿閲覧権を認めていないようです。
このため、取締役は株主に働きかける必要があります。
もっとも、閲覧範囲を巡って会社と株主とで紛争となる場合もあり(会社法第433条第2項)、法廷闘争となる場面もあり得ます。
次に、株主総会議事録と取締役会議事録の閲覧権についても、株主の権利として会社法上定められています。もっとも、個々の取締役もその職務執行に関係する限り、当然に議事録を閲覧することは可能と考えられます。
なお、議事録の閲覧範囲については、やはり会社と株主とで紛争となる場合があり(会社法第371条)、特に取締役会議事録については裁判所の許可が必要となる場合もあることから、法廷闘争に発展しやすい傾向があります。
いずれにせよ、法廷闘争に至った場合は、会社はそれ相応のダメージを免れることはできません。
4.経営責任を巡る経営陣・役員(取締役)の対立
(1)経営責任のルール
取締役には様々な義務が課されていますが、代表的なものは次の通りです。
【会社法第355条】
| 取締役は、法令及び定款並びに株主総会の決議を遵守し、株式会社のため忠実にその職務を行わなければならない。 |
忠実義務と呼ばれるものですが、会社法第330条では「株式会社と役員及び会計監査人との関係は、委任に関する規定に従う」と規定されている以上、取締役は当然に善管注意義務を負うことになります(民法第644条)。
よく耳にする“経営判断の原則”は、この忠実義務や善管注意義務違反にならないかという観点で議論の対象となります。
なお、忠実義務と善管注意義務の関係につき、特段相違が無いという解釈が一般的です。
【会社法第356条第1項】
| 取締役は、次に掲げる場合には、株主総会において、当該取引につき重要な事実を開示し、その承認を受けなければならない。
①取締役が自己又は第三者のために株式会社の事業の部類に属する取引をしようとするとき。 ②取締役が自己又は第三者のために株式会社と取引をしようとするとき。 ③株式会社が取締役の債務を保証することその他取締役以外の者との間において株式会社と当該取締役との利益が相反する取引をしようとするとき。 |
いわゆる競業禁止義務、利益相反取引の禁止に関する規定となります。
上記条文では株主総会の承認が必要と規定されていますが、取締役会設置会社の場合、取締役会の承認が必要となります(会社法第365条)。
【会社法第423条第1項】
| 取締役、会計参与、監査役、執行役又は会計監査人(以下この章において「役員等」という。)は、その任務を怠ったときは、株式会社に対し、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。 |
会社が取締役に対して、損害賠償責任を追及するための根拠規定となります。なお、会社法第423条2項以下では、損害の推定規定、過失の推定規定などが定められています。
(2)紛争類型
経営責任を巡る経営陣・役員(取締役)が対立した場合、次のような紛争が起こりがちです。
①損害賠償
取締役が任務を怠った場合に損害賠償責任が発生することは前述の通りです(会社法第423条第1項)。そして、この責任追及は会社が本来行うべきものですが、会社が行わない場合は株主が株主代表訴訟を通じて行うことになります。
ところで、任務懈怠は結果論で判断されるわけではありません。情報収集とその分析・検討に不備はなかったか、分析・検討により得られた事実に基づく推論過程や内容に不合理な点はなかったか、という経営判断プロセスを重視して任務懈怠の有無を判断します(経営判断の原則)。
このため、経営判断の原則が適用されるか否かを巡って、激しい論争となりがちであり、責任追及につき結論が出るまでには相当な時間(それに伴う労力と金銭負担)が生じることになり、確実に会社の体力を奪うことになります。
②利益相反
取締役が、取締役会の承認を得ずに利益相反取引を行い、会社に損害を与えた場合は当然に損害賠償責任を負います。
一方、たとえ取締役会の承認を得ていたとしても、会社に損害が発生した場合、利益相反取引を行った取締役は無過失で損害賠償責任を負う場合があります(会社法第428条第1項)。また、利益相反取引を行ってはいないものの承認をしたほかの取締役については、過失があったと推定されます(会社法第423条第3項)。
このように利益相反取引を行った場合、その承認をした取締役を含めて損害賠償責任を負う可能性が高くなるのですが、これが経営陣・役員(取締役)の対立が生じている場合、格好の攻撃材料となりえます。もっとも、利益相反取引のうち、特に間接取引と呼ばれるものについては、その範囲が不明確であるため、利益相反取引該当性を巡って紛糾しがちです。
この結果、会社の事業活動にはほぼ役に立たない紛争に力を注がれる結果、会社は徐々に衰退する等の悪影響を受けることがあります。
③競業取引
取締役が競業取引につき、取締役会の承認を得ることなく行ったことで会社に損害を与えた場合、損害賠償責任が発生するのは当然のことですが、損害額の算定が難しいという問題があります。そこで、会社法は、取締役等が得た利益を損害額と推定する規定を設けています(会社法第423条第2項)。
一方、取締役会の承認を得たものの、競業取引により会社に損害が発生した場合、個々の取締役に善管注意義務・忠実義務違反があれば損害賠償責任を負うことになります。
このように競業取引についても、経営陣・役員(取締役)の対立が生じている場合は格好の攻撃材料となるのですが、そもそも競業と言えるのか、任務懈怠があったと言えるのか等で論争となりがちです。
このため、取締役個人の責任追及に議論が集中し、会社が損害を被っている現状が度外視される傾向があります。この結果、確実に会社の体力が奪われ、気が付いたときは会社の事業継続が難しい状態に陥ることも実際にあったりします。
5.地位・処遇を巡る経営陣・役員(取締役)の対立
(1)地位・処遇のルール
取締役の地位や処遇については、次のように規定されています。
【会社法第339条】
| 1 役員及び会計監査人は、いつでも、株主総会の決議によって解任することができる。
2 前項の規定により解任された者は、その解任について正当な理由がある場合を除き、株式会社に対し、解任によって生じた損害の賠償を請求することができる。 |
労働者のような不当解雇規制が無い分、取締役は理由の如何を問わず簡単に解任されてしまうという点では、地位が不安定となります。もっとも、正当事由が無い限り、解任された取締役は損害賠償請求ができますので、安易な解任に対する一種の抑止力は働くことになります。
【会社法第361条第1項】
| 取締役の報酬、賞与その他の職務執行の対価として株式会社から受ける財産上の利益(以下この章において「報酬等」という。)についての次に掲げる事項は、定款に当該事項を定めていないときは、株主総会の決議によって定める。
(以下省略) |
取締役の報酬については株主総会の決議が必要ですが、その決議に基づき、取締役と委任契約を締結し報酬額を定めた場合、事後的に報酬額を株主総会で変更するはできません。
この意味では、取締役の処遇は守られていると言えます。
(2)紛争類型
地位・処遇を巡る経営陣・役員(取締役)が対立した場合、次のような紛争が起こりがちです。
①解任
株主総会で多数派につく取締役が目障りな取締役を解任しようとする、一方で当該取締役が上記2.(2)②で解説したような対抗手段を講じること以外に、例えば、「役員の地位を仮に定める仮処分」といった裁判手続きを行ってくる場合があります。
いずれにせよ法廷闘争を通じて泥沼化しますので、取引先や従業員などを含むステークホルダーからの会社に対する信用力低下を免れることはできません。取引の打ち切りや従業員の退職など負の連鎖を生む場合さえ有り得るところです。
②報酬の減額
取締役会で多数派につく取締役が、対立する取締役の報酬減額を取締役会で決議する、あるいは株主総会で報酬の減額を決議するといった画策を行うことがあります。
一見すると報酬減額は有効になるように思われるかもしれません。
しかし、取締役の就任に際し、取締役は会社と(準)委任契約を締結しています。契約を締結している以上、一方の都合で契約内容を変更することは法的に許されません。これは取締役会決議や株主総会決議があっても同様です。
したがって、上記のような画策は無効であり、減額された取締役は不支給分の報酬支払いを求めて会社を訴える、違法行為を画策した個々の取締役に対して損害賠償請求を行うといった事態を招くことになります。
一方的な報酬減額は、会社自らが内外にコンプライアンス意識がないことを表明する恥さらしであり、コンプライアンス重視の昨今の風潮には相反するものです。
6.弁護士に依頼するメリット
経営陣・役員(取締役)間の対立や内部紛争は、「単なる人間関係のトラブル」と片付けられる問題ではありません。
取締役会の決議無効、株主総会の開催阻止、代表取締役の解任劇、損害賠償請求、帳簿閲覧請求、役員報酬の争い…。
これらはすべて法的手続きの舞台となり、会社の信用・機動性・事業継続性に深刻なダメージを与えることになります。
こういったダメージを予防し、あるいは最小限の被害に抑えるべく、弁護士を活用するのが最良の策であると共に、次のような5つのメリットがあります。
①法律に基づく正当な対応ができる
感情や力関係ではなく、会社法や民法に基づいた「筋の通った対応」を設計できます。
②相手の出方を先読みした戦略が立てられる
内部紛争は相手の動き次第で一気に泥沼化します。経験豊富な弁護士であれば、先手を打つことが可能です。
③裁判・仮処分・株主代表訴訟への備えができる
不意打ちの仮処分申立や株主代表訴訟への的確な対応により、会社へのダメージを最小限に抑えられます。
④取締役会・株主総会の運営が「合法的に」安定する
適法な招集、議事録の整備、特別利害関係人の排除など、会社の意思決定の「法的安定性」を守ることができます。
⑤ステークホルダー(取引先・社員・株主)への悪影響を最小化
弁護士の関与によって、第三者から見た「安心感・信頼感」が高まり、会社の信用失墜を防げます。
【重要なポイント】
「弁護士に相談するのは揉めた後」では手遅れです。
内部紛争が表面化したときには、すでに会社の信用は揺らいでいるかもしれません。
経営陣・役員(取締役)同士の対立は、早期に法的な視点から整理しなければ、「気がついたら会社が立ち行かない」という事態にもなりかねません。
7.リーガルブレスD法律事務所における経営陣・役員(取締役)対立対応への強み
リーガルブレスD法律事務所の代表弁護士は、2001年より弁護士活動を開始すると同時に多くの会社内部で生じうるトラブル予防策の構築や紛争対応を行ってきました。その中には、事業承継や後継者争い、M&A後の主導権争い、社内体制の変更に絡んだものなど多種多様なものが含まれます。
また、通算200社を超える顧問弁護士としての活動実績もあり、日常的に社内紛争や権力争いの事例に接することから、多くの知見とノウハウを有しています。
さらに、法律知識のブラッシュアップはもちろんのこと、心理学や交渉術などの研鑽を積んでいます。
その上で、当事務所では、形式的な法律論だけで経営陣・役員(取締役)間の対立問題を処理しないよう心がけています。なぜなら、非上場企業・中小企業における経営陣・役員(取締役)対立は人間関係(心情・感情など)が深く関わっており、形式的な法律論だけでは反感を招き、かえって問題解決が困難となる可能性が高いからです。
そこで、当事務所では、クライアント様にとって真のゴールはどこにあるのかを見定め、法律はゴールに導くための一手段に過ぎないと捉え、時間・労力・カネ等の合理性を勘案しつつ、クライアント様にとって最も痛みを伴わない柔軟な対処法をご提案するようにしています。
そして、ゴールに最短でたどり着けるのであれば、弁護士がステークホルダーとの直接交渉などを行うことも厭いません。
クライアント様の不安、困惑、面倒を取り除き、最良のゴールに導くことができるよう尽力しますので、経営陣・役員(取締役)間での対立問題についてお悩みがあれば、是非リーガルブレスD法律事務所へお問い合わせください。
ご相談は早い段階で行うほど、有利な選択肢を確保できます。
<2025年3月執筆>
※上記記載事項は弁護士湯原伸一の個人的見解をまとめたものです。今後の社会事情の変動や裁判所の判断などにより適宜見解を変更する場合がありますのでご注意下さい。